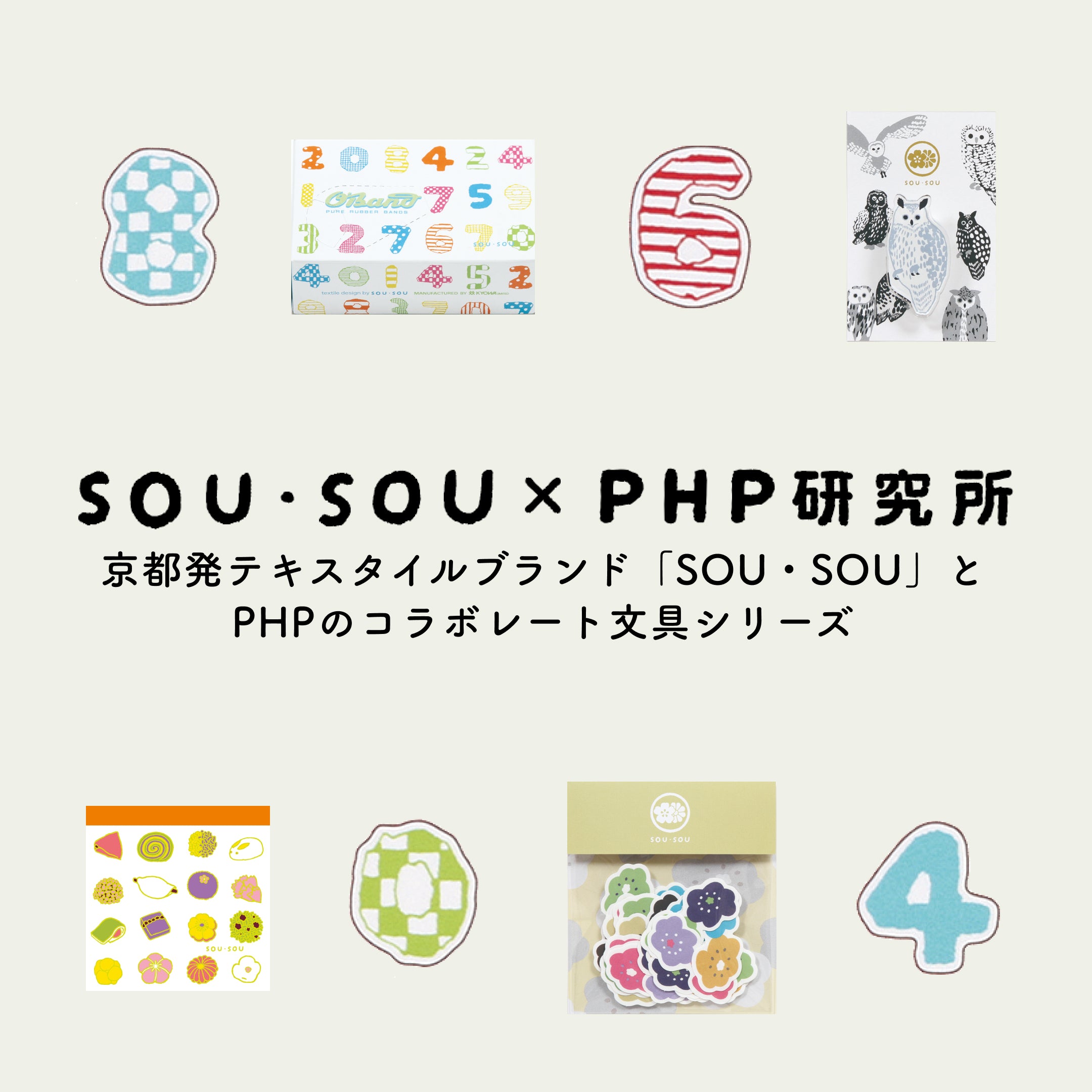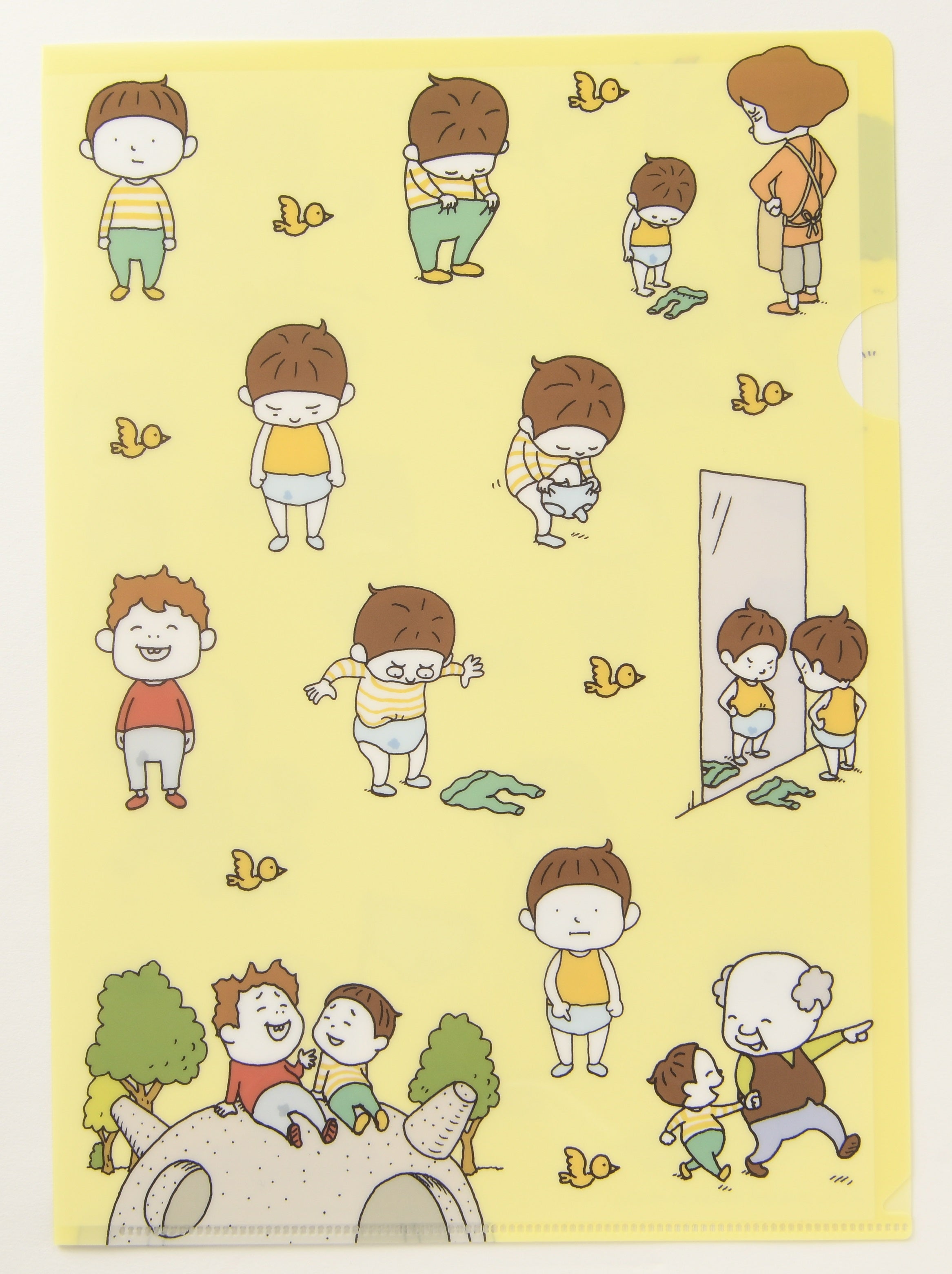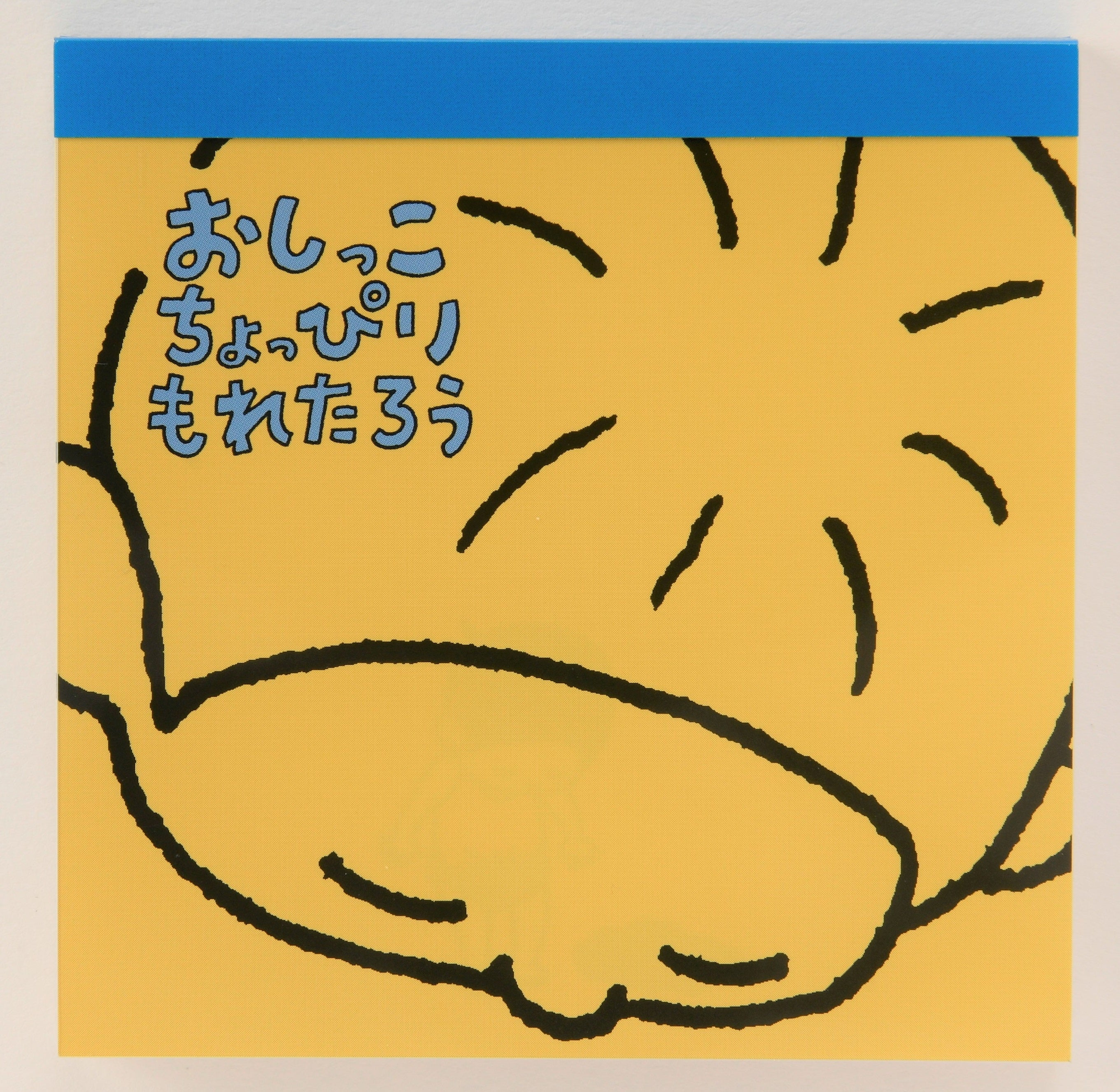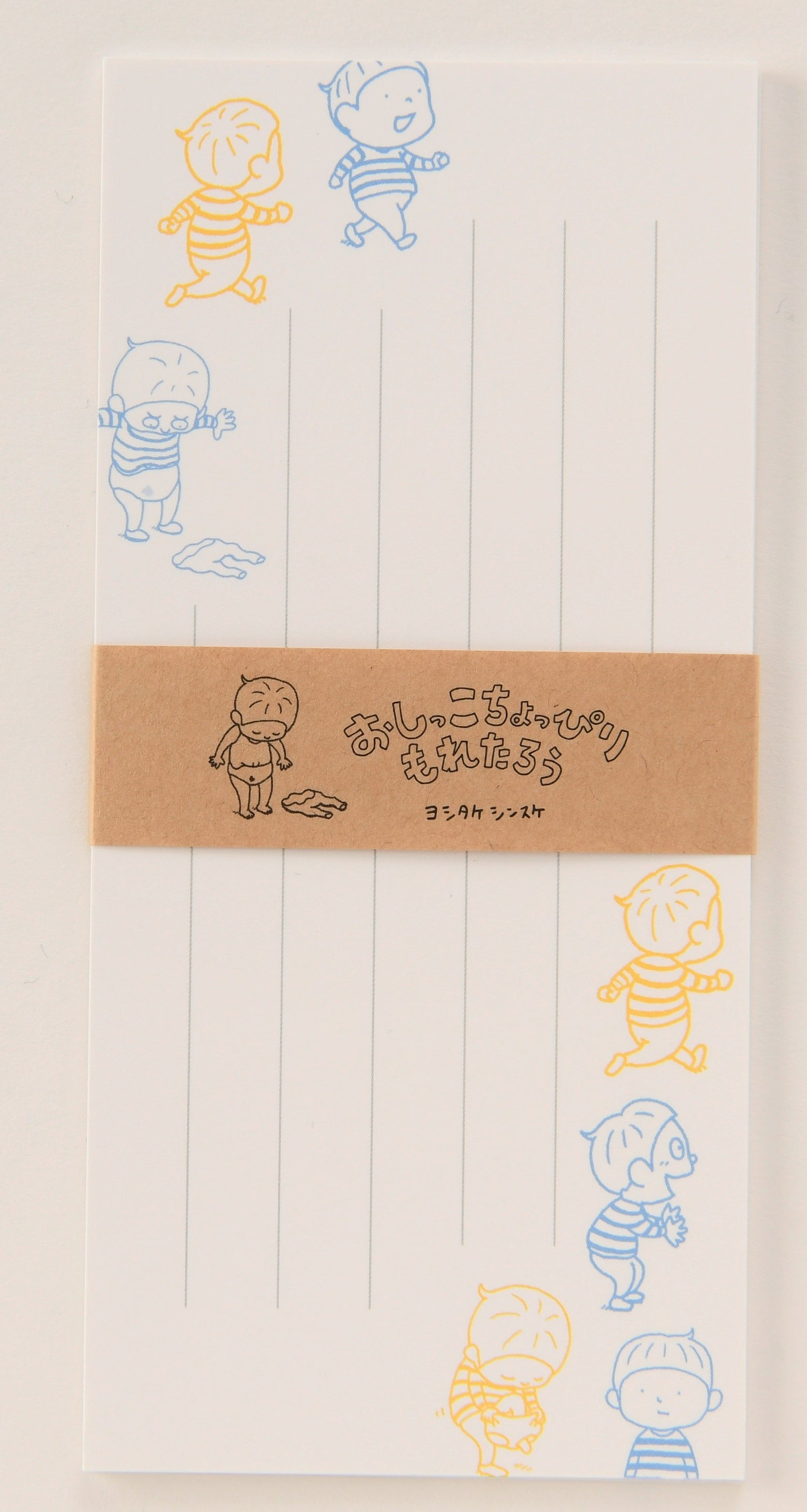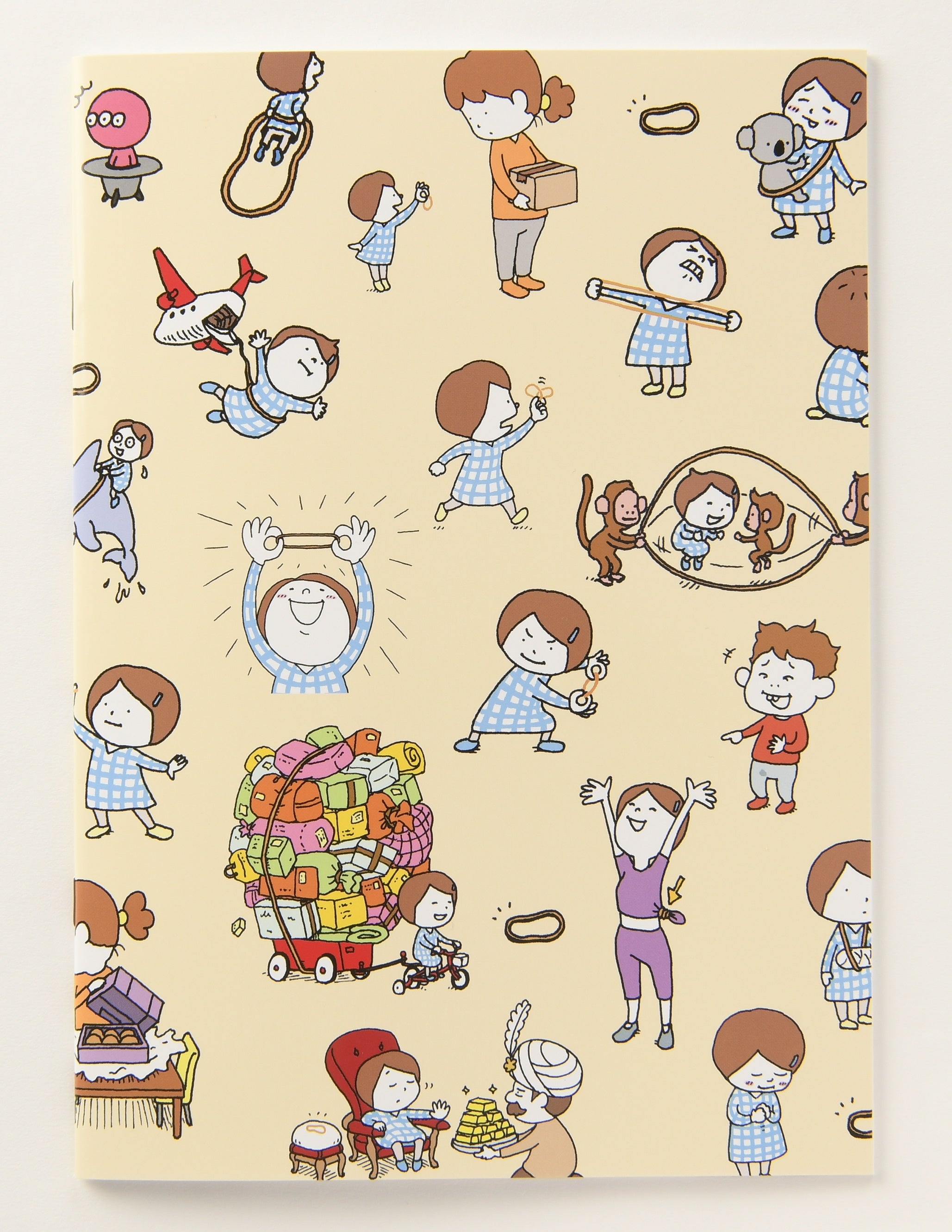発達障害・グレーゾーンの「子どもの脳」にちゃんと伝わる「声かけ変換」
発達障害・グレーゾーンの「子どもの脳」にちゃんと伝わる「声かけ変換」
「ウチの子って、もしかして発達障害?!」
そんな不安を覚え、この本を手にとられた親御さんが多いと思います。
あるいは、すでにお子さんに発達障害の診断がなされ、今後どのように対応したらよいのか、この子は将来ちゃんと自立できるだろうか……そんなふうに悩んでおられる方も少なくないでしょう。
まずお伝えしたいのは、お子さんに発達障害の特性やグレーゾーンの傾向があったとしても、早い時期にお子さんの特性や傾向を知り、それに応じた適切な対応や療育を行ない、適切な環境を選べば、お子さんはきっと幸せで実りある人生を送ることができるということです。
今思えば私の両親は、かなり早い時期から私の特徴を理解していました。その特徴の中には、今では「発達障害特性」と呼ばれるものも多く含まれますが、その都度適切な対応をしてくれていました。私自身は十代の頃に学校への適応に非常に苦しんだものの、それをきっかけに視野を広げ、自分自身を分析し、自分に合った生き方をすることができるようになりました。
ですから、お子さんの現状と将来を案じておられる親御さんたちに対し、自らの体験も交えながら、「心配しなくても大丈夫ですよ」とお伝えしたく、本書を上梓しました。
発達障害の診断がなされる人は、過去30年の間におよそ50倍も増えています。これは「発達障害そのものが増えた」のではなく、「発達障害と診断される人が増えた」というのが正確な表現です。
発達障害の特性のひとつである「多動」や「不注意」が目立つ子どもがいても、ひと昔前であれば「わんぱくで、ちょっとおっちょこちょいな子」として、周囲も比較的寛容に受け入れていたと思います。
友だち関係が苦手な傾向があっても、マンガを描くのが上手などの特技があれば、自然と周りに人が集まってきて、クラスでも一目置かれるような存在であることもできたと思います。
ところが近年は、「多様性の時代」とは名ばかりで、世の中で求められているのは「忘れものをしない」「コミュ力(コミュニケーション能力)が高い」人たちで、苦手なこと、難しいことがどうしても多くなりがちな発達障害の特性がある人にとっては、「生きづらい」社会となっています。小学生以下のお子さんも、それは例外ではありません。
加えて、「発達障害」という言葉が一般に広く浸透したことも、発達障害と診断される人の増加にさらに拍車をかけています。詳しくは本文に記載させていただきますが、程度の差はあれども、多くの人に発達障害の特性は存在します。
それなのに、その特性と周りの人が求めていることがマッチしないと、表面的な理解で「あの子、発達障害じゃない?」という話になります。そして、周りの人は発達障害についての理解を深めることも対応について学ぶこともなく、お子さんが医療機関の受診を促されることも稀ではありません。
これは単純な多数決の問題で、数が多いほう(定型発達だと思っている人たち)が、数が少ないほうを集団から排除しているという構図なのです。
一方、発達障害の診断がなされて、「気持ちがラクになった」とおっしゃる親御さんも、数多くいらっしゃいます。お子さんの発達障害の特性は、「親の躾が悪いから」という誤解がいまだにありますが、発達障害は生まれ持った脳機能の特性(クセ)であり、躾とは関係がありません。しかし、お子さんが〝生きづらさ〟を克服し、実りある人生にしていくには、親御さんの適切な関わりが欠かせないことも事実です。
発達障害とひと口に言っても一人ひとりに個性があり、診断名だけではお子さんの特性は捉えきれません。発達障害は「社会との摩擦」という面がありますから、発達障害に対して、「医療だけで対応できること」には限界があります。
お子さんのいちばん身近にいる親御さんが主体となり、まずはお子さんの特性やお子さんの生きる社会のニーズをしっかりと理解し、それらに応じた適切な関わりを日常的に行なっていただくことが大切です。
難しいことではありません。日常的な「声かけの仕方」や「関わり方」「見守り方」をほんの少し工夫するだけで大丈夫です。
本書では、発達障害(いわゆるグレーゾーンも含みます)のお子さんの脳の中で起こっていることが想像できる機能を7つに分類し、それらの不具合によって生じる「困りごと」や「社会・周囲との摩擦」をできるだけやわらげたり解消したりするための具体的な「声かけ例」や「関わり方」を紹介しています。
親御さんがつい口にしがちな「NGワード」を挙げ、それをうまく変換するための考え方やコツ、変換後の適切な声かけ例を併せて提示することで、納得しながら実践できるようにしています。
親御さんの言葉というのは、想像以上にお子さんの心の発達に大きな影響を及ぼします。毎日「NGワード」を浴びせかけていると、発達障害かどうかに関係なく、お子さんはストレスを抱えて心の発達に悪影響が出ます。
逆に、適切な「声かけ」を心がければ、お子さんはストレスから解放され、心の健全な発達が促されます。
繰り返しになりますが、発達障害は生まれ持った特性と、生きている社会のニーズとの間の「摩擦」に由来します。その特性は生涯を通して大きくは変化しませんが、生きる社会を選ぶことで長所にも短所にもなりえます。
お子さんにとって親御さんは「最初の社会」であり、選ぶことができません。親御さんがお子さんにとって「適切な社会」を提供することで、お子さんは自己肯定感を高め、一般社会の中で生きる力(実行機能)を向上させます。
親御さんの手を離れ、自分で生きる社会を選ぶようになったあとのお子さんの人生を豊かで充実したものにするためには、実は幼少期の日常の声かけや関わりが非常に重要です。
本書の内容が、お子さんの心の発達を願う親御さんの助けとなることを、心より願っています。 (「はじめに」より)
青木悠太
縦:21×横:14.7 全頁数:176
重量334g厚さ1.2cm
97 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした