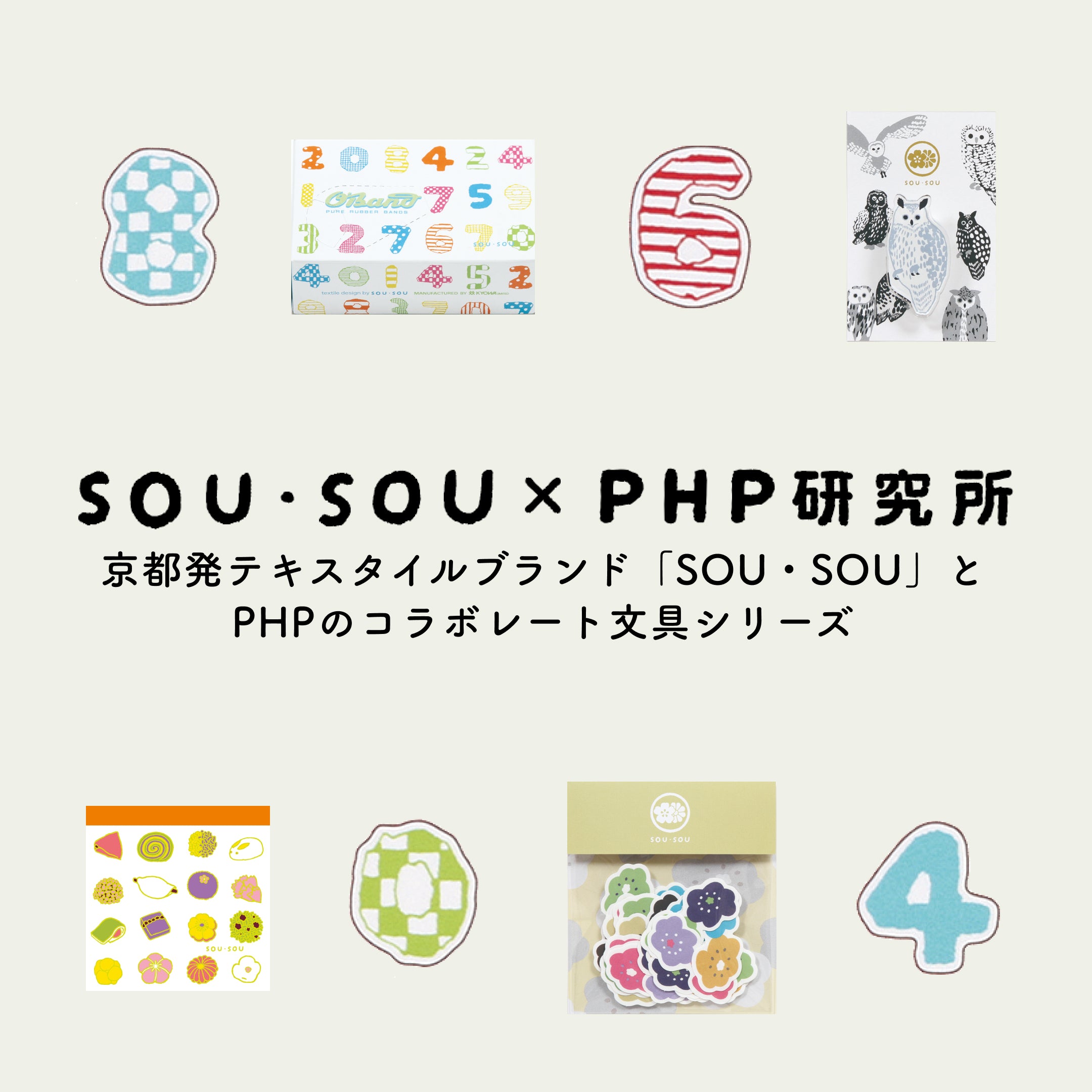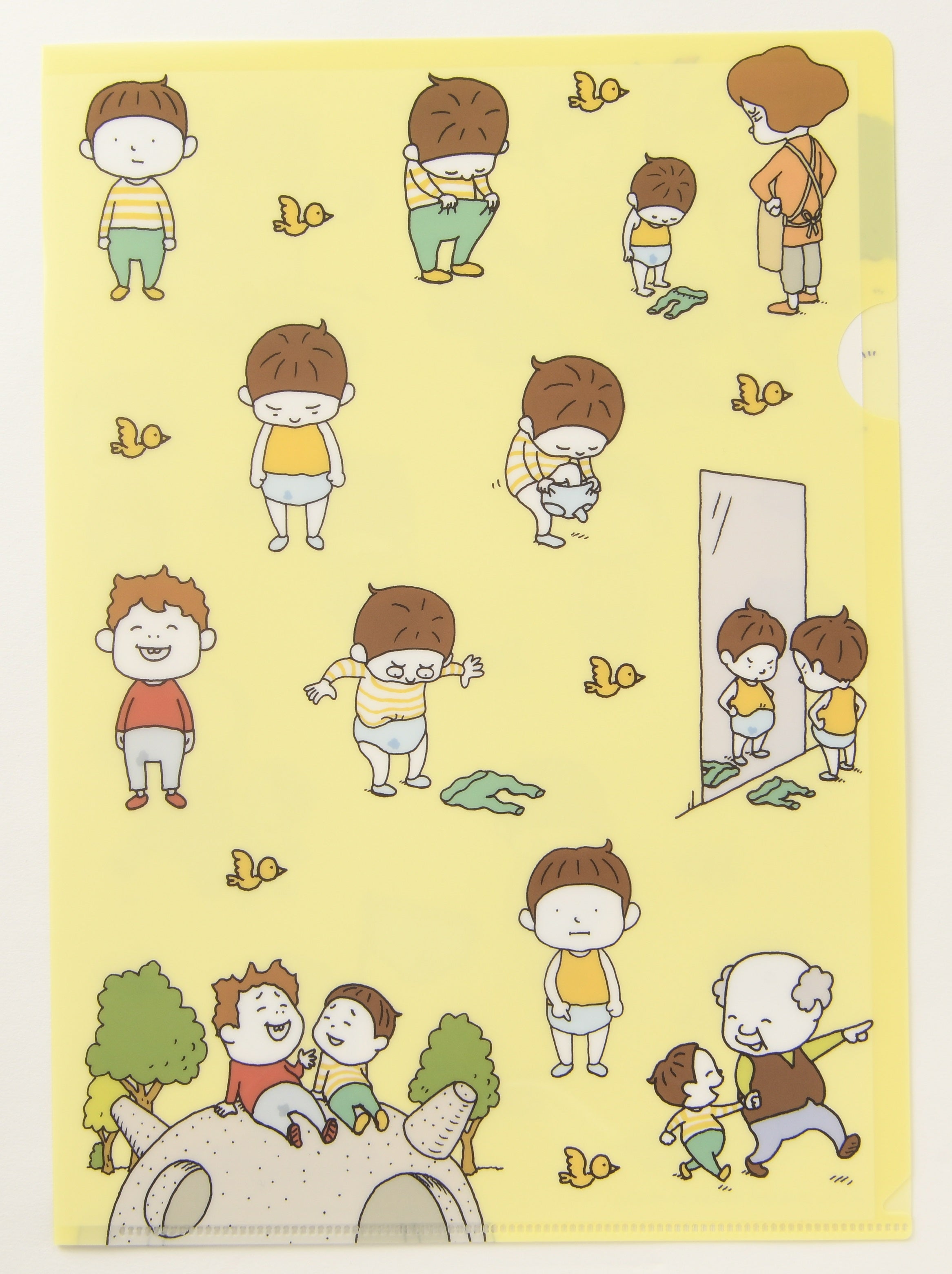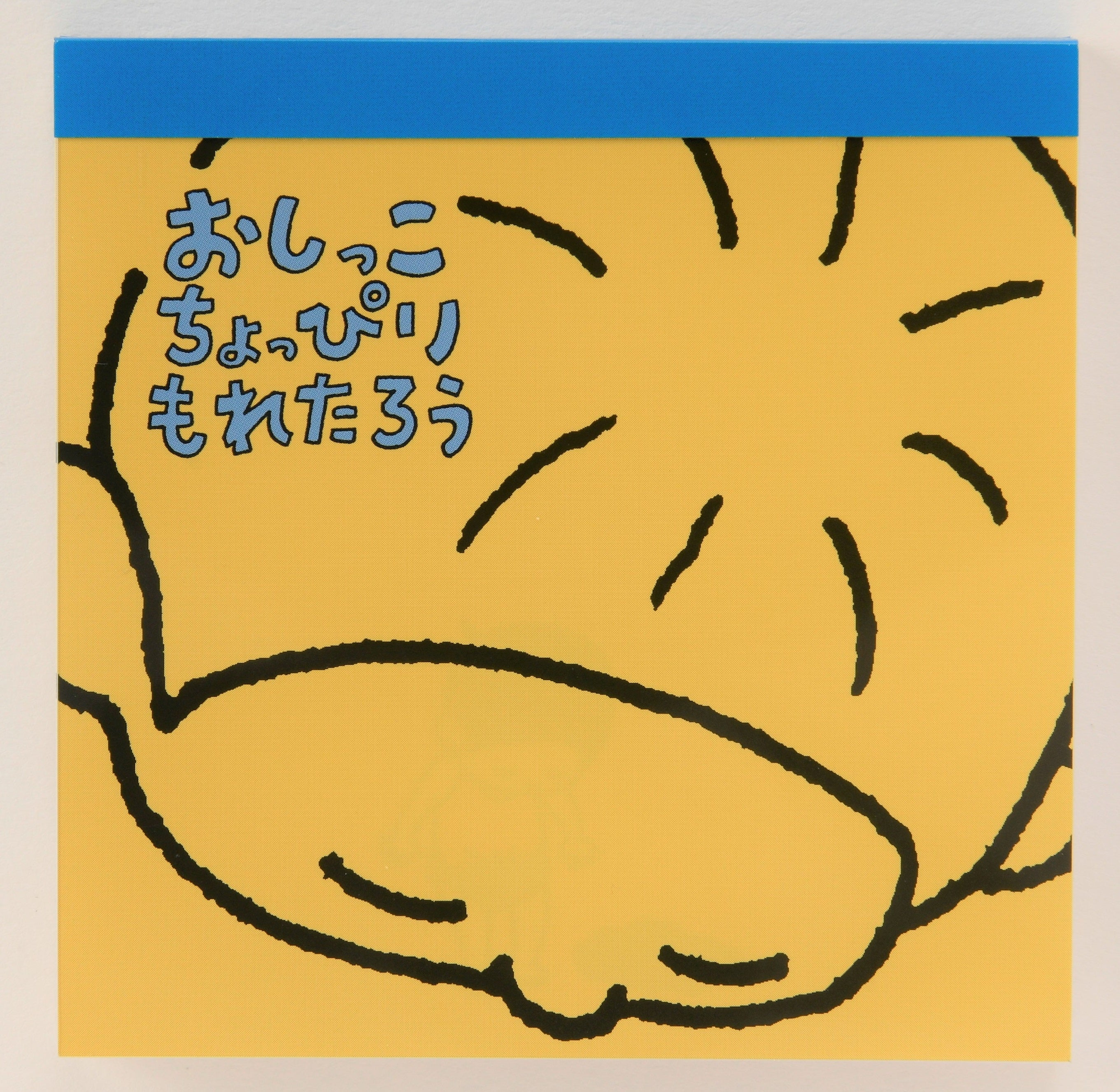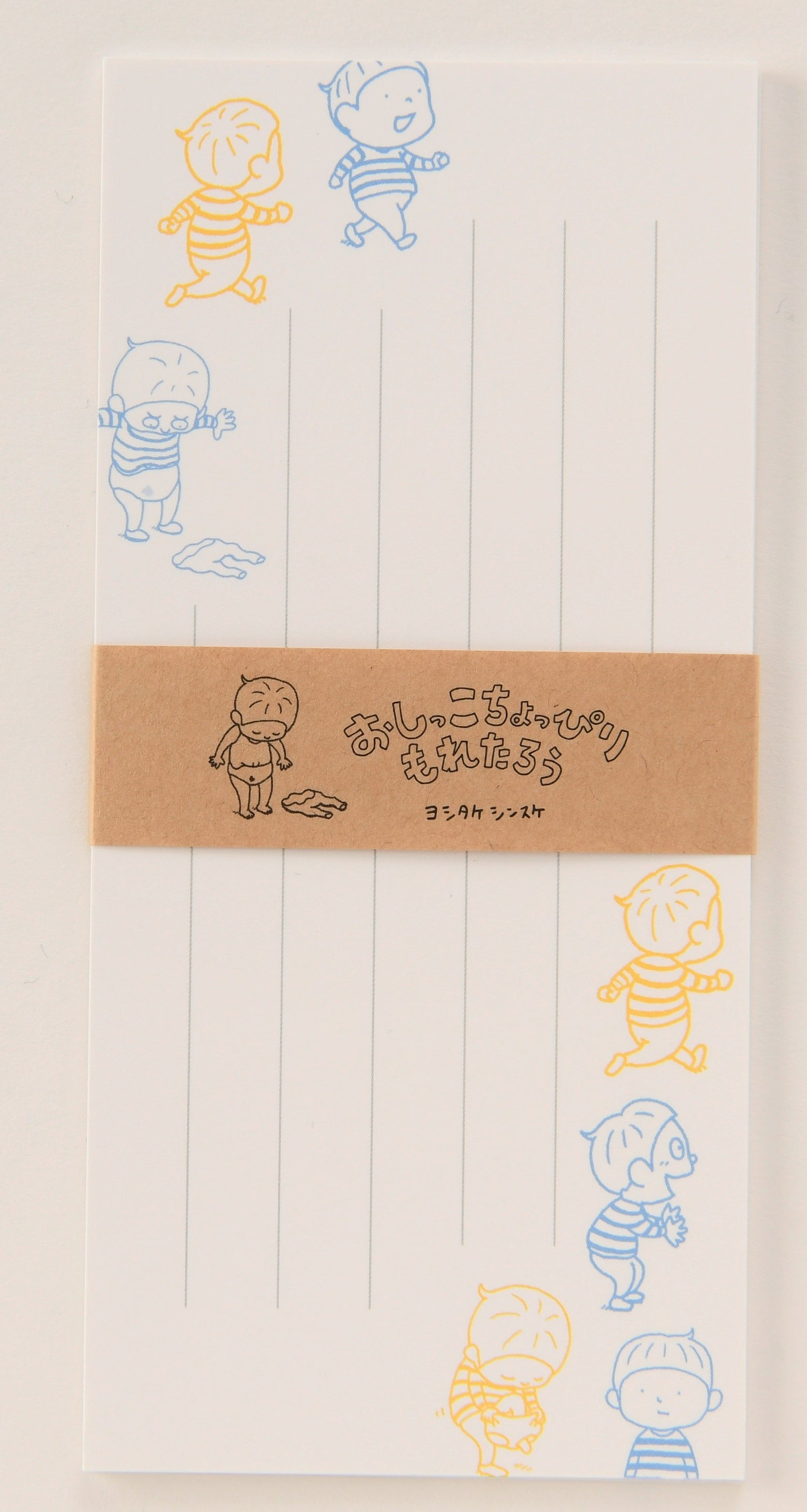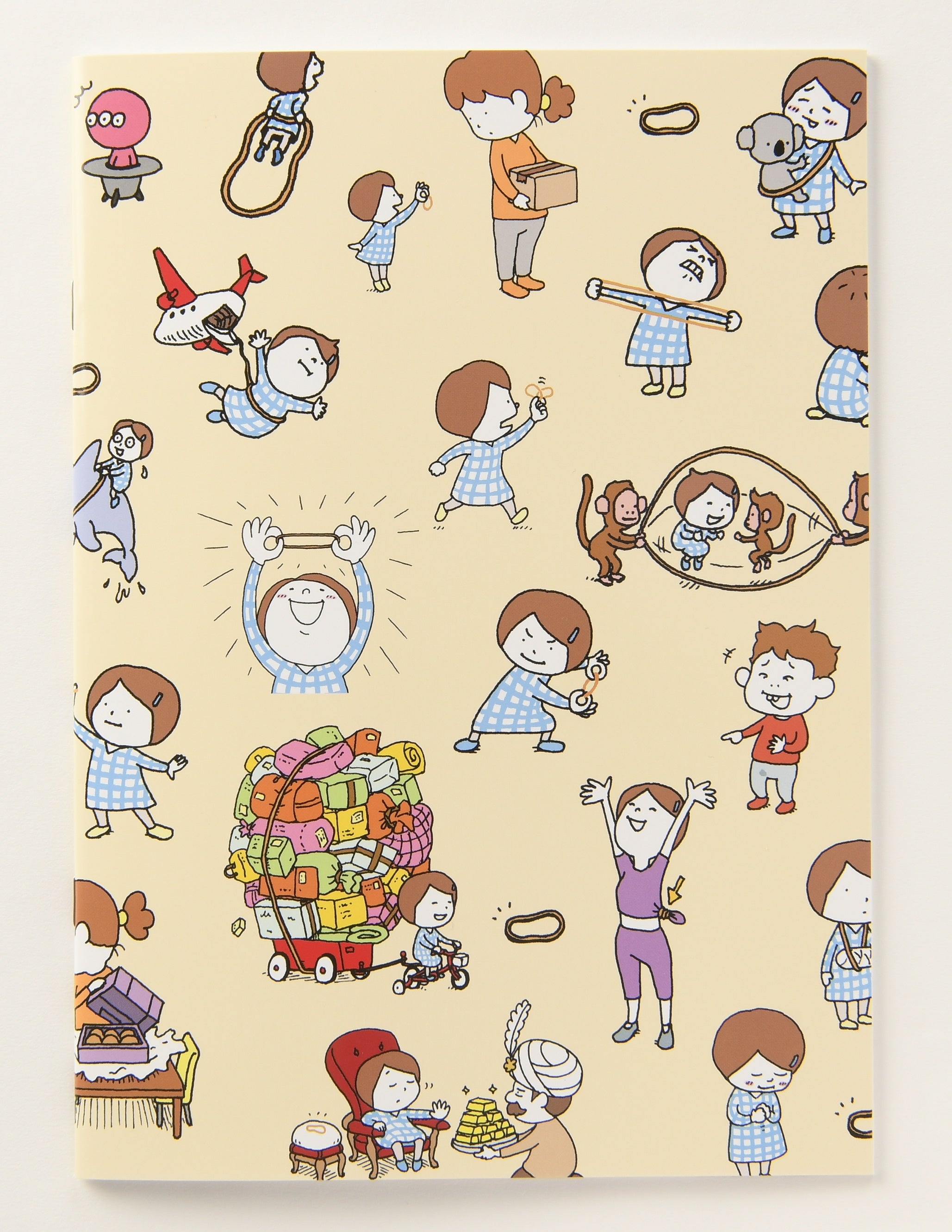心と体が整う 「おうち薬膳養生」12か月
心と体が整う 「おうち薬膳養生」12か月
皆さんは季節にどんな印象を持っているでしょうか。二十四節気という言葉を聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。
季節によって何か影響があるの? と思うかもしれません。はたまた、立春だの冬至だの天気予報では聞くけれども、風情や教養のある人が知っていることでしょう? と思うかもしれません。季節の話をすると、現在はネガティブな面ばかりが見えるかもしれません。冬は寒い、夏は暑い、梅雨は湿気が多くて、春は花粉症で天候が変わりやすくて……どの季節も辛いと言われる方がたくさんいらっしゃいます。
特にここ数年は猛暑が続き、大規模な自然災害も起こり、気候の激しさが増していると感じる人も多いのではないでしょうか。無用の長物のように感じる季節の言葉ですが、実は体調を管理したり整えたりするのにとても重要な役割を担っているのです。
私は夫の鍼灸治療院で日々、患者様に漢方をお出ししたり、薬膳のアドバイスをしたりしています。体の不調というのは実にいろいろな要因で起きています。1つの要因ということはまずなく、大抵は複数の要因が重なって起きています。
その中でも季節に影響を受けた要因はとても多いです。体質や生活習慣などさまざまな要因がありますが、季節に関係した要因がない人はほぼいません。
例えば、夏は熱中症や夏バテがありますが、この暑さや湿気への対策、皆さんはどうやってしているでしょうか。
クーラーをしっかりつける? 水分補給を心がける?
もちろんそれらも大切なことです。でも東洋医学の知恵を使えば、実は自分でできる対処法がもっとたくさんあるのです。昔の人たちはクーラーも冷蔵庫もない時代でも季節を上手に乗り切るように気をつけてきました。それは「季節に体を合わせて過ごす」ということです。昔の人は季節に対応できなければ死んでしまう可能性が高かったわけですから、季節に対応できるかは一大事だったのです。
東洋医学の礎となる『黄帝内経』の「四気調神大論」には、季節による過ごし方が書かれています。季節ごとの生活養生や、どんな心持ちで過ごすべきかが載っているのです。また、「五運六気」といって、その年の天候を予測する内容もあります。農業をはじめ、国を治めることに天候が大きく影響する時代で、現代より天候の予測が重要視されていたのだと思います。そして病になって倒れないためにも、この天候を知ることが大切だったのです。
東洋医学には三因制宣という言葉があります。
因人、因時、因地、つまり、体質によって、季節によって、住んでいる土地によって、治療法を考えるということです。
最近では気象病という言葉も見受けられるようになりましたが、気温や気圧など天候によって不調となる症状のことを指すようです。実は東洋医学ではずっと昔から気象病といえるものを取り扱ってきました。
季節に合わせた過ごし方ができれば、季節から受ける不調の要因がぐっと減るわけです。季節に合わせてうまく過ごすことができないために、その季節だけでなく、1年中不調になってしまっている人もいます。私たちは季節をコントロールすることはできません。暑い夏に逆らって過ごせば熱中症になりますし、雨の多い秋に逆らえば体のむくみも増します。逆に季節、天候に合わせて過ごせば、大きな不調もなく心穏やかに楽しく過ごせるのです。
季節は悪い面ばかりではなく、良い面もたくさんあります。その良い面を享受できるようになれば、自然の力を味方につけて、もっと元気になることもできるのです。季節の養生は季節を重ねるごとに少しずつ体も心もラクになってきます。1か月後、3か月後、1年後にはきっと、季節の移ろいが楽しめていると思います。 (「はじめに」より)
著者:瀬戸佳子
縦:25.7×横:18.2 全頁数:208ページ
重量374g厚さ1.6cm
99 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした