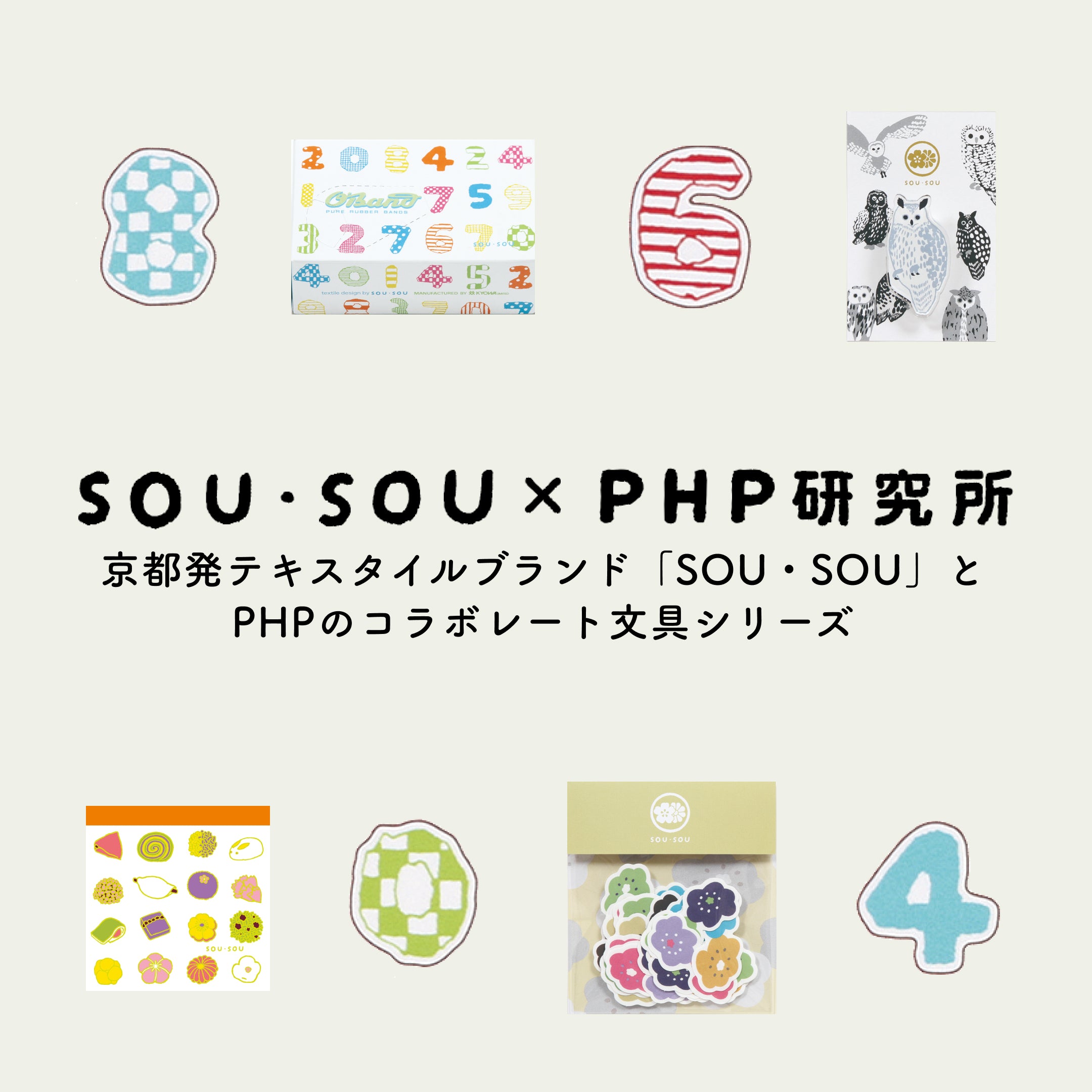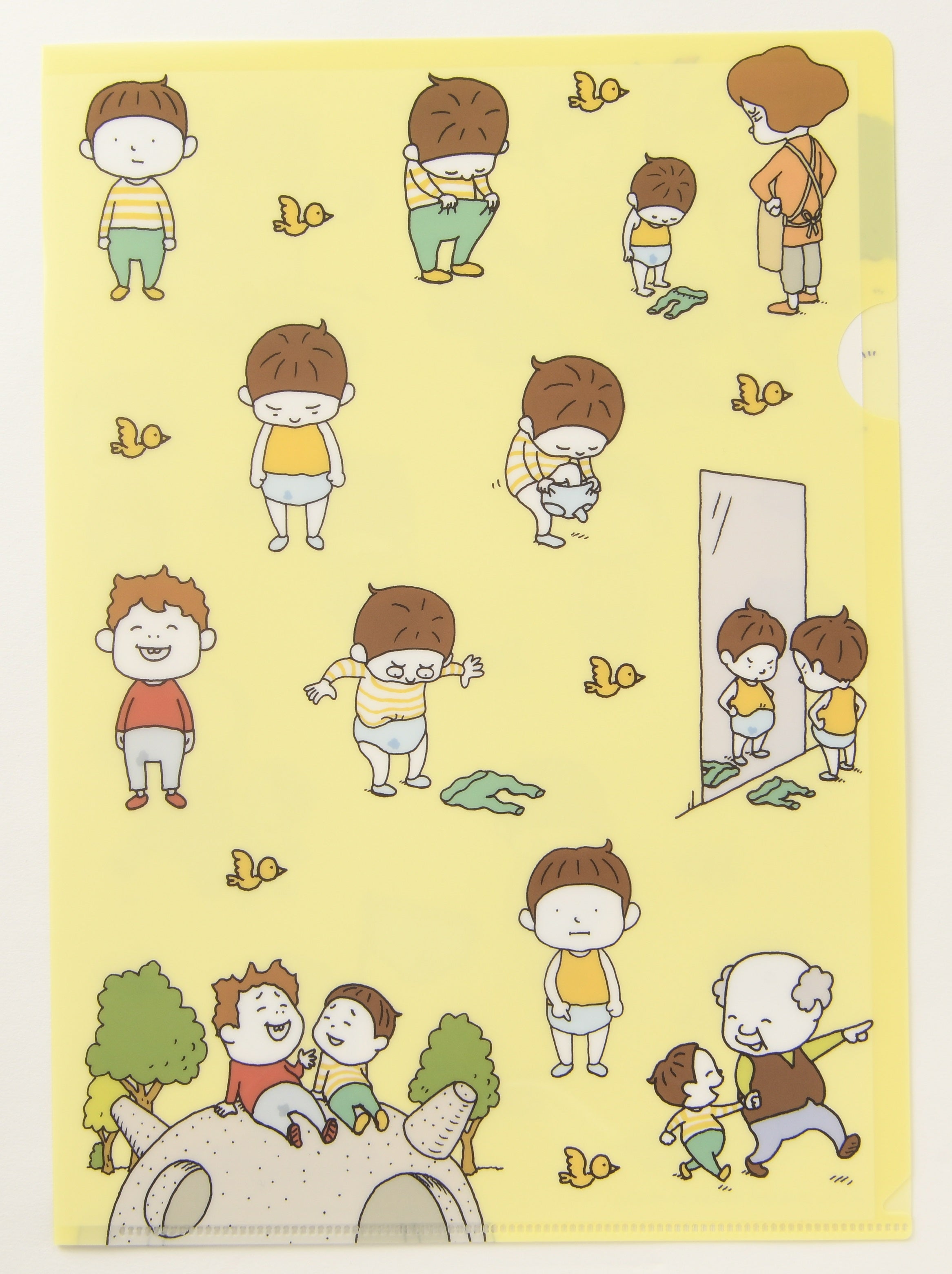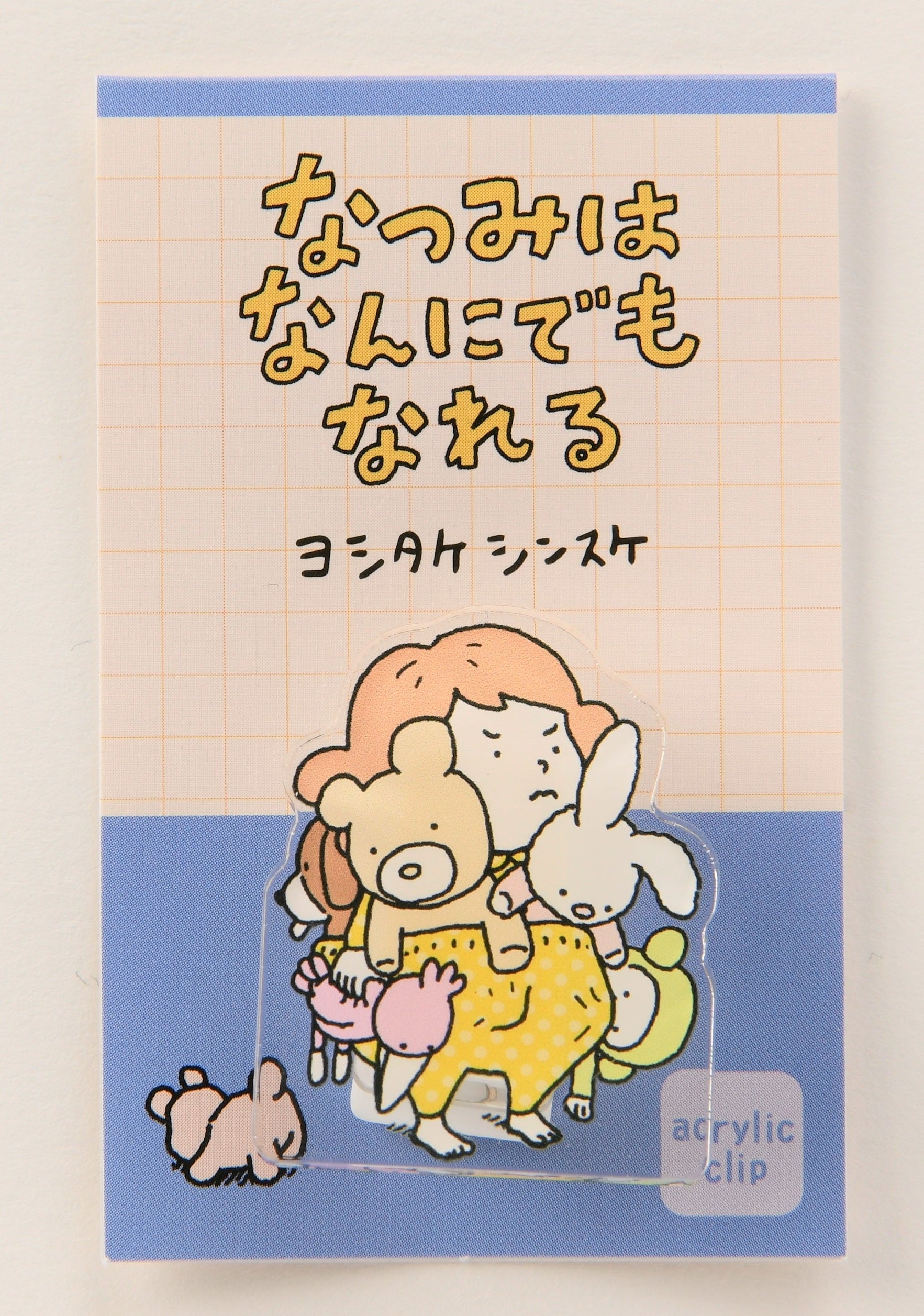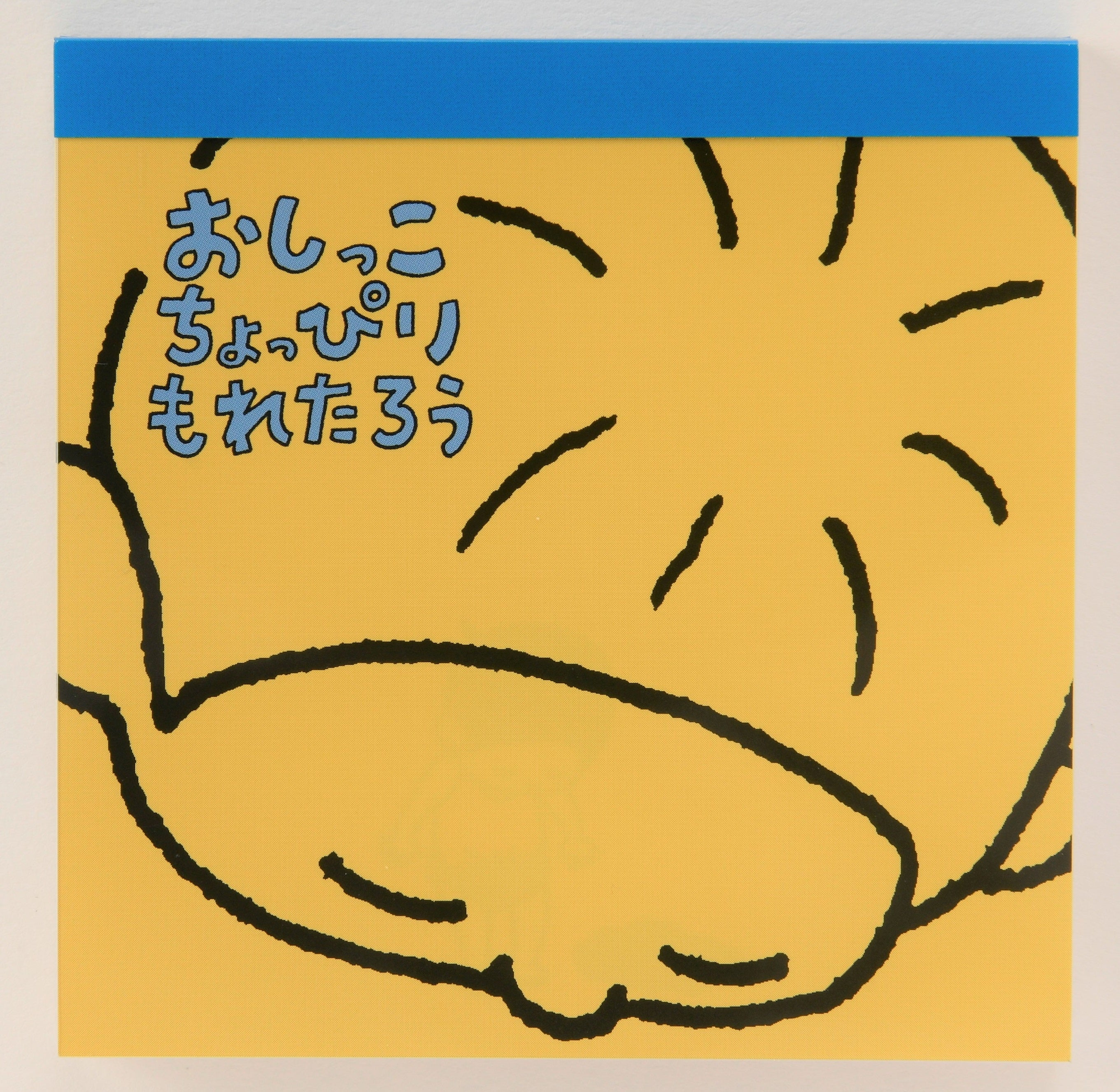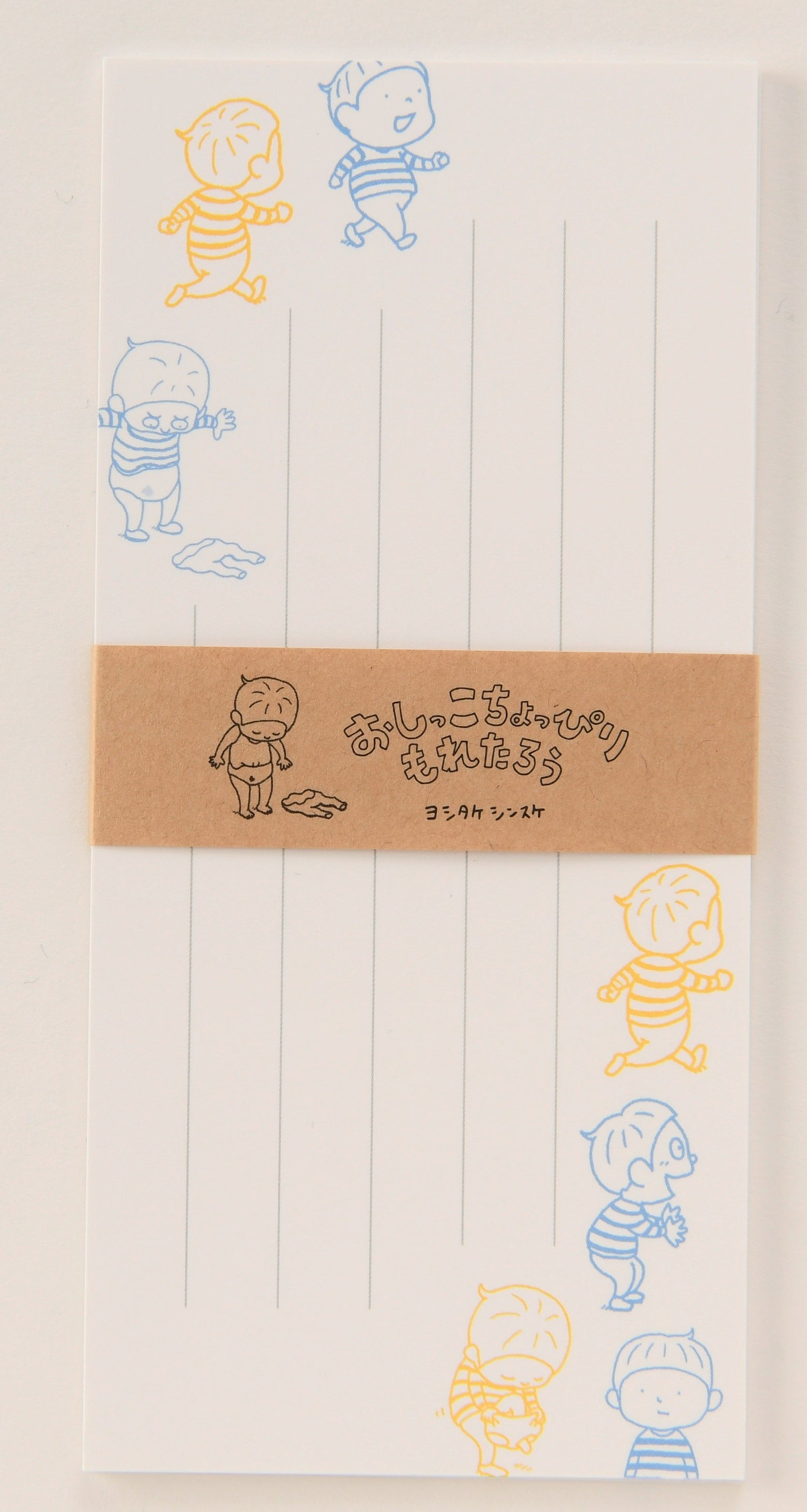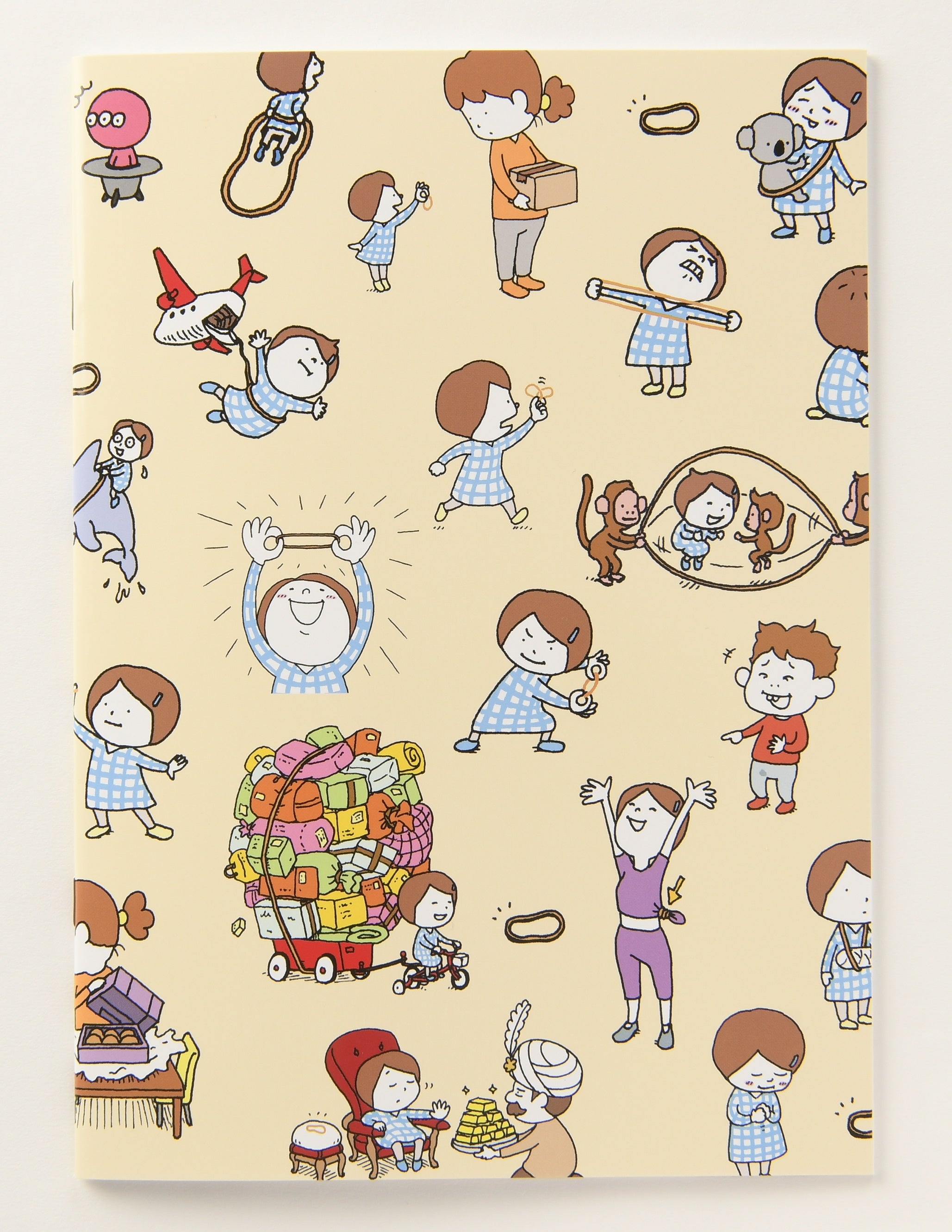「空腹」は認知症のクスリ
「空腹」は認知症のクスリ
通常価格
¥1,320
セールスプライス
¥1,320
通常価格
税込み。
■私が認知症と無縁でいられる理由
私は今年(2022年)の9月で74歳になりますが、この50年間で、健康保険証は2、3回しか使ったことがありません。特に、この30年間は皆無です。
といっても、生まれつき強靱な体力があったわけではなく、幼少時はすぐ高熱を出す、肺炎を患う、肺結核になりかける……といった具合で、よく両親に心配をかけたものでした。
小学6年生ごろから体力がつき、当時の少年がよくやっていた草野球や相撲などでも、他の同級生よりずっと秀逸な力を発揮できるようになりました。
しかし、中学3年生から高校3年間、そして大学1年生までは、1日に何回も便意を催して下痢をくり返す、常に残便感がある、試験や運動会などの行事があると、その症状が悪化する……という、今、考えると「過敏性腸症候群」にかかり、ふつうの西洋医、それに加えて漢方医も受診し、薬を処方してもらっても、まさに「薬石効なし」で、不快な5年間を過ごしたものでした。
大学生のときに、西勝造氏が編み出した民間医学「西医学」を解説してある小冊子を、偶然読む機会を得て、中に「胃腸病には青汁がよい」と書いてあったので、さっそく母に頼んでジューサーでキャベツ汁を作ってもらい、朝、夕、グラス1杯ずつ飲用したところ、1日7、8回もあった下痢が2、3回に減り、腹満や軽い腹痛の症状がなくなったのです。
これを機会に、食物と病気の関係に興味をもち始め、東大の教授や駒込病院長を歴任され、文化勲章も受章された二木謙三博士(1873~1966)や、「骨髄造血説」を覆す「腸管造血説」を打ち立てられた森下敬一博士(1928~2019)のご著書を読み漁った結果、「玄米食が健康によい」との結論に達し、玄米菜食+魚介食を始めたのが、大学2年生のときです。すると、みるみる腸の調子がよくなり、すこぶる健康になって、「何か運動をしたい!」という意欲が湧いてきました。
そこでバーベルを使って「ベンチプレス」と「スクワット」で、挙上重量を競う、パワーリフティングのクラブに入部しました。当初はベンチプレス=30kg、スクワット=50kgの挙上がやっとでしたが、大学5~6年のときはベンチプレス=105kg、スクワット=155kgまで記録を伸ばし、全九州学生パワーリフティング選手権軽量級(体重60kg未満)で優勝するまでになりました。
医学部卒業と同時に、森下敬一博士の血液学を勉強したく、血液内科に入局しましたが、血液内科の患者さんは、白血病、悪性リンパ腫、再生不良性貧血……など。当時は致死率が高く、受けもちの患者さんが、1週間に10人近く亡くなられることもあり、青二才の医師としては、耐えきれない思いの日々の連続でした。
そこで、「病気は予防することこそ大切だ」という自分なりの結論に達し、長崎大学大学院の博士課程を受験し、4年間、「運動や食物と、白血球の免疫力が、どう関わっているか」を毎日、顕微鏡で白血球をのぞきながら、研究しました。
実験にひと区切りつくたびに、米国の玄米自然食運動や、ソ連(当時)のコーカサス地方(現ジョージア)の100歳以上の長寿者たちの食生活の調査に出かけました。また、全ヨーロッパから集まってくる難病、奇病の患者を人参リンゴジュースやミューズリー(ヨーグルトと果物をミキサーにかけて作る)黒パン、野菜などの自然食や鍼灸、マッサージ、ヒドロテラピー(水療法)……などの自然療法で治療を行う、スイス、チューリッヒにあったビルヒャー・ベンナー病院にも研修に出向きました。さらにユーリー・ニコライエフ教授が、モスクワでやっておられた断食療法病院に研修に出かけたのも、この期間でした。
大学院を修了するころには、「病気の予防・治療」にとって食事、運動、入浴・サウナ等の温熱療法が、きわめて大切なことを確信し、上京して内科を開業する傍ら1985(昭和60)年、伊豆高原に、人参リンゴジュース断食、玄米自然食、温泉、生姜湿布、ヨガ……等々で健康を増進する保養所(ヒポクラティック・サナトリウム)を建設しました。最初は、「断食」というと、いかがわしいことをやっているのではないかと、周囲から白眼視され、また、やってこられる保養者の方も少なく、土地購入や建設費用に借りた約5億円の借金返済にとても苦労したものです。
しかし、石原慎太郎元都知事や、知の巨人といわれた上智大学名誉教授の渡部昇一教授が来てくださり、サナトリウムのことをご著書にも紹介してくださるようになったころから、徐々に保養者が増え始め、今では総理大臣経験者3名を含む20余名の大臣経験者、教育界、法曹界、芸能・スポーツ界の著名人から、サラリーマン、主婦、学生まで、まさに多士済々の方が保養に来てくださり、リピーターになってくださる方もたくさんいらっしゃいます。
日本に存在する企業約360万社のうち、30年後まで存続するのは約3%、企業の平均寿命が37.8歳という厳しい現実の中、今年(2022年)10月1日から38周年を迎える当サナトリウムが、こうして存続できているのは健康増進のために頻繁に来てくださる方々、そして、2016年に大隅良典博士に授与されたノーベル生理学・医学賞の「Autophagy」(オートファジー)(自食作用)や、2000年に米国のL・ギャラン教授の「空腹のときに活発化する長寿遺伝子(sirtuin)(サーチュイン)が健康・長寿に貢献する」などの研究成果などのおかげと深く感謝しているしだいです。
私の今の生活は、週5日はサナトリウムで健康講演会や保養者の方々の診察をし、残りの2日は東京のクリニックで診察を行い、その合間をぬって、本の執筆や講演活動を行っています。
26歳から46歳までは、朝食に人参リンゴジュース、グラス2杯、昼食には、とろろそば、夕食=和食中心、というものでしたが、1995~2008年の間は、みのもんた氏司会の「午後は○○おもいッきりテレビ」に出演していたため、少々有名になり、それ以降、昼の休み時間に雑誌や新聞の記者さんが取材に来られるようになり、昼食が食べられなくなりました。以来、昼は生姜紅茶1~2杯で済ませています。
今の食事は、朝に人参リンゴジュース2杯+生姜紅茶1杯。昼は生姜紅茶1~2杯。夕食はビール1~2本、お湯割りの焼酎1~2合、ご飯にみそ汁、野菜の煮物、魚介類の刺身や天ぷら……といった和食中心です。昼間にクッキーやチョコレートをつまむこともありますが……。
週4回は1回につき1時間(約10km)のジョギングを楽しみ、週2回はバーベルを使ってベンチプレス(80~90kg)、スクワット(100kg)で筋肉を鍛えています。
1991年から、毎週日曜日は朝8時30分から11時30分までぶっ続けで、断食の効能をはじめとする健康講演をサナトリウムでやっており、自分でいうのも変ですが、保養者の方々から、その記憶力のよさをびっくりされています。
よって、私は、体の病気(生活習慣病)や認知症など“老化”とは、まったく無縁の健康生活を謳歌しているのです。
本書では、私が日ごろ指導している健康法の中でも、現在深刻な社会問題である認知症の予防と改善に役立つ知識を網羅しました。認知症という病気のことをよく理解していただいて、ご自身やご家族の健康のために役立てていただけたら幸いです。 (「はじめに」より)
著者:石原結實
縦:21×横:14.8 全頁数:128ページ
重量186g厚さ0.8cm
私は今年(2022年)の9月で74歳になりますが、この50年間で、健康保険証は2、3回しか使ったことがありません。特に、この30年間は皆無です。
といっても、生まれつき強靱な体力があったわけではなく、幼少時はすぐ高熱を出す、肺炎を患う、肺結核になりかける……といった具合で、よく両親に心配をかけたものでした。
小学6年生ごろから体力がつき、当時の少年がよくやっていた草野球や相撲などでも、他の同級生よりずっと秀逸な力を発揮できるようになりました。
しかし、中学3年生から高校3年間、そして大学1年生までは、1日に何回も便意を催して下痢をくり返す、常に残便感がある、試験や運動会などの行事があると、その症状が悪化する……という、今、考えると「過敏性腸症候群」にかかり、ふつうの西洋医、それに加えて漢方医も受診し、薬を処方してもらっても、まさに「薬石効なし」で、不快な5年間を過ごしたものでした。
大学生のときに、西勝造氏が編み出した民間医学「西医学」を解説してある小冊子を、偶然読む機会を得て、中に「胃腸病には青汁がよい」と書いてあったので、さっそく母に頼んでジューサーでキャベツ汁を作ってもらい、朝、夕、グラス1杯ずつ飲用したところ、1日7、8回もあった下痢が2、3回に減り、腹満や軽い腹痛の症状がなくなったのです。
これを機会に、食物と病気の関係に興味をもち始め、東大の教授や駒込病院長を歴任され、文化勲章も受章された二木謙三博士(1873~1966)や、「骨髄造血説」を覆す「腸管造血説」を打ち立てられた森下敬一博士(1928~2019)のご著書を読み漁った結果、「玄米食が健康によい」との結論に達し、玄米菜食+魚介食を始めたのが、大学2年生のときです。すると、みるみる腸の調子がよくなり、すこぶる健康になって、「何か運動をしたい!」という意欲が湧いてきました。
そこでバーベルを使って「ベンチプレス」と「スクワット」で、挙上重量を競う、パワーリフティングのクラブに入部しました。当初はベンチプレス=30kg、スクワット=50kgの挙上がやっとでしたが、大学5~6年のときはベンチプレス=105kg、スクワット=155kgまで記録を伸ばし、全九州学生パワーリフティング選手権軽量級(体重60kg未満)で優勝するまでになりました。
医学部卒業と同時に、森下敬一博士の血液学を勉強したく、血液内科に入局しましたが、血液内科の患者さんは、白血病、悪性リンパ腫、再生不良性貧血……など。当時は致死率が高く、受けもちの患者さんが、1週間に10人近く亡くなられることもあり、青二才の医師としては、耐えきれない思いの日々の連続でした。
そこで、「病気は予防することこそ大切だ」という自分なりの結論に達し、長崎大学大学院の博士課程を受験し、4年間、「運動や食物と、白血球の免疫力が、どう関わっているか」を毎日、顕微鏡で白血球をのぞきながら、研究しました。
実験にひと区切りつくたびに、米国の玄米自然食運動や、ソ連(当時)のコーカサス地方(現ジョージア)の100歳以上の長寿者たちの食生活の調査に出かけました。また、全ヨーロッパから集まってくる難病、奇病の患者を人参リンゴジュースやミューズリー(ヨーグルトと果物をミキサーにかけて作る)黒パン、野菜などの自然食や鍼灸、マッサージ、ヒドロテラピー(水療法)……などの自然療法で治療を行う、スイス、チューリッヒにあったビルヒャー・ベンナー病院にも研修に出向きました。さらにユーリー・ニコライエフ教授が、モスクワでやっておられた断食療法病院に研修に出かけたのも、この期間でした。
大学院を修了するころには、「病気の予防・治療」にとって食事、運動、入浴・サウナ等の温熱療法が、きわめて大切なことを確信し、上京して内科を開業する傍ら1985(昭和60)年、伊豆高原に、人参リンゴジュース断食、玄米自然食、温泉、生姜湿布、ヨガ……等々で健康を増進する保養所(ヒポクラティック・サナトリウム)を建設しました。最初は、「断食」というと、いかがわしいことをやっているのではないかと、周囲から白眼視され、また、やってこられる保養者の方も少なく、土地購入や建設費用に借りた約5億円の借金返済にとても苦労したものです。
しかし、石原慎太郎元都知事や、知の巨人といわれた上智大学名誉教授の渡部昇一教授が来てくださり、サナトリウムのことをご著書にも紹介してくださるようになったころから、徐々に保養者が増え始め、今では総理大臣経験者3名を含む20余名の大臣経験者、教育界、法曹界、芸能・スポーツ界の著名人から、サラリーマン、主婦、学生まで、まさに多士済々の方が保養に来てくださり、リピーターになってくださる方もたくさんいらっしゃいます。
日本に存在する企業約360万社のうち、30年後まで存続するのは約3%、企業の平均寿命が37.8歳という厳しい現実の中、今年(2022年)10月1日から38周年を迎える当サナトリウムが、こうして存続できているのは健康増進のために頻繁に来てくださる方々、そして、2016年に大隅良典博士に授与されたノーベル生理学・医学賞の「Autophagy」(オートファジー)(自食作用)や、2000年に米国のL・ギャラン教授の「空腹のときに活発化する長寿遺伝子(sirtuin)(サーチュイン)が健康・長寿に貢献する」などの研究成果などのおかげと深く感謝しているしだいです。
私の今の生活は、週5日はサナトリウムで健康講演会や保養者の方々の診察をし、残りの2日は東京のクリニックで診察を行い、その合間をぬって、本の執筆や講演活動を行っています。
26歳から46歳までは、朝食に人参リンゴジュース、グラス2杯、昼食には、とろろそば、夕食=和食中心、というものでしたが、1995~2008年の間は、みのもんた氏司会の「午後は○○おもいッきりテレビ」に出演していたため、少々有名になり、それ以降、昼の休み時間に雑誌や新聞の記者さんが取材に来られるようになり、昼食が食べられなくなりました。以来、昼は生姜紅茶1~2杯で済ませています。
今の食事は、朝に人参リンゴジュース2杯+生姜紅茶1杯。昼は生姜紅茶1~2杯。夕食はビール1~2本、お湯割りの焼酎1~2合、ご飯にみそ汁、野菜の煮物、魚介類の刺身や天ぷら……といった和食中心です。昼間にクッキーやチョコレートをつまむこともありますが……。
週4回は1回につき1時間(約10km)のジョギングを楽しみ、週2回はバーベルを使ってベンチプレス(80~90kg)、スクワット(100kg)で筋肉を鍛えています。
1991年から、毎週日曜日は朝8時30分から11時30分までぶっ続けで、断食の効能をはじめとする健康講演をサナトリウムでやっており、自分でいうのも変ですが、保養者の方々から、その記憶力のよさをびっくりされています。
よって、私は、体の病気(生活習慣病)や認知症など“老化”とは、まったく無縁の健康生活を謳歌しているのです。
本書では、私が日ごろ指導している健康法の中でも、現在深刻な社会問題である認知症の予防と改善に役立つ知識を網羅しました。認知症という病気のことをよく理解していただいて、ご自身やご家族の健康のために役立てていただけたら幸いです。 (「はじめに」より)
著者:石原結實
縦:21×横:14.8 全頁数:128ページ
重量186g厚さ0.8cm
100 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした