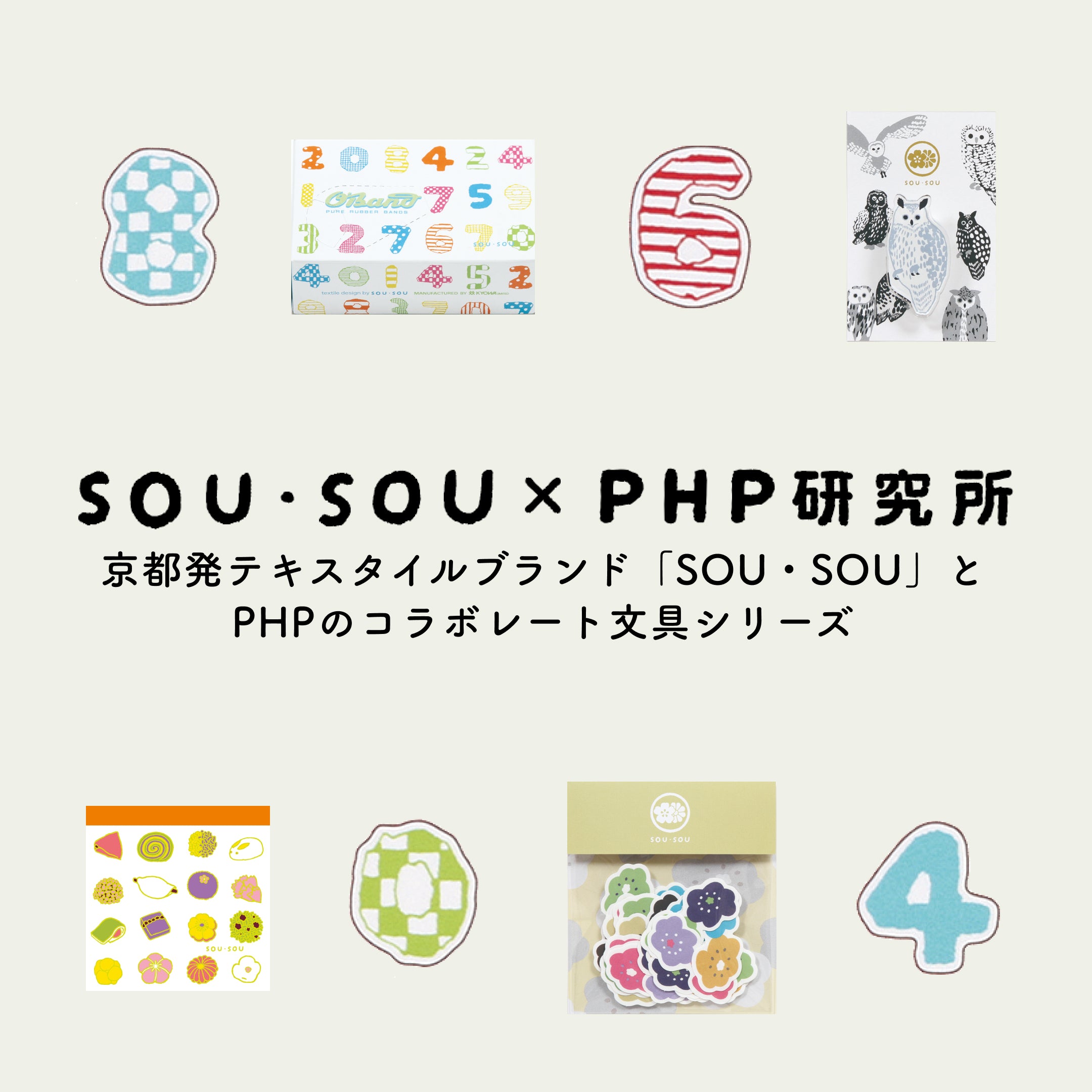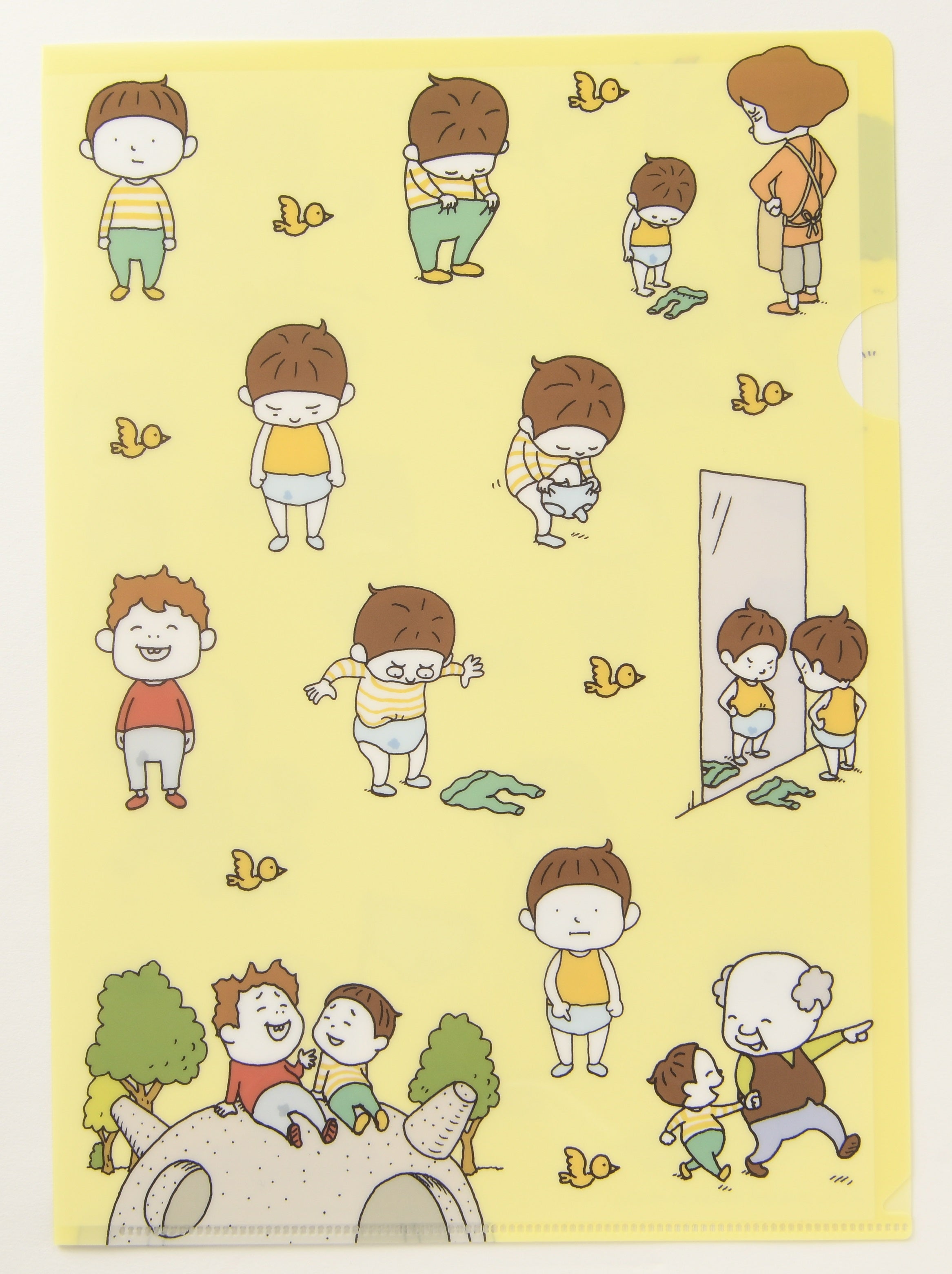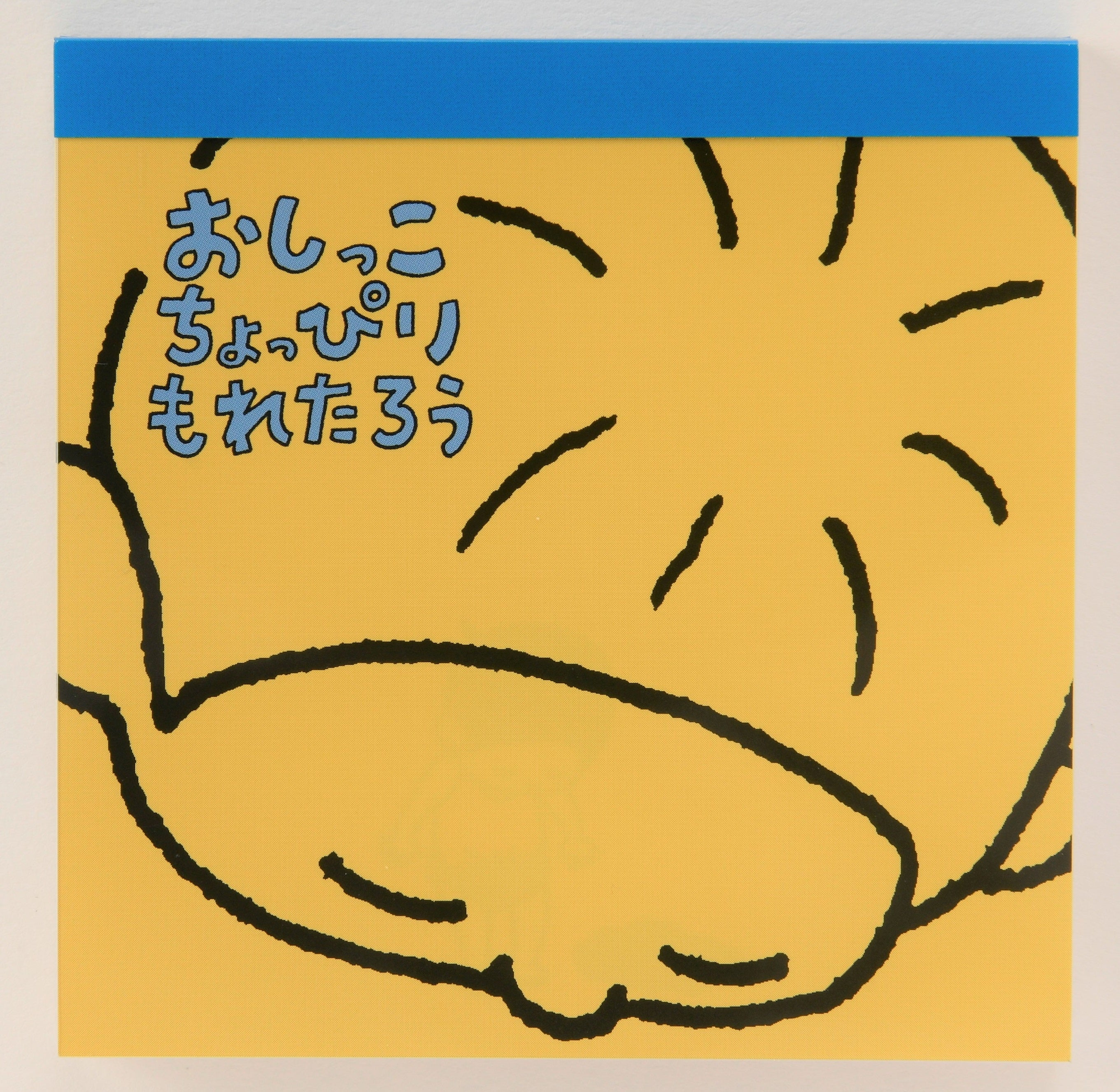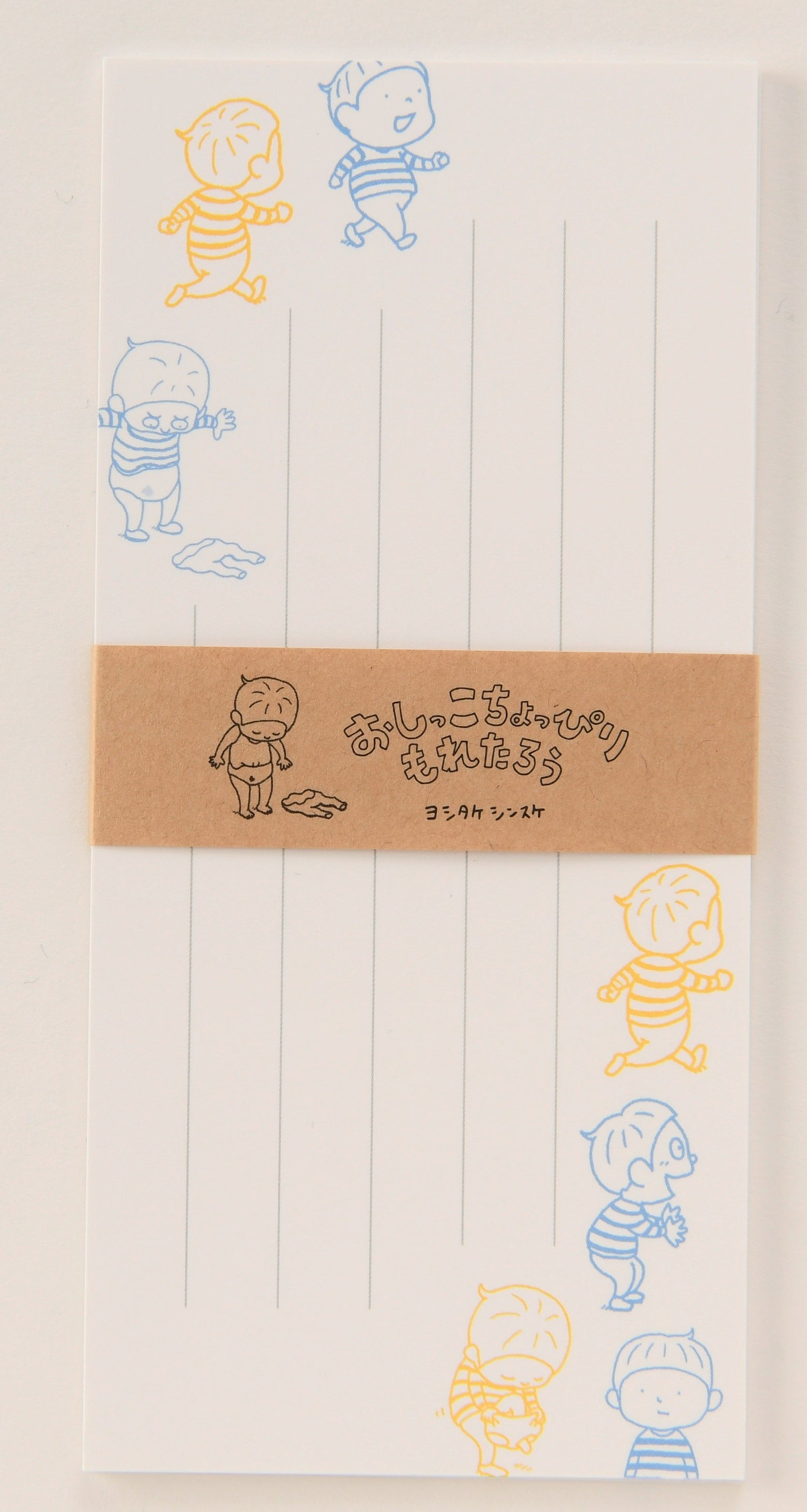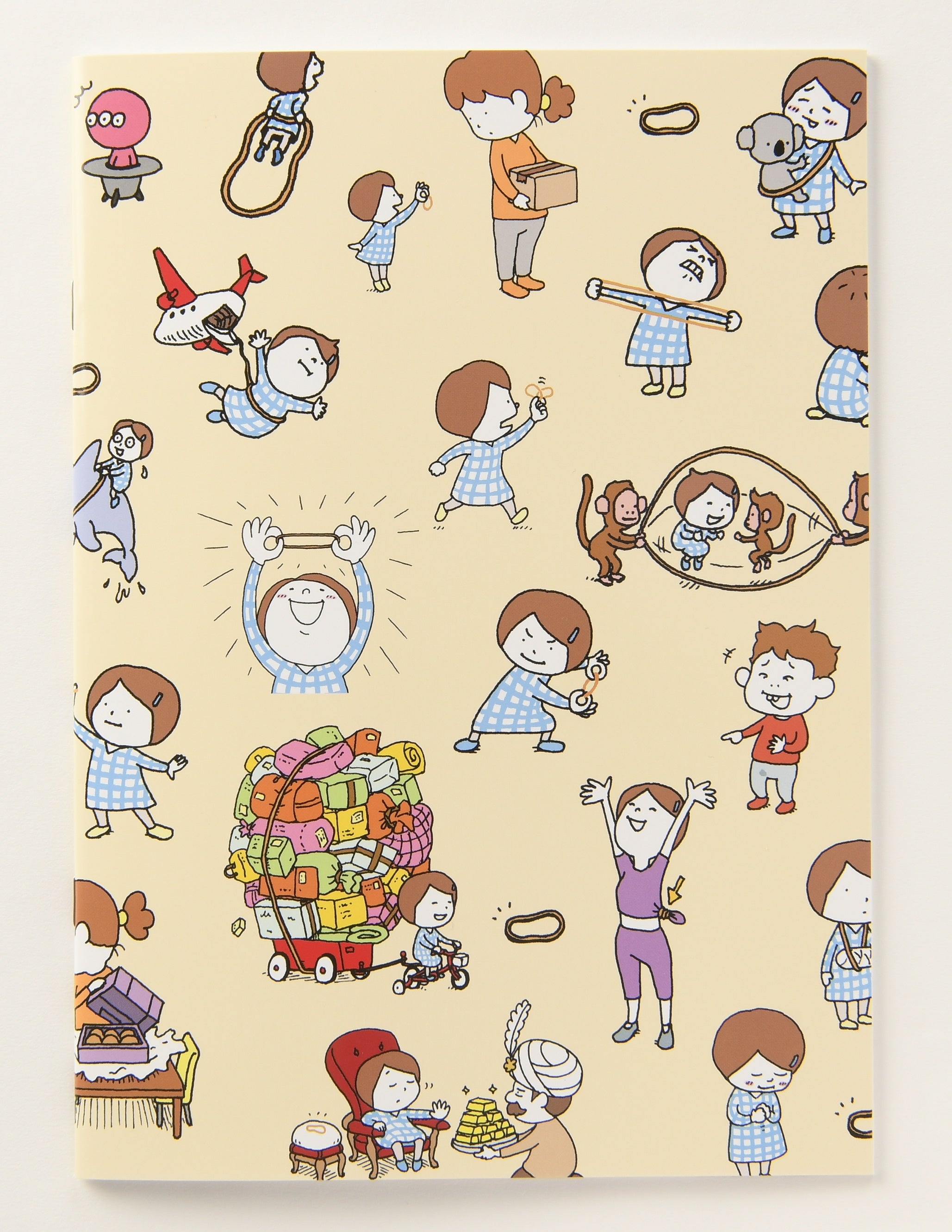育ちのいい人は知っている 13歳からの日本人の「作法」と「しきたり」
育ちのいい人は知っている 13歳からの日本人の「作法」と「しきたり」
礼儀作法やしきたりというと「堅苦しい」「ややこしくて覚えられない」というイメージを持つ人も多いかもしれません。でも、それは違います。
礼儀作法やマナーは、相手を大切に思う心から生まれたもの。人と人との関係をスムーズにして、お互いに快適に暮らしていくためのものです。
マナーデザイナーとして活動を続けてきて37年。私がつねに心に置いている、大好きな言葉があります。日本の教育者・思想家である新渡戸稲造(五千円札の顔にもなった人、というとわかるでしょうか)が、著書『武士道』に記したものです。
「体裁を気にして行うのならば礼儀とはあさましい行為である。
真の礼儀とは相手に対する思いやりの心が外に現れたもの」
つまり、世間体を気にして行ったり、これみよがしに行ったりするのは本当の礼儀やマナーではないということです。
自分を大切にするように、人を大切にする心が現れたものが礼儀や作法。ですからそれは、「思いやり」、もっというと「愛」なのです。
一方、しきたりというのは、人から神様への心配り。私たちをいつも見守ってくださっている神様に感謝し、祈りを捧げる行為です。
このようなしきたりとさまざまなシーンでの礼儀作法は、日々を快適に、心豊かに過ごすために、日本人が大切にしてきた「暮らしの作法」。ですから、もともとは堅苦しいことでもややこしいことでもなく、覚えてしまえば逆に、トラブルを避け、自由に、自分らしく生きていくことができるのです。
グローバル化の時代といわれて久しいですが、日本人としての作法やしきたりをきちんと理解し、身につけることができれば、国際人として世界に通用する人になります。
国際人として活躍できるのは、外国のことを知っている人ではなく、何よりも自分の国のことを知っていて、それを外国の人たちに語れる人です。作法やしきたりを通じて日本の文化、精神性を知ることが、これから求められる国際人となる近道だといえるかもしれません。
古来、日本では左が上位とされてきました。「左上右下」といって、上座から見て左側に位の高い人や大切なものを置く習わしがあるのです。
食事の際、ご飯を左に置くのは、お米によって生かされてきた日本人にとって、お米は何よりも大切なものだから。雛人形の並びも、関西ではお雛様から見て男雛は左(向かって右)です。
ところが、「プロトコル」と呼ばれる国際儀礼では、逆に右が上位とされます。たとえば、オリンピックの表彰台上での並びは、最上位の金が真ん中で、次の銀が真ん中の人から見て右側(向かって左)、最下位の銅が真ん中の人から見て左(向かって右)なのは、そのためです。
日本の作法とプロトコルのどちらがよい、悪いということではなく、文化の違いです。郷に入っては郷に従えで、海外では海外の文化に敬意を表してプロトコルに従いますが、日本では日本の伝統に従って、堂々と振る舞う。外国の方にも、その理由をきちんと説明することができる。それが、真の国際人のあるべき姿なのではないでしょうか。
本書のタイトルを『育ちのいい人は知っている 13歳からの日本人の「作法」と「しきたり」』としたのには理由があります。自立心が芽生え、大人の世界に大きく一歩踏み出そうとする。その時期がちょうど13歳くらいではないかと思うのです。
とくに礼儀作法は、今日学んだからといってすぐ身につくものではありません。自然と振る舞えるようになるには、日々、実践することが大切。13歳から(いえ、もっと早い時期からでも)作法やしきたりを学んでいれば、いつどこへ出ていっても堂々と、スマートに振る舞える大人になれます。そして、心に余裕ができる分、人に対する思いやりの気持ちをより発揮できるはずです。
もちろん、大人のみなさんも、美しい日本の作法としきたりについて今一度、おさらいしてみてください。親子で「へえ、そうなんだ」「素敵な心遣いね」と楽しく話しながら、礼儀作法やしきたりを身につけていただけたら、私としてはこんなにうれしいことはありません。 (「はじめに」より)
著者:監修:岩下宣子
縦:21×横:14.8 全頁数:160ページ
重量266g厚さ1.3cm
99 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした