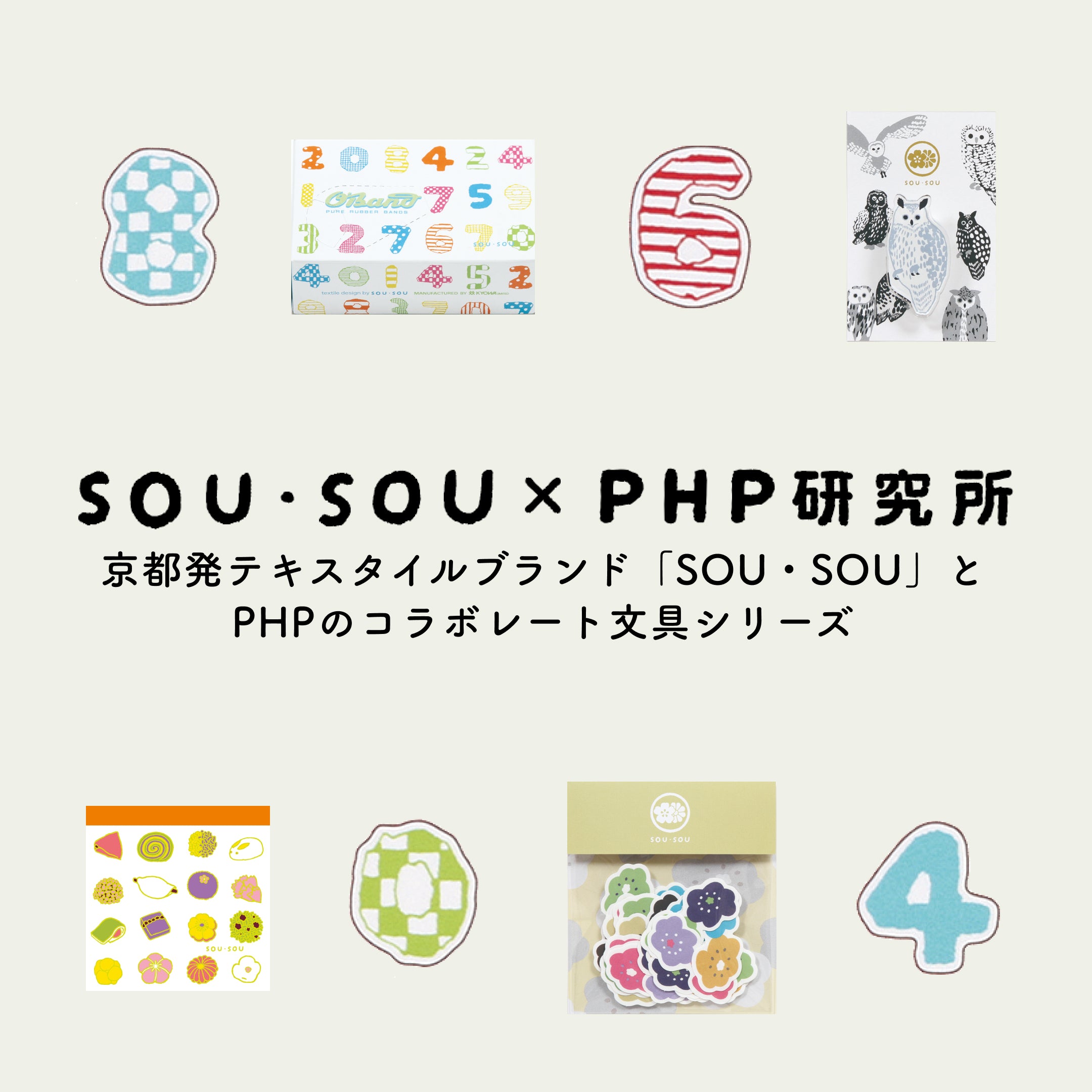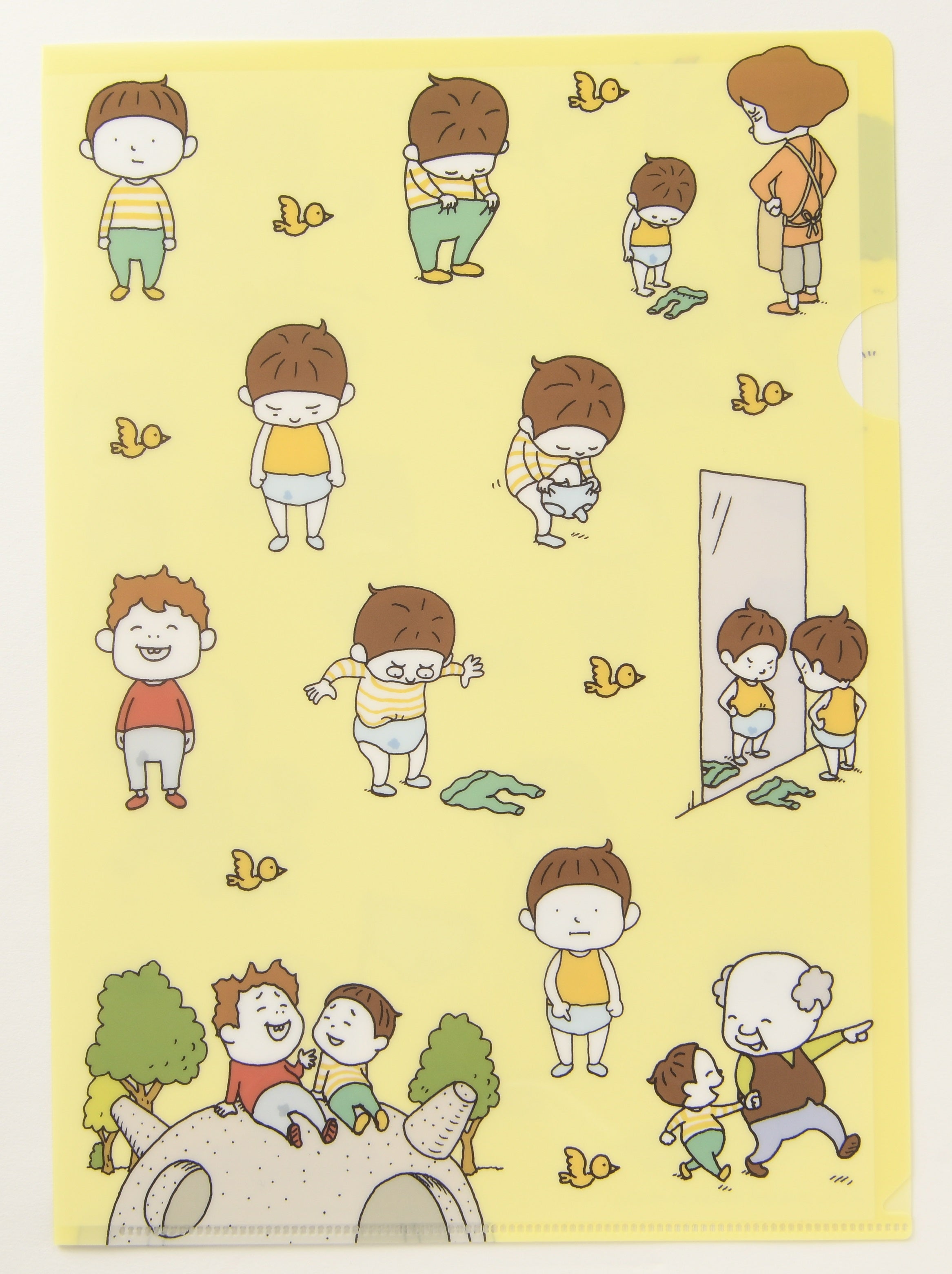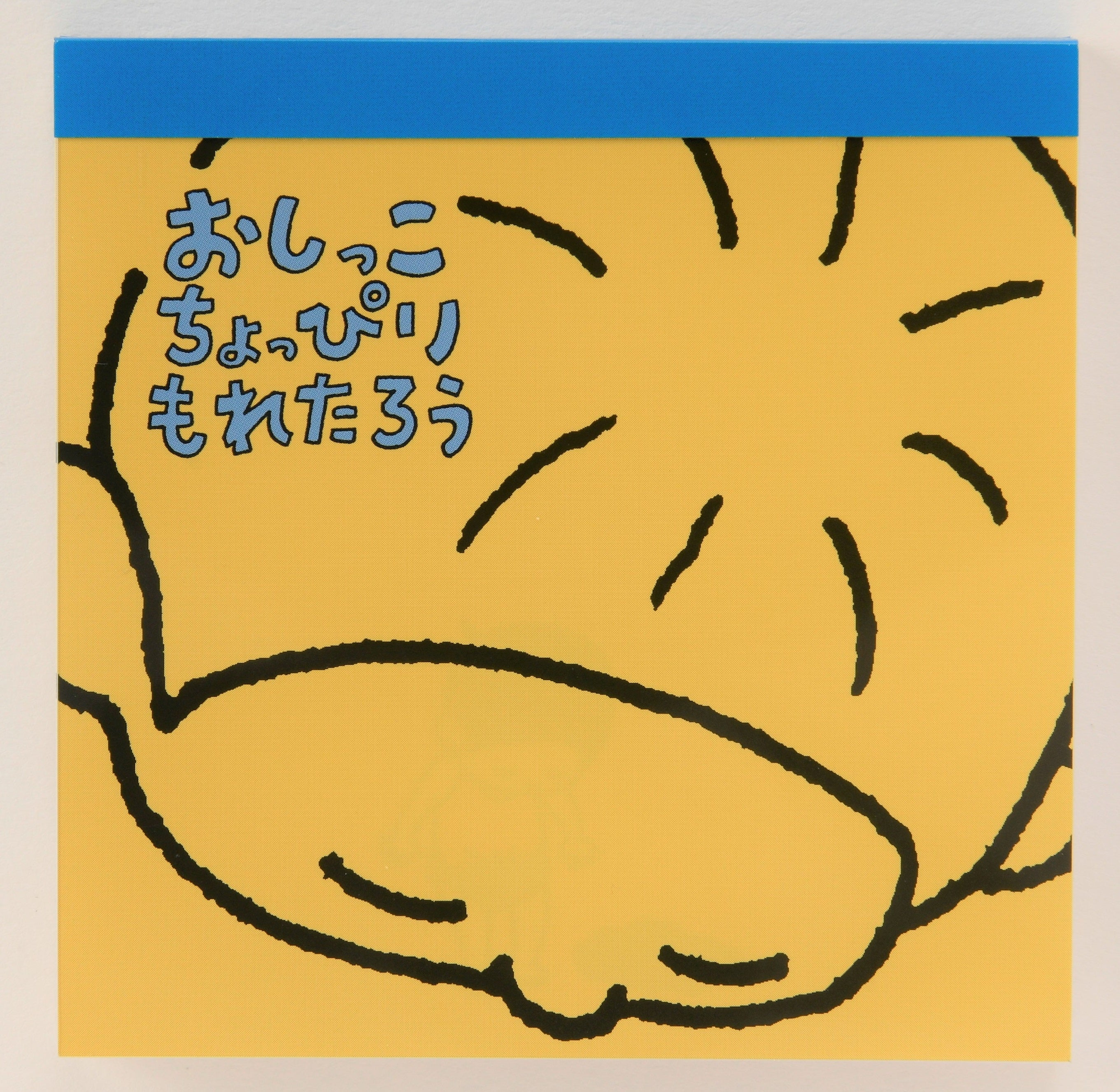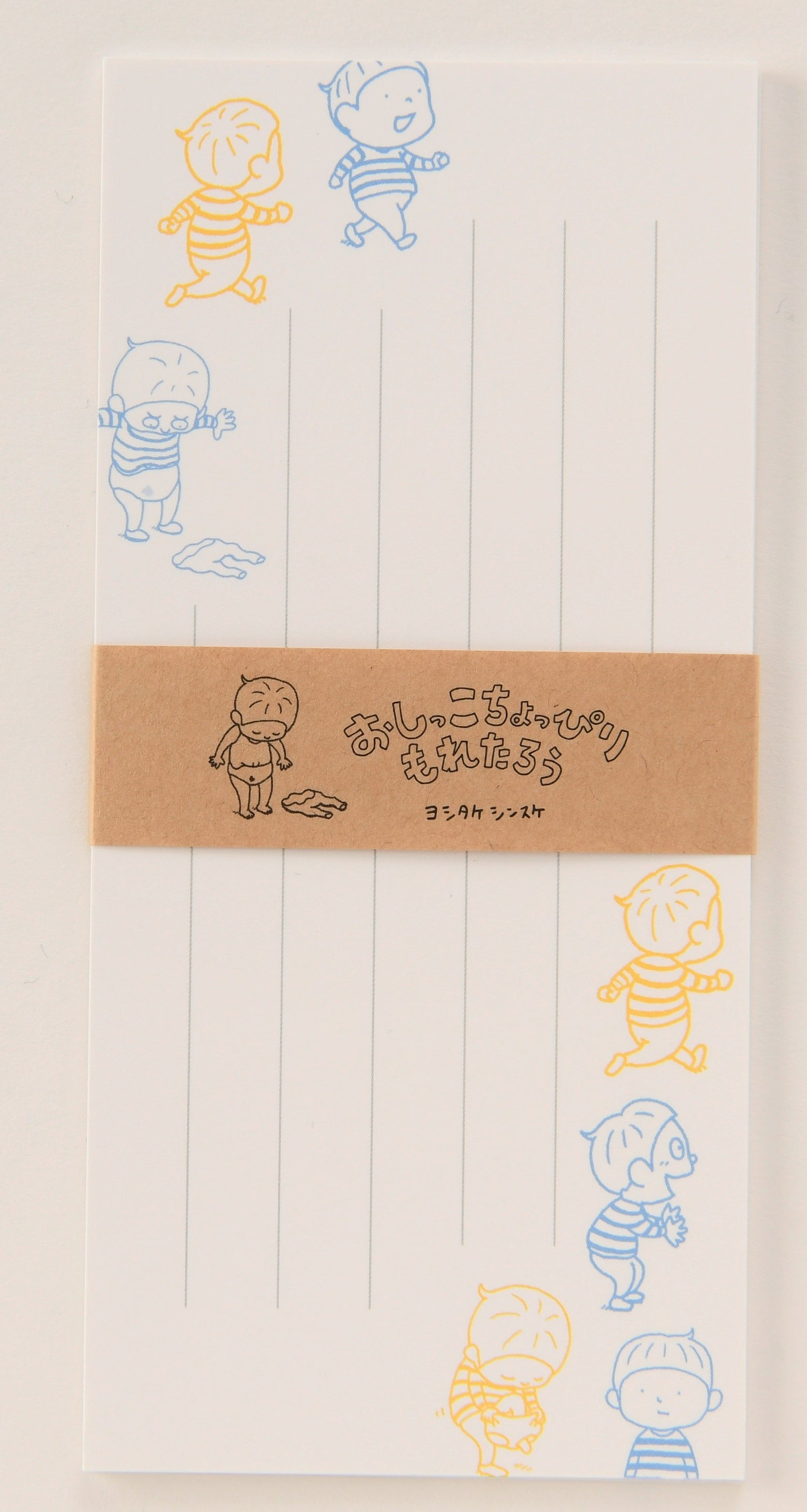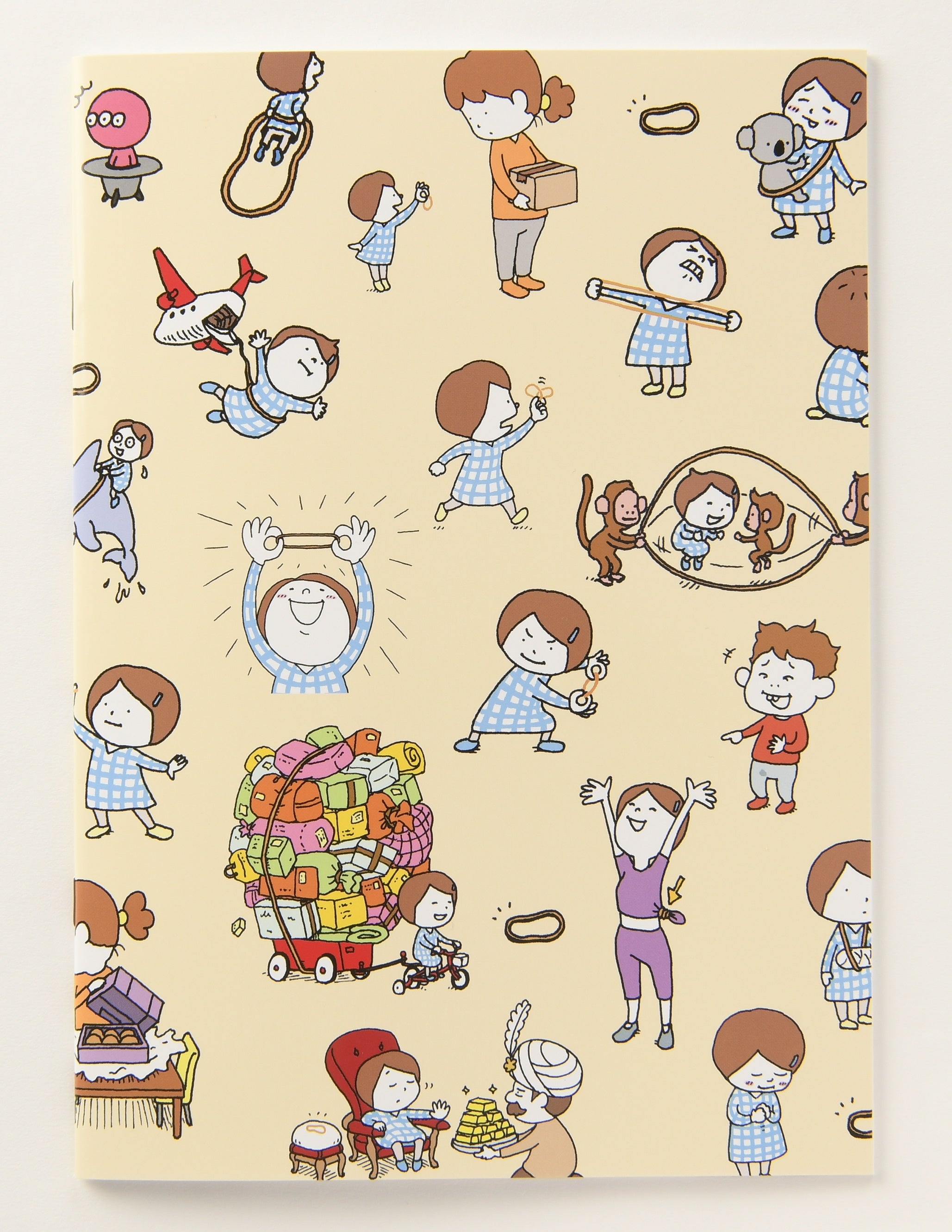心が荒れている子にちゃんと伝わる12歳までのお母さんの言葉がけ
心が荒れている子にちゃんと伝わる12歳までのお母さんの言葉がけ
通常価格
¥1,320
セールスプライス
¥1,320
通常価格
税込み。
人は、「自分とはなんだろう?」「自分はどうして生まれてきたのだろう?」という問いをいつからか持ちはじめ、やがて、それなりに「自分らしさ」を見つけて、主体的に自律的に生きようとします。これを「個性化」といいます。
他方で、他人のことが気になり、親しくなりたいと思うものの、うまくいかないこともあり、悩みつつ他人と協力する術を知り、社会に適応する生活を送るようになります。これは「社会化」と呼ばれます。
この「個性化」と「社会化」は、同時に育ちながらも、発達の折々で矛盾しはじめます。自分らしさを出しすぎると他人に責められることもあれば、他人のことを考えて自分を抑え込みすぎてもストレスが大きくなり、途方に暮れることとなります。自分が間違っているのか、自分は存在していいのだろうかと悩みはじめます。
同時に、他の人と協力して生きていくために、自分に折り合いをつけたり、他人と衝突したりと、試行錯誤を繰り返します。特に幼児期や児童期は、こうした自分の心を客観的に見る力が未熟なので、不快さの原因を、自分で意識できない場合もあるでしょう。
子どもの中のこうしたトラブルや葛藤が、親には「心の荒れ」として映るものです。何かにふてくされたり、気持ちが高ぶったり、逆に、落ち込んだりと、発達の各時期で子どもが見せる「荒れ」に、親は手に負えないような気持ちになることも少なくないと思います。しかし、心の荒れは、人が発達を通して「変化(チェンジ)」していく上で、常に経験するものなのです。
幼児期には「~したい」という強い欲求に突き上げられていますが、そのうち「~すべき」という規範がわかるようになります。「~すべき」という考え方が、「~したい」という欲求を抑えるように「我慢する心」が獲得できるようになります。しかし、それまでに、何度も失敗を経験して、ようやくコントロールできるようになるのです。
「昨日」も「明日」も考えられなかった子どもが、次第に時間の概念を理解しはじめ、過去や未来のことが展望できるようになると、そのぶん悩みが増えてきます。対人関係において、好きな子とばかり遊んでいたのが、友だちが増えると、いろいろな人の気持ちを考えることが必要になり、そのぶんトラブルが増えてきます。
つまり、健康な発達を遂げているからこそ、葛藤が減るどころか、新たに増えてくるわけです。
そもそも、人が「生きる」ということは、さまざまな葛藤を抱えながら生活していくということで、悩みや葛藤が「ゼロ」というのはあり得ないことではないでしょうか。「健康だからこそ、葛藤を抱えることができる」と言えます。葛藤をすべて回避し、葛藤を抱えない状況こそが、心配すべきことなのです。
ですから、子どもの心の「荒れ」を、むやみにダメなものと決めつけて、「早く直しなさい!」と押さえ込んだり、叱ったりしないでください。見ないように見過ごすものでもありません。
子どもの心がカサカサと荒れてきたと感じたら、それは子どもが一歩成長し、階段をひとつ登ろうとしていることの表れと捉えましょう。
登り方を教えたり、足場をかけたり、親自身がモデルとなって導くのもよいでしょう。子どもの気持ちに寄り添って手をかけ、心をかければ、ほっこり、フーッと息がつける経験が、親子にとってかけがえがない人生の一コマとなるはずです。
「今、ここ」で穏やかになれるときがあると、子どもの心は充電され、困難の中でも勇気を持って新たな一歩を踏み出すことができます。
さあ、子どもの独自性を認めつつ、少しずつ社会に適応できる知識やスキルを、特にこの本では「感情力」を上手に身につけていくための「足場かけ」を、今日から実践していきましょう。 (「はじめに」より)
著者:渡辺弥生
縦:26×横:18 全頁数:96ページ
重量226g厚さ1cm
他方で、他人のことが気になり、親しくなりたいと思うものの、うまくいかないこともあり、悩みつつ他人と協力する術を知り、社会に適応する生活を送るようになります。これは「社会化」と呼ばれます。
この「個性化」と「社会化」は、同時に育ちながらも、発達の折々で矛盾しはじめます。自分らしさを出しすぎると他人に責められることもあれば、他人のことを考えて自分を抑え込みすぎてもストレスが大きくなり、途方に暮れることとなります。自分が間違っているのか、自分は存在していいのだろうかと悩みはじめます。
同時に、他の人と協力して生きていくために、自分に折り合いをつけたり、他人と衝突したりと、試行錯誤を繰り返します。特に幼児期や児童期は、こうした自分の心を客観的に見る力が未熟なので、不快さの原因を、自分で意識できない場合もあるでしょう。
子どもの中のこうしたトラブルや葛藤が、親には「心の荒れ」として映るものです。何かにふてくされたり、気持ちが高ぶったり、逆に、落ち込んだりと、発達の各時期で子どもが見せる「荒れ」に、親は手に負えないような気持ちになることも少なくないと思います。しかし、心の荒れは、人が発達を通して「変化(チェンジ)」していく上で、常に経験するものなのです。
幼児期には「~したい」という強い欲求に突き上げられていますが、そのうち「~すべき」という規範がわかるようになります。「~すべき」という考え方が、「~したい」という欲求を抑えるように「我慢する心」が獲得できるようになります。しかし、それまでに、何度も失敗を経験して、ようやくコントロールできるようになるのです。
「昨日」も「明日」も考えられなかった子どもが、次第に時間の概念を理解しはじめ、過去や未来のことが展望できるようになると、そのぶん悩みが増えてきます。対人関係において、好きな子とばかり遊んでいたのが、友だちが増えると、いろいろな人の気持ちを考えることが必要になり、そのぶんトラブルが増えてきます。
つまり、健康な発達を遂げているからこそ、葛藤が減るどころか、新たに増えてくるわけです。
そもそも、人が「生きる」ということは、さまざまな葛藤を抱えながら生活していくということで、悩みや葛藤が「ゼロ」というのはあり得ないことではないでしょうか。「健康だからこそ、葛藤を抱えることができる」と言えます。葛藤をすべて回避し、葛藤を抱えない状況こそが、心配すべきことなのです。
ですから、子どもの心の「荒れ」を、むやみにダメなものと決めつけて、「早く直しなさい!」と押さえ込んだり、叱ったりしないでください。見ないように見過ごすものでもありません。
子どもの心がカサカサと荒れてきたと感じたら、それは子どもが一歩成長し、階段をひとつ登ろうとしていることの表れと捉えましょう。
登り方を教えたり、足場をかけたり、親自身がモデルとなって導くのもよいでしょう。子どもの気持ちに寄り添って手をかけ、心をかければ、ほっこり、フーッと息がつける経験が、親子にとってかけがえがない人生の一コマとなるはずです。
「今、ここ」で穏やかになれるときがあると、子どもの心は充電され、困難の中でも勇気を持って新たな一歩を踏み出すことができます。
さあ、子どもの独自性を認めつつ、少しずつ社会に適応できる知識やスキルを、特にこの本では「感情力」を上手に身につけていくための「足場かけ」を、今日から実践していきましょう。 (「はじめに」より)
著者:渡辺弥生
縦:26×横:18 全頁数:96ページ
重量226g厚さ1cm
100 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした