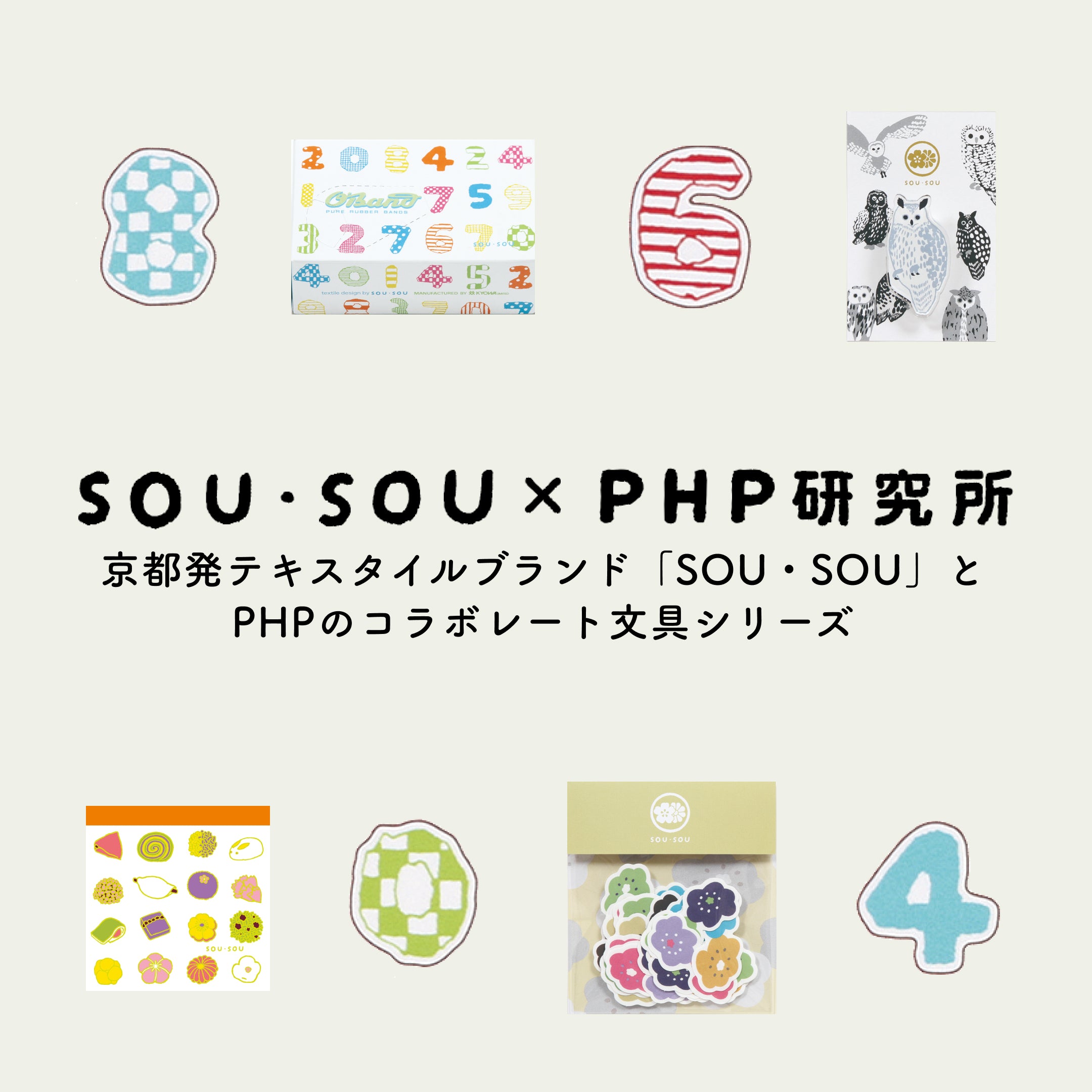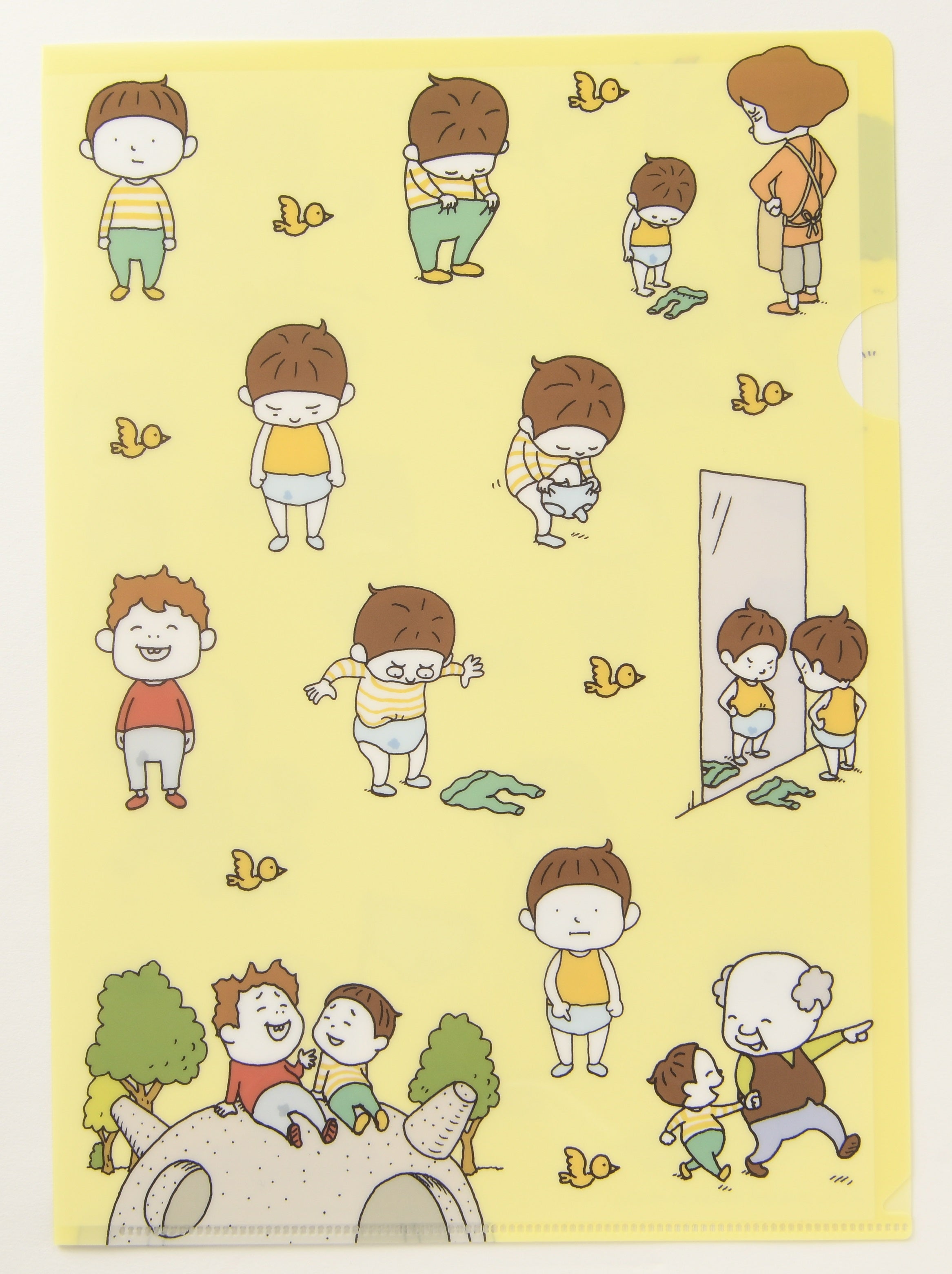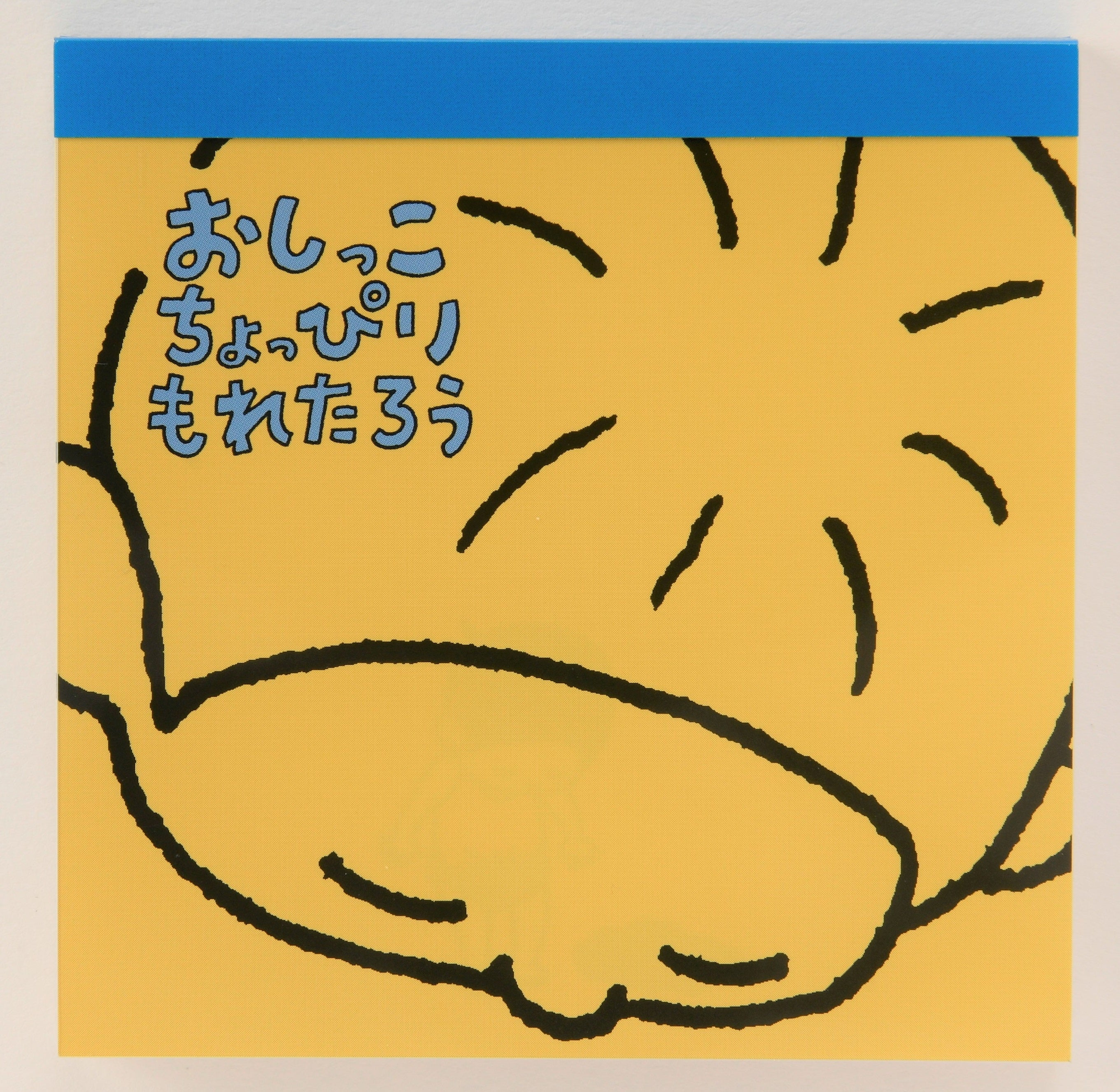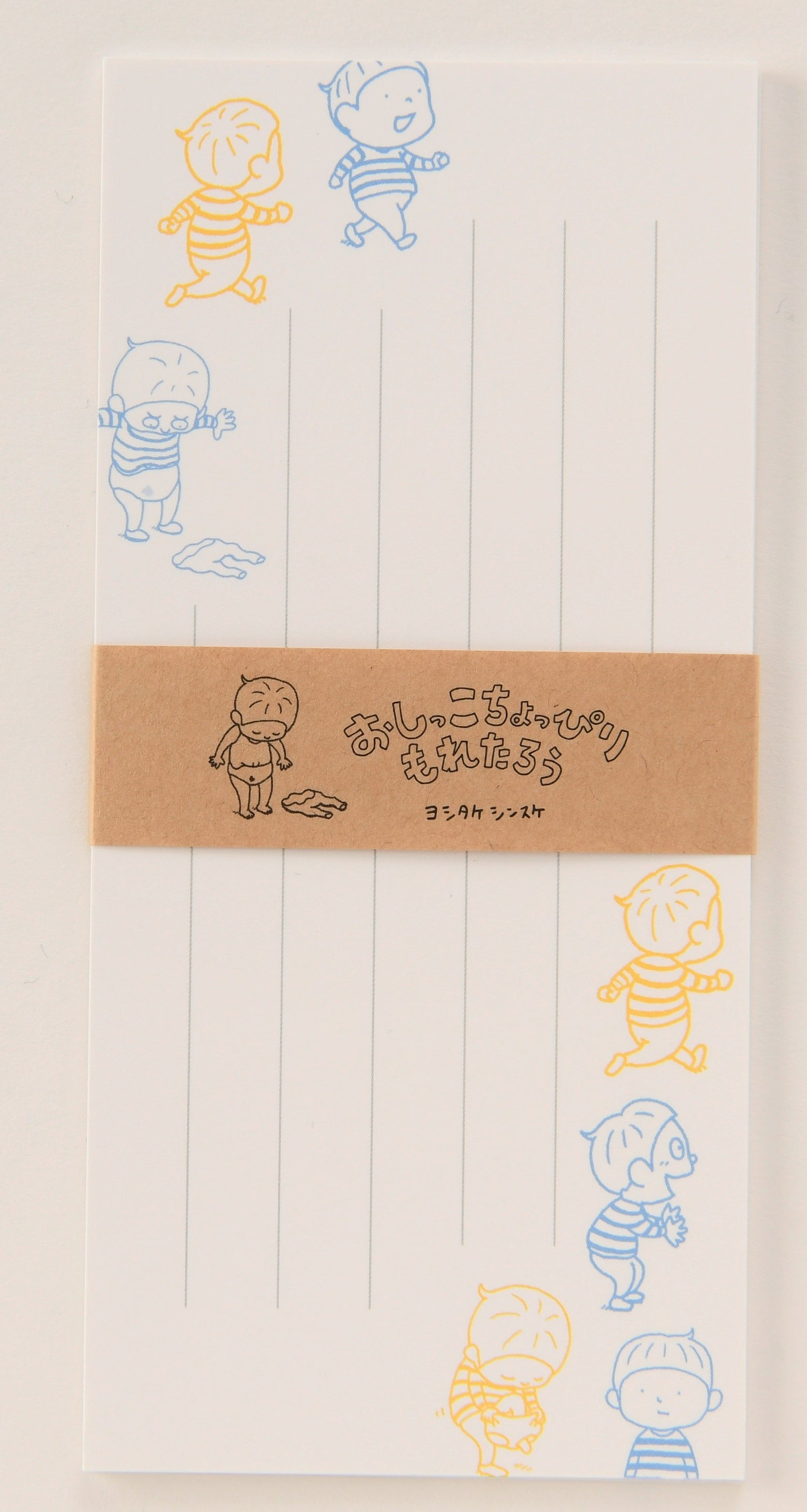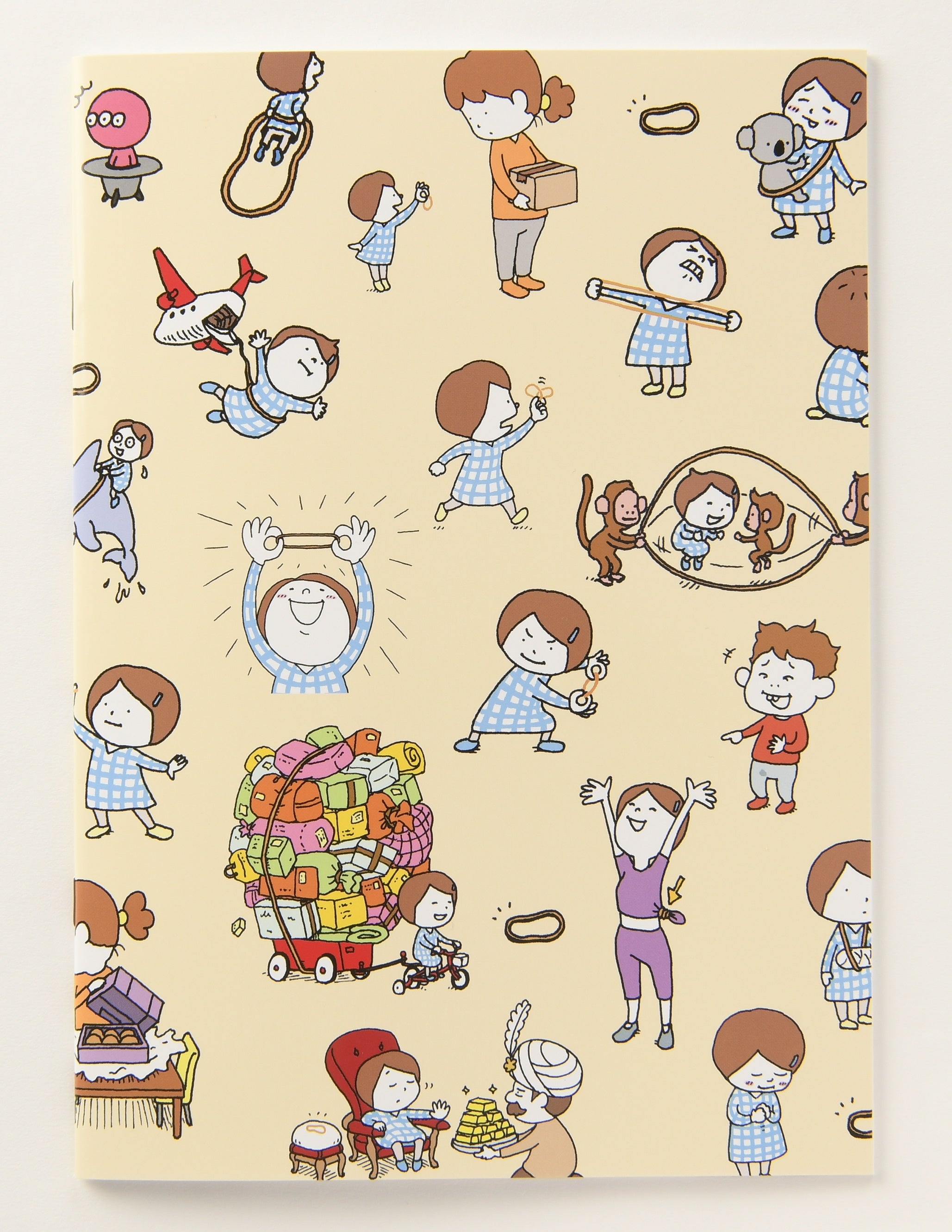子どもの脳をダメにするほめ方・脳を育てる叱り方
子どもの脳をダメにするほめ方・脳を育てる叱り方
通常価格
¥1,320
セールスプライス
¥1,320
通常価格
税込み。
毎日、お子さんと向き合って育児に孤軍奮闘しているお母さん。
「衣食住」を快適に整え、元気いっぱいのお子さんの遊び相手を務め、さらには将来に向け、しつけにも日夜尽力する。ときには、自分の用事なんてあと回しに……。そんな奮闘ぶりには頭が下がります。
ときに、あわただしく過ぎていく日常の中で、“自己流でなんとなく済ませてしまっていること”はありませんか?
もちろん、離乳食の作り方や掃除の仕方など、たいていのことは“自己流”でもなんとかなるものです。適当に取り組んだからといって、何かが決定的に損なわれたり、将来に悪影響が及んだりすることはないでしょう。
けれども、できれば“自己流”を避けてほしいことがあります。
それが、お子さんの「ほめ方」と「叱り方」です。
近年、脳科学の世界では驚異的な速さで研究が進みました。その結果、今まで「わからない」とされてきたことが、どんどん明らかにされています。
それに伴い「このような言葉をかけたほうが、赤ちゃんの脳はよく育つ」というような事実も、多く発見されるようになりました。
つまり、幼い頃の自分がほめられたようにほめたり、叱られたように叱ったりするのではなく、最新の研究結果を取り入れた育児法にも、注目をしたほうがよいこともあるのです。
たとえば、あなたは次のような声かけをお子さんにしていませんか?
【ほめるとき】
・父親を敬う気持ちをもってほしくて、「さすがパパの子だね」という「わが家の決まり文句」で機械的にほめるようにしている。
・離れて暮らす祖父母らとの絆も大切にしたいので、「おばあちゃんもきっと喜ぶよ」というほめ言葉をクセにしている。
【叱るとき】
・公園でお友だちをたたいてしまったら、他のお母さんの手前、あえて“大勢の前で”わが子を大声で叱っている。
・テストで悪い成績をとってきたら、「そんな成績じゃ、将来いい会社に入れないわよ」と励ましのつもりで言っている。
これらのほめ方、叱り方は、一見素晴らしいものに思えるかもしれません。けれども脳科学的な観点からすると、すべて“アウト”なのです。
いったい、どのような点がダメなのか。詳しい解説は、あとの本文に譲るとしましょう。
「脳を育てる」ということは、体も心も健やかに育ってほしいという親の願いです。
脳とはどのように成長するのか、どのような性質を備えているのか、どうすれば喜んで力を発揮してくれるのかなどを知ることが重要です。
本書はそれらのニーズを踏まえ、「脳の仕組み」にまで踏み込み、わかりやすく解説することを目的としています。
「脳」とは、得体の知れないブラックボックス、というわけではありません。非常に扱いやすい「やる気を起こすためのスイッチ」ととらえてみてください。
脳に向かって、「よいほめ方」「よい叱り方」をしたときは、「そうだったのか!」とお子さんが納得し、よい脳内物質が分泌されて、やる気が出たり、次への意欲が湧いてきたりします。
反対に「悪いほめ方」「悪い叱り方」をしたときは、好ましくない脳内物質が分泌されて、お子さんはただ「不快」になったり、次への意欲を失ってしまったり、悲しみや不安などのネガティブな感情に流されてしまいます。つまり、お母さんの声かけ1つに、お子さんの脳の働きは簡単に左右されてしまうものなのです。お母さんの今の言動が、お子さんの将来の姿を決定するといっても過言ではないでしょう。
とはいえ、脳科学の観点から理想の子育てを求めていくことは、さして難しいことではありません。本書では事例もふんだんに提示して、わかりやすくお話ししていきます。肩の力を抜いて、リラックスして読み進めてください。 (「はじめに」より)
著者:片野晶子
縦:25.8×横:18.2 全頁数:96ページ
重量290g厚さ1.1cm
「衣食住」を快適に整え、元気いっぱいのお子さんの遊び相手を務め、さらには将来に向け、しつけにも日夜尽力する。ときには、自分の用事なんてあと回しに……。そんな奮闘ぶりには頭が下がります。
ときに、あわただしく過ぎていく日常の中で、“自己流でなんとなく済ませてしまっていること”はありませんか?
もちろん、離乳食の作り方や掃除の仕方など、たいていのことは“自己流”でもなんとかなるものです。適当に取り組んだからといって、何かが決定的に損なわれたり、将来に悪影響が及んだりすることはないでしょう。
けれども、できれば“自己流”を避けてほしいことがあります。
それが、お子さんの「ほめ方」と「叱り方」です。
近年、脳科学の世界では驚異的な速さで研究が進みました。その結果、今まで「わからない」とされてきたことが、どんどん明らかにされています。
それに伴い「このような言葉をかけたほうが、赤ちゃんの脳はよく育つ」というような事実も、多く発見されるようになりました。
つまり、幼い頃の自分がほめられたようにほめたり、叱られたように叱ったりするのではなく、最新の研究結果を取り入れた育児法にも、注目をしたほうがよいこともあるのです。
たとえば、あなたは次のような声かけをお子さんにしていませんか?
【ほめるとき】
・父親を敬う気持ちをもってほしくて、「さすがパパの子だね」という「わが家の決まり文句」で機械的にほめるようにしている。
・離れて暮らす祖父母らとの絆も大切にしたいので、「おばあちゃんもきっと喜ぶよ」というほめ言葉をクセにしている。
【叱るとき】
・公園でお友だちをたたいてしまったら、他のお母さんの手前、あえて“大勢の前で”わが子を大声で叱っている。
・テストで悪い成績をとってきたら、「そんな成績じゃ、将来いい会社に入れないわよ」と励ましのつもりで言っている。
これらのほめ方、叱り方は、一見素晴らしいものに思えるかもしれません。けれども脳科学的な観点からすると、すべて“アウト”なのです。
いったい、どのような点がダメなのか。詳しい解説は、あとの本文に譲るとしましょう。
「脳を育てる」ということは、体も心も健やかに育ってほしいという親の願いです。
脳とはどのように成長するのか、どのような性質を備えているのか、どうすれば喜んで力を発揮してくれるのかなどを知ることが重要です。
本書はそれらのニーズを踏まえ、「脳の仕組み」にまで踏み込み、わかりやすく解説することを目的としています。
「脳」とは、得体の知れないブラックボックス、というわけではありません。非常に扱いやすい「やる気を起こすためのスイッチ」ととらえてみてください。
脳に向かって、「よいほめ方」「よい叱り方」をしたときは、「そうだったのか!」とお子さんが納得し、よい脳内物質が分泌されて、やる気が出たり、次への意欲が湧いてきたりします。
反対に「悪いほめ方」「悪い叱り方」をしたときは、好ましくない脳内物質が分泌されて、お子さんはただ「不快」になったり、次への意欲を失ってしまったり、悲しみや不安などのネガティブな感情に流されてしまいます。つまり、お母さんの声かけ1つに、お子さんの脳の働きは簡単に左右されてしまうものなのです。お母さんの今の言動が、お子さんの将来の姿を決定するといっても過言ではないでしょう。
とはいえ、脳科学の観点から理想の子育てを求めていくことは、さして難しいことではありません。本書では事例もふんだんに提示して、わかりやすくお話ししていきます。肩の力を抜いて、リラックスして読み進めてください。 (「はじめに」より)
著者:片野晶子
縦:25.8×横:18.2 全頁数:96ページ
重量290g厚さ1.1cm
100 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした