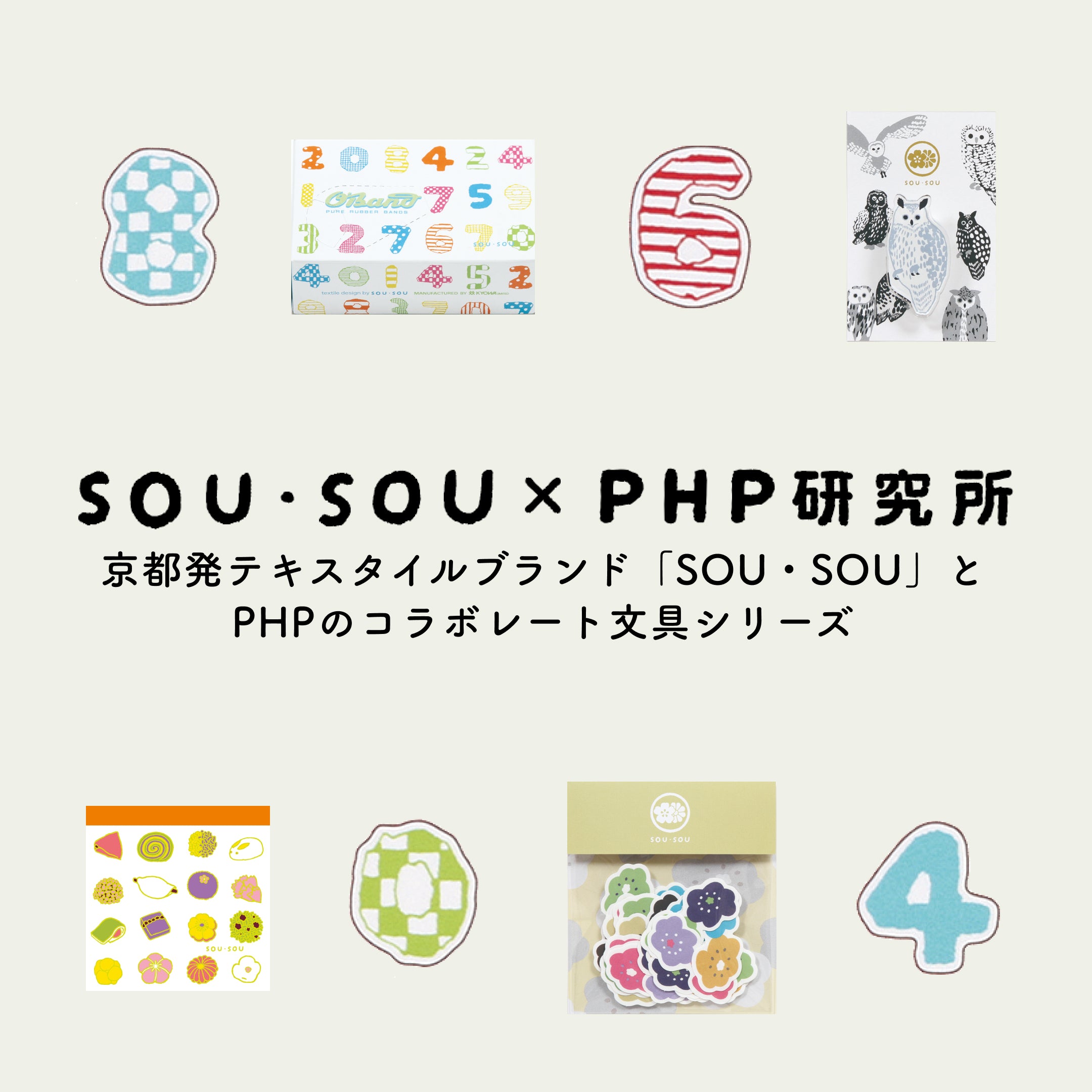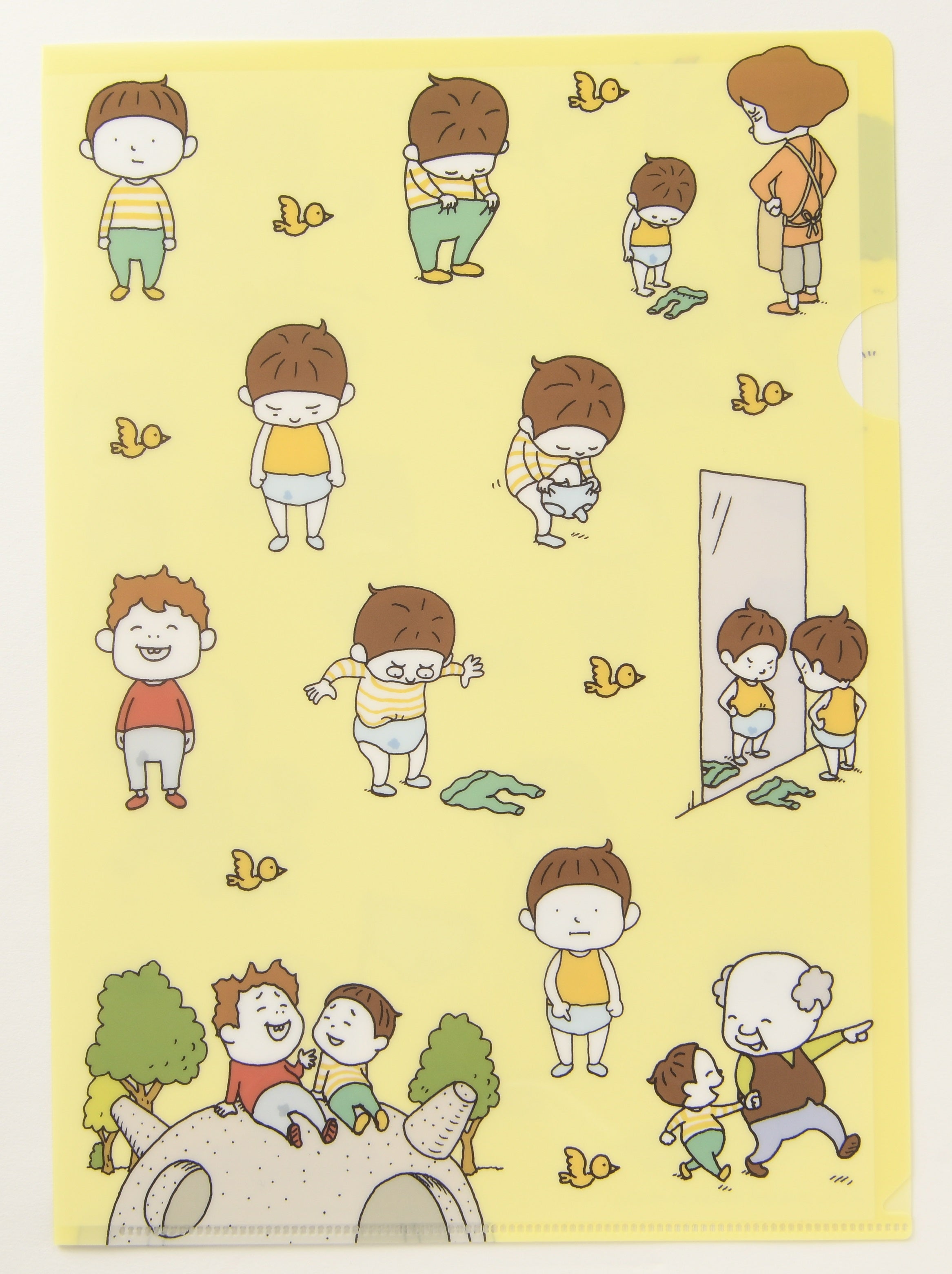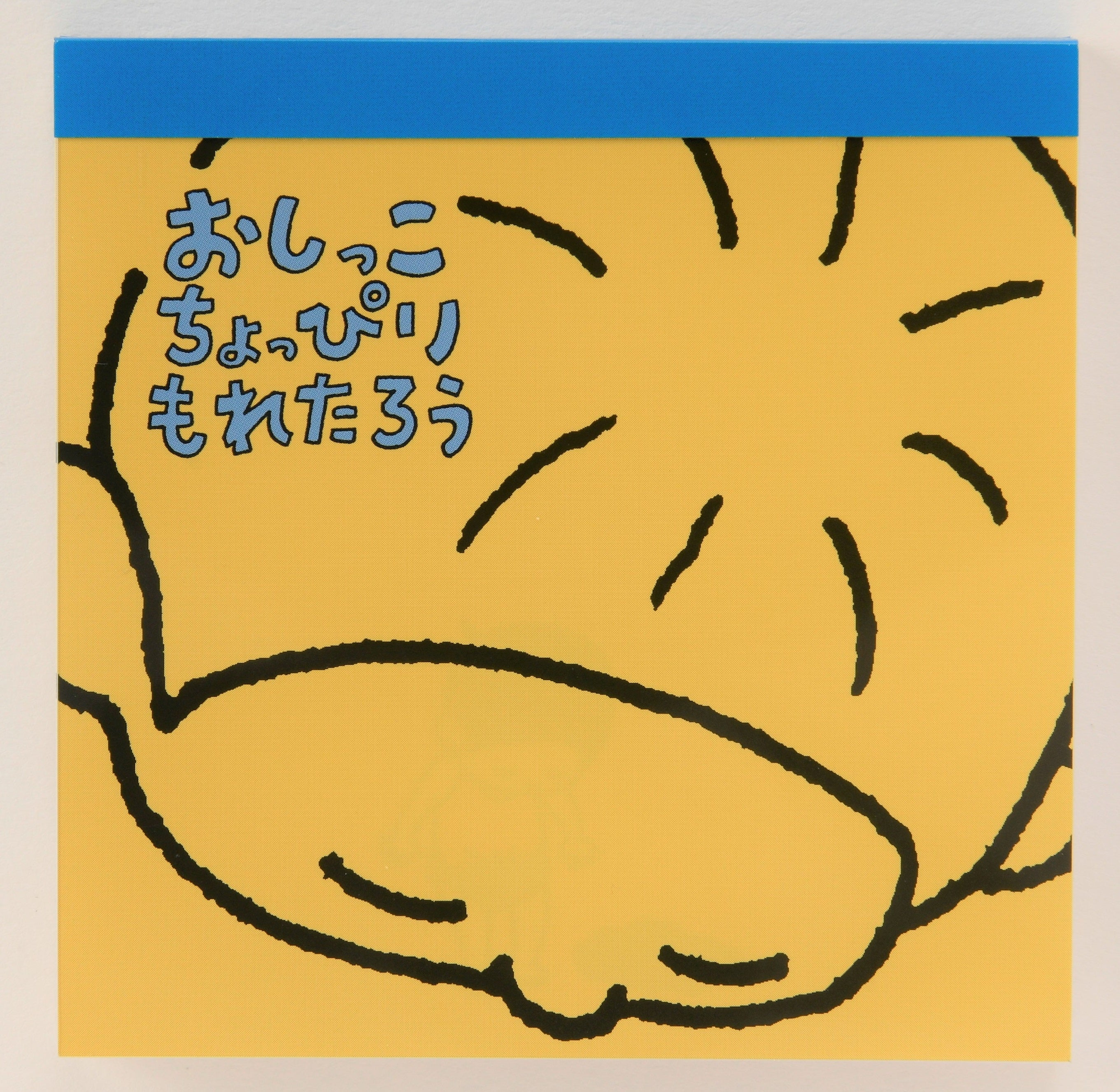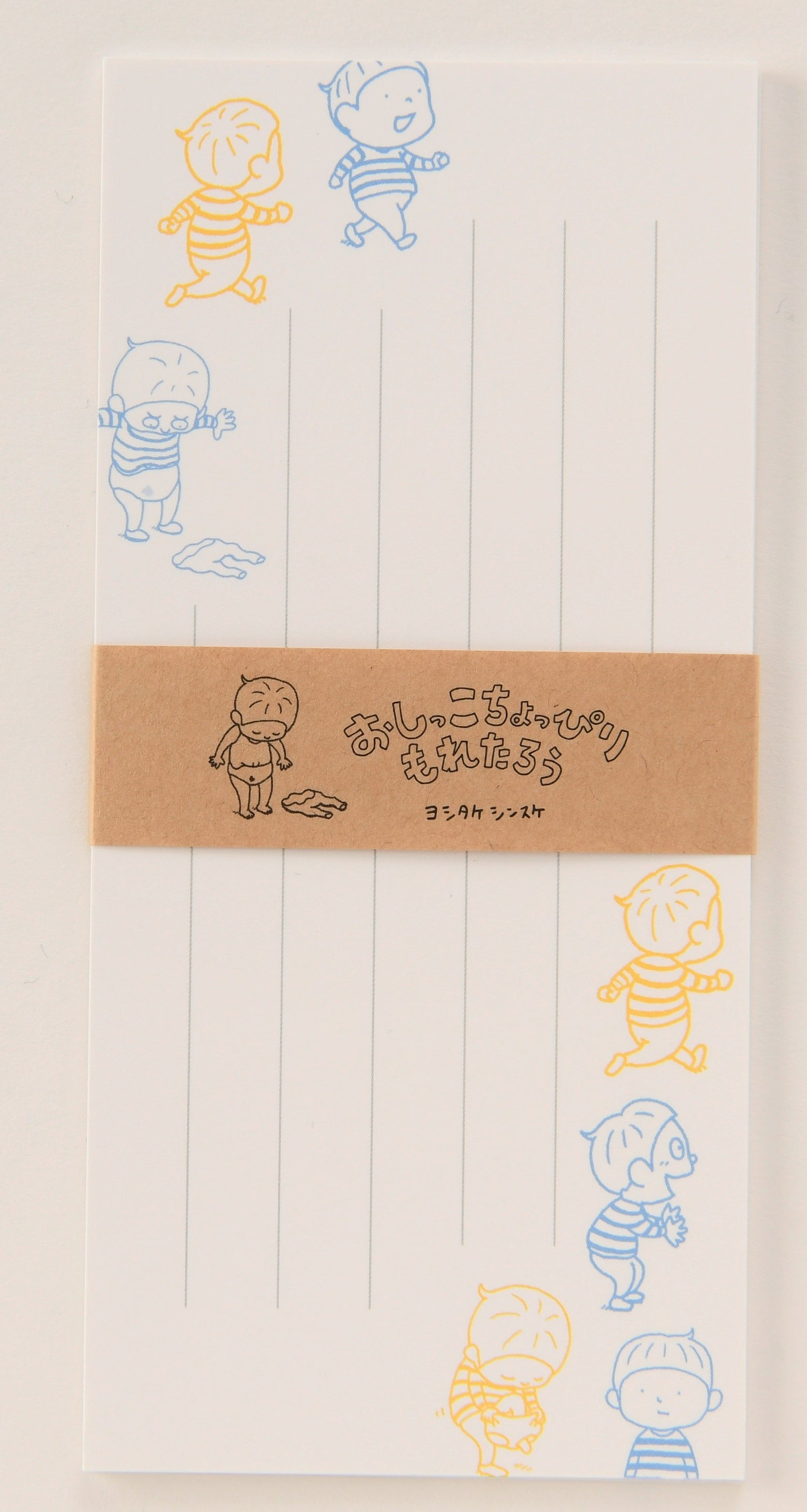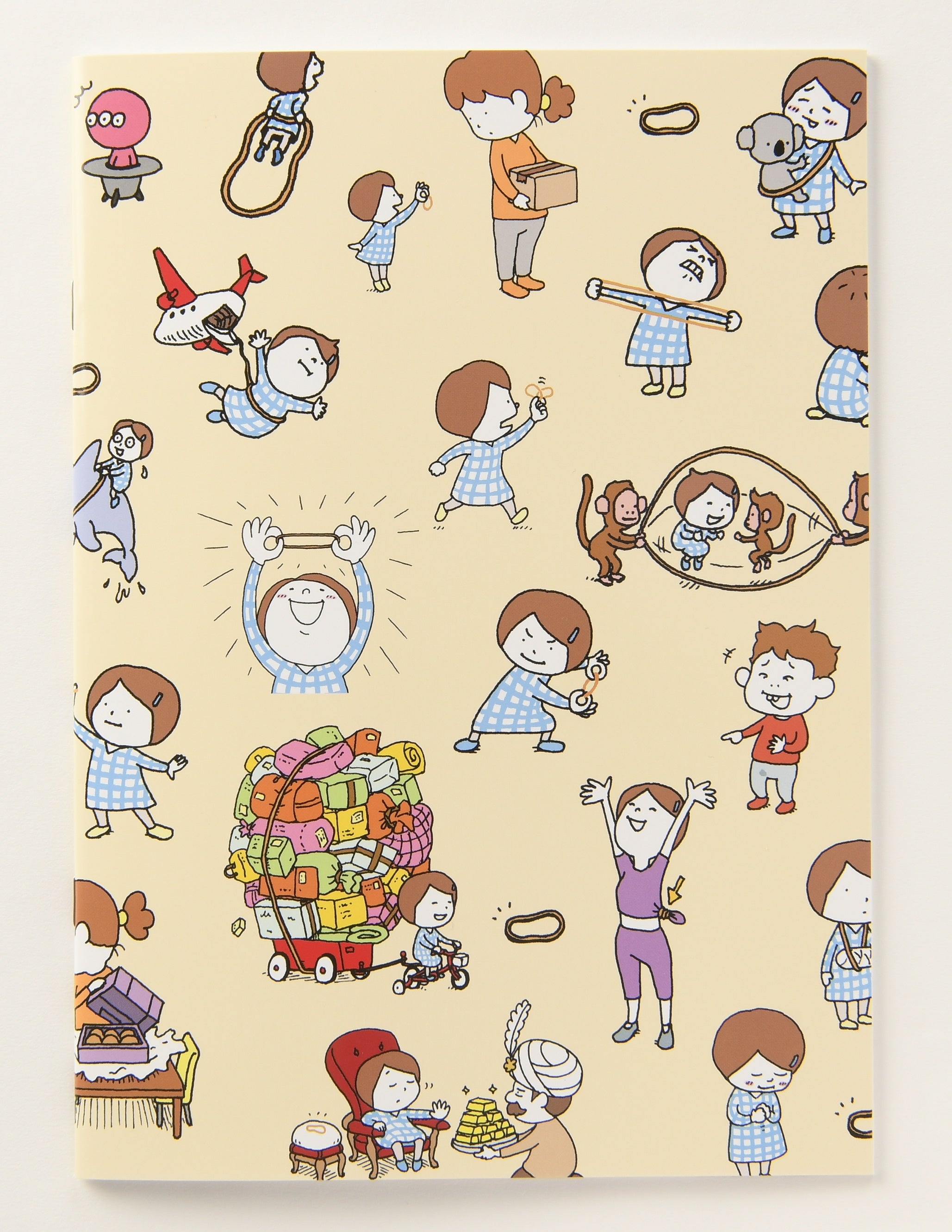女性なら知っておきたい“女性の糖尿病”
女性なら知っておきたい“女性の糖尿病”
私は現在、東京江東区で糖尿病専門のクリニックを開設し、日々大勢の糖尿病患者さんの診療にあたっています。
同志社大学を卒業後、受験勉強を開始し、東京女子医科大学に入学しました。医学部を卒業後、当時1日約500人の糖尿病患者さんが来院していた東京女子医科大学の糖尿病センターに入局しました。東京女子医科大学の糖尿病センターは1975年に平田幸正先生が日本で初めて糖尿病を専門に診る科として開設されたこともあり、糖尿病分野では日本で最先端の施設でした。そのため、全国から糖尿病患者さんが訪れ、中には他の病院に入院しているにもかかわらず、セカンドオピニオンを求め、パジャマ姿で受診する方も見受けました。合併症がかなり進んだ重症の方や、日本では一般的には少ない若い1型糖尿病の患者さんもたくさん診る機会がありました。数年病棟で研鑽を積んだのち、糖尿病の合併症研究のため、大学院に進学しました。大学院と臨床の二足のわらじを履いての日々は、実験、当直などでめまぐるしい日々でした。実験は病棟業務が終わってから行うことが多く、いつも首から病棟用のPHSと実験用のストップウォッチを常に2~3個ぶら下げていたので、鳴った瞬間、どれが鳴っているの? と思うこともありました。またその頃は、いつも実験室を出るのが0時以降だったことを覚えていますが、学位論文が発表できて、やっと報われたと思ったことも覚えています。そんな忙しい日々でしたが、この糖尿病センターで沢山の糖尿病の方々を診察する機会を得たことは、私の医師人生にとって、かけがえのない財産になっています。そしてさらに、若くしておこる突然死、失明、人工透析、足の切断を目の当たりにして、糖尿病の恐ろしさを実感し、医師として重症合併症を絶対防ぎたいという思いを強く心に刻むことにもなりました。
糖尿病の患者さんと20年近く接してきて、常々残念に思うことがあります。それは、糖尿病専門医が全国で一番多いとされる東京でも、すでに取り返しのつかない合併症の状態で受診される方々に遭遇することです。何故、もう少し早く受診に来てくれなかったのか、心から悔やまれる患者さんに出会うと、時間を巻き戻したい気持ちになります。
そして、診療の中で感じることの1つに、女性の糖尿病患者さんは、男性と違い発見が遅れたり、家族や周囲の影響をより受けやすいということです。発見が遅れる理由は、男性よりも健診を受ける機会が少ないことが原因していますが、その他に、女性が糖尿病になりやすくなる40代以降は、更年期も併発することが多く、そのわずかな糖尿病の自覚症状を更年期が原因であると思いこむことにもあるからです。
そして、女性で家庭を持っている方は特に、家族に合わせる生活スタイルを余儀なくされています。その結果、食事時間も不規則になり、家族の帰宅時間が遅いことで睡眠不足にもなりがちです。早朝のお子さんのお弁当作りが控えているのに、ご主人が夜中を過ぎて帰宅し、そこから食事の世話、睡眠不足が解消できないなどの声もよく耳にします。
不規則な食事、睡眠不足は確実に血糖値を上昇させます。また、急に血糖コントロールが悪化した50代の女性に話を伺うと、「両親の認知症が始まって奔走していた」など、よく耳にします。働く女性はさらに仕事場でのストレスもあり、なおかつ家族の世話にも追われ、ついつい自分のことは後回しにしてしまいがちです。
私も同じ仕事を持つ女性として、また妻、母として奔走する毎日です。診察に加え、論文作成、講演準備、夕食の支度、子どもの世話などなど、毎日が綱渡りです。子どもに急な熱で学校を休まれたら、あっという間に綱から落ちてしまいます。でも、どれも手を抜きたくないのです。幸い、女性は男性と違っていくつかのことを同時に並行して行うことが得意なのではないかと思っています。だから、ある程度まではこなせてしまうのかな? とは思っていますが、それは健康であってこそです。
クリニックでも、仕事に加え家族のためにも一生懸命やってきて、受診の機会を逃し、重症の糖尿病になってから来院される40代の女性に出会うことは少なくありません。最後の採血はいつですか? とお伺いすると、なかには「お産のとき以来です」とお答えになる方もいます。
長年糖尿病に特化した診療を行うにあたり、合併症の恐ろしさを実感しているからこそ、この本を通して、日々頑張っている女性のみなさんに糖尿病への知識を深めて欲しいと思います。そして、この本がその予防や合併症の進行を防ぐ一助となれば、医師としてこんな嬉しいことはありません。 (「はじめに」より)
著者:岡本亜紀
縦:21×横:14.8 全頁数:160ページ
重量194g厚さ1cm
99 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした