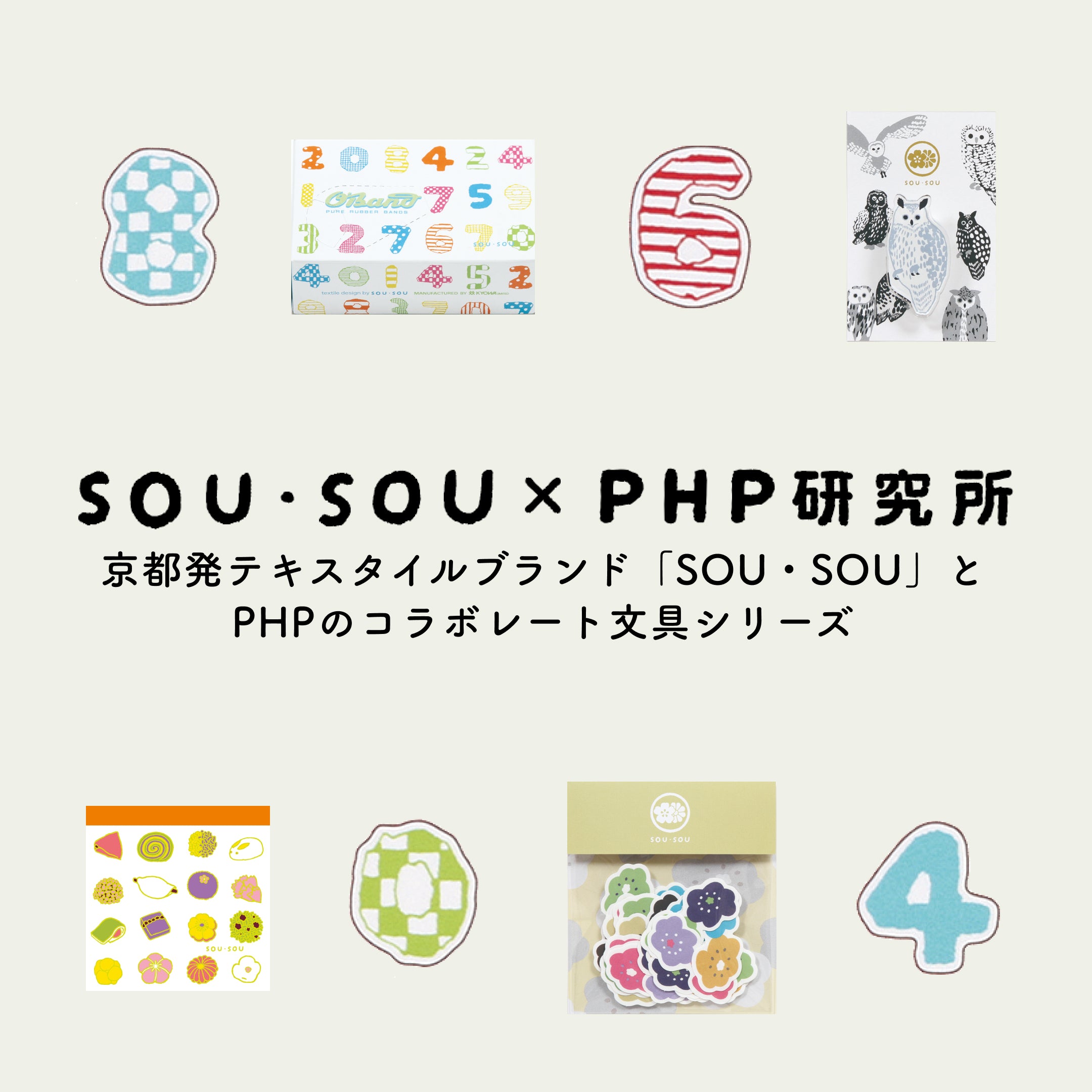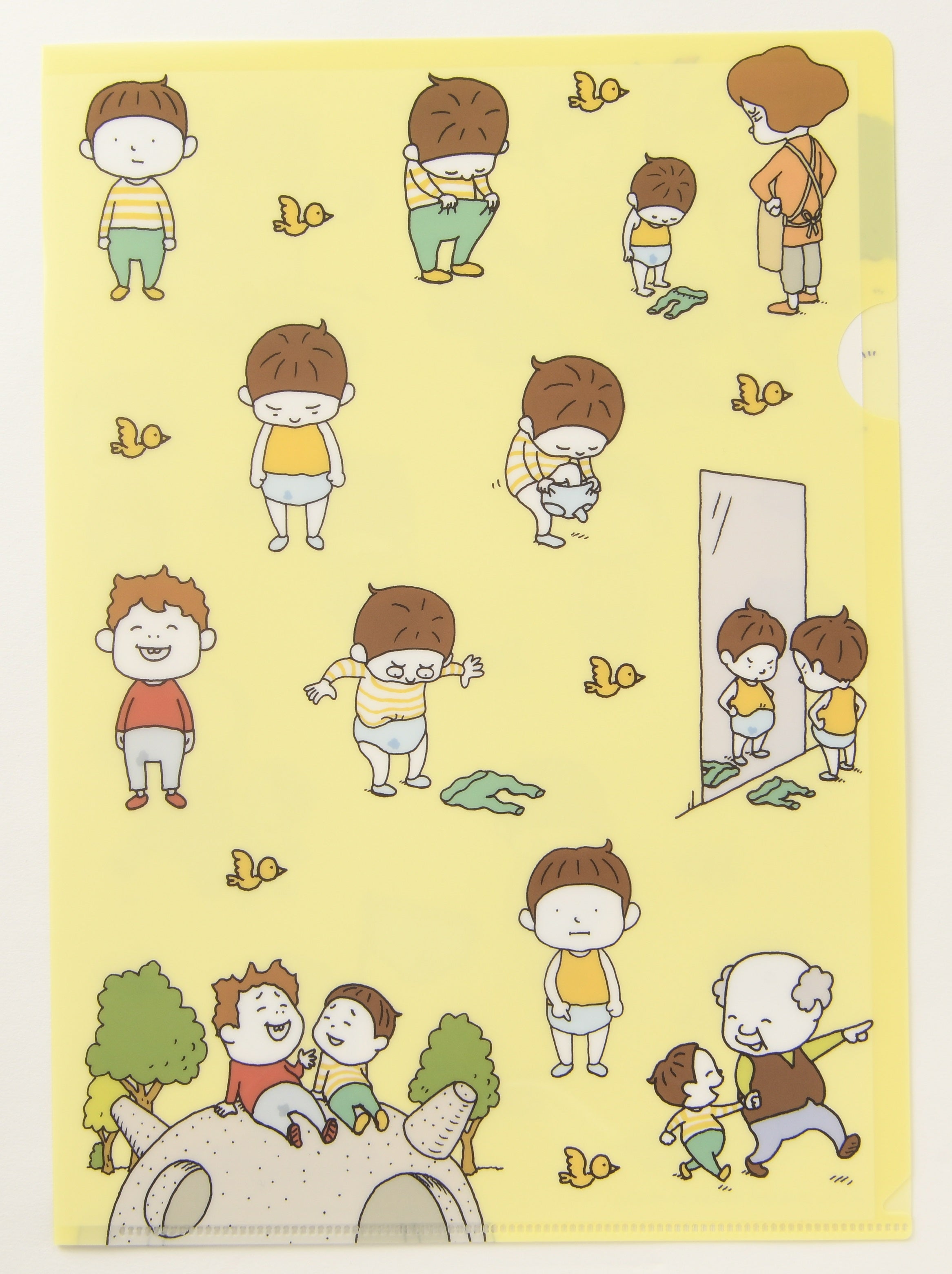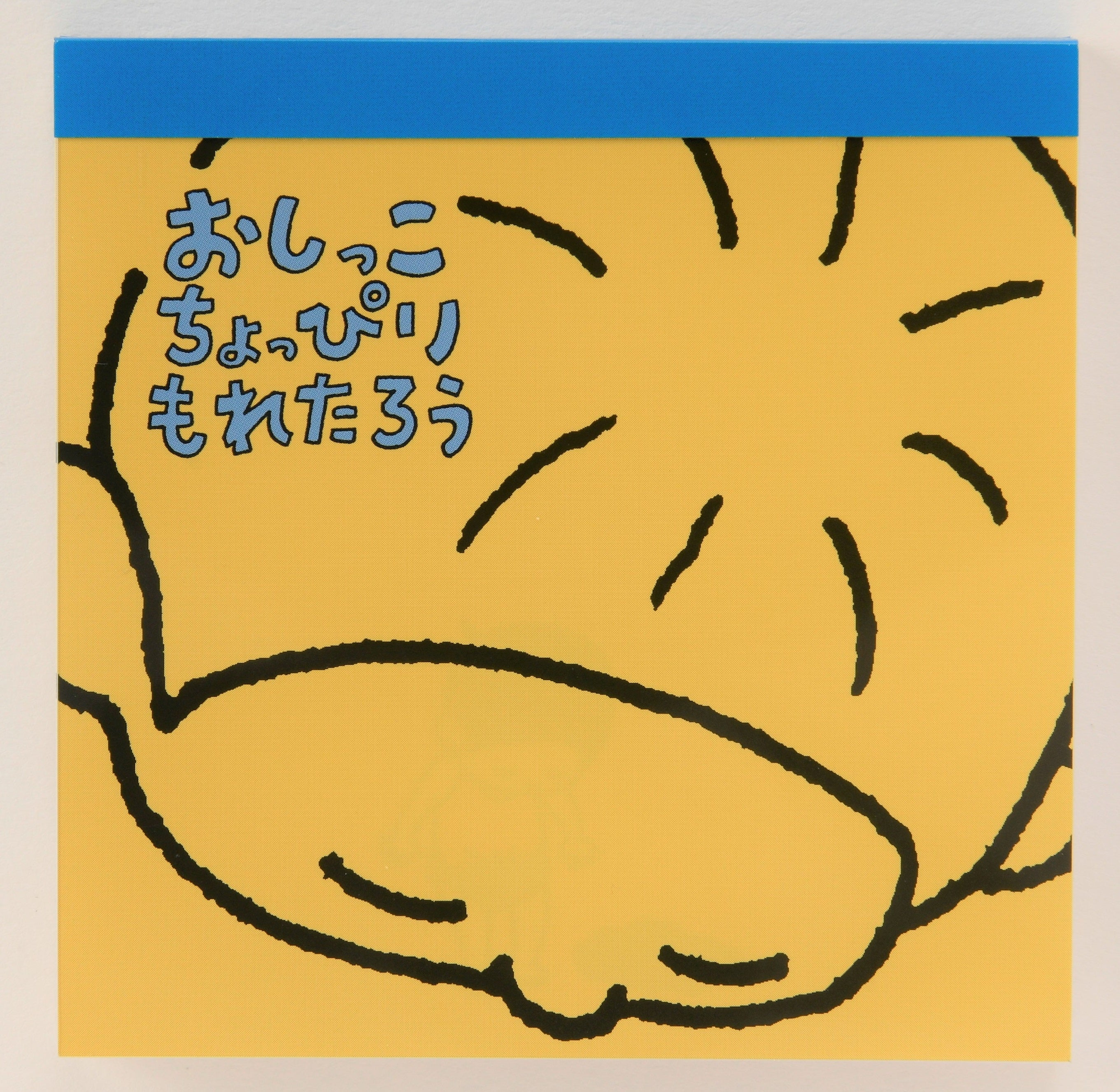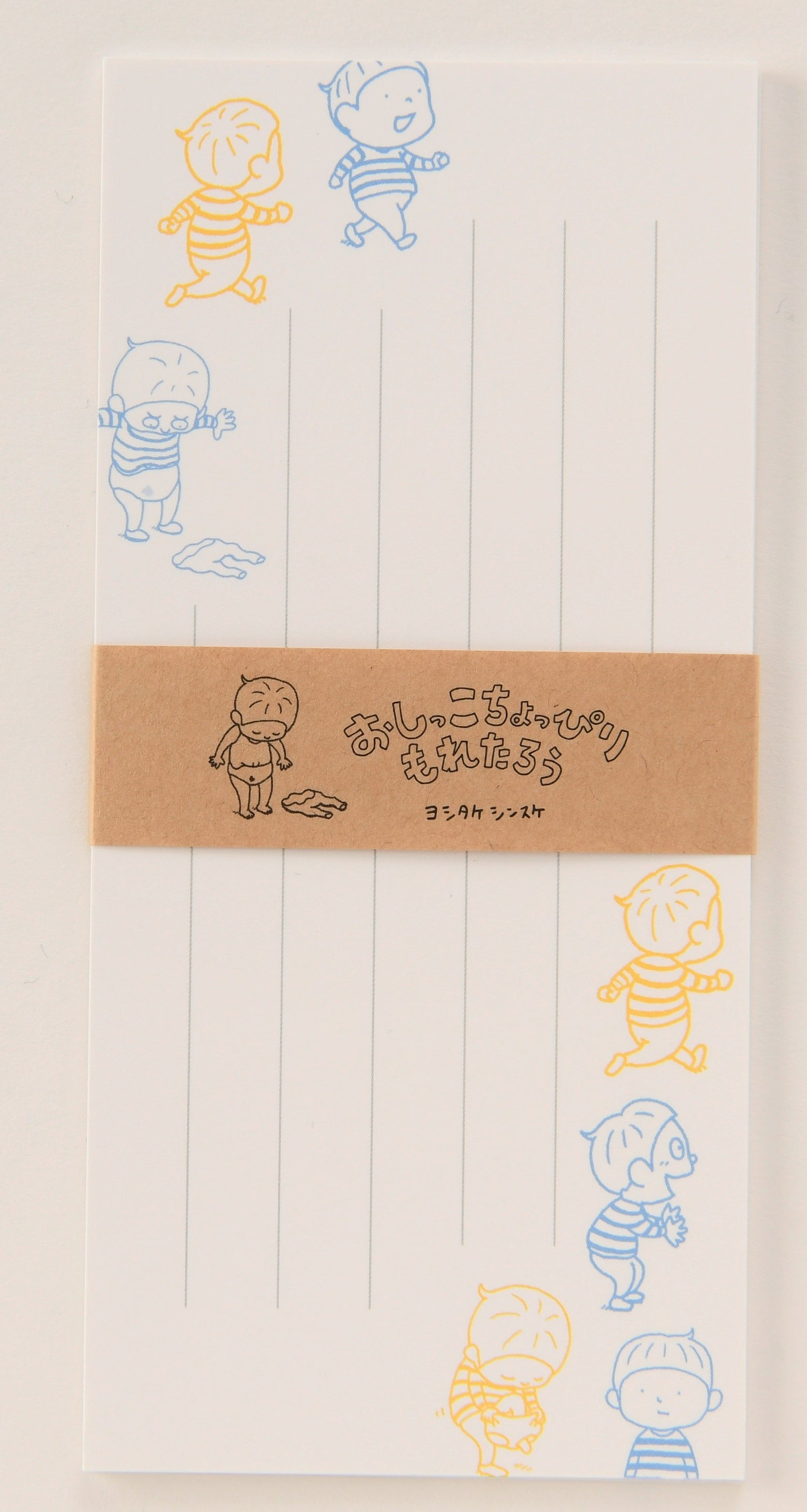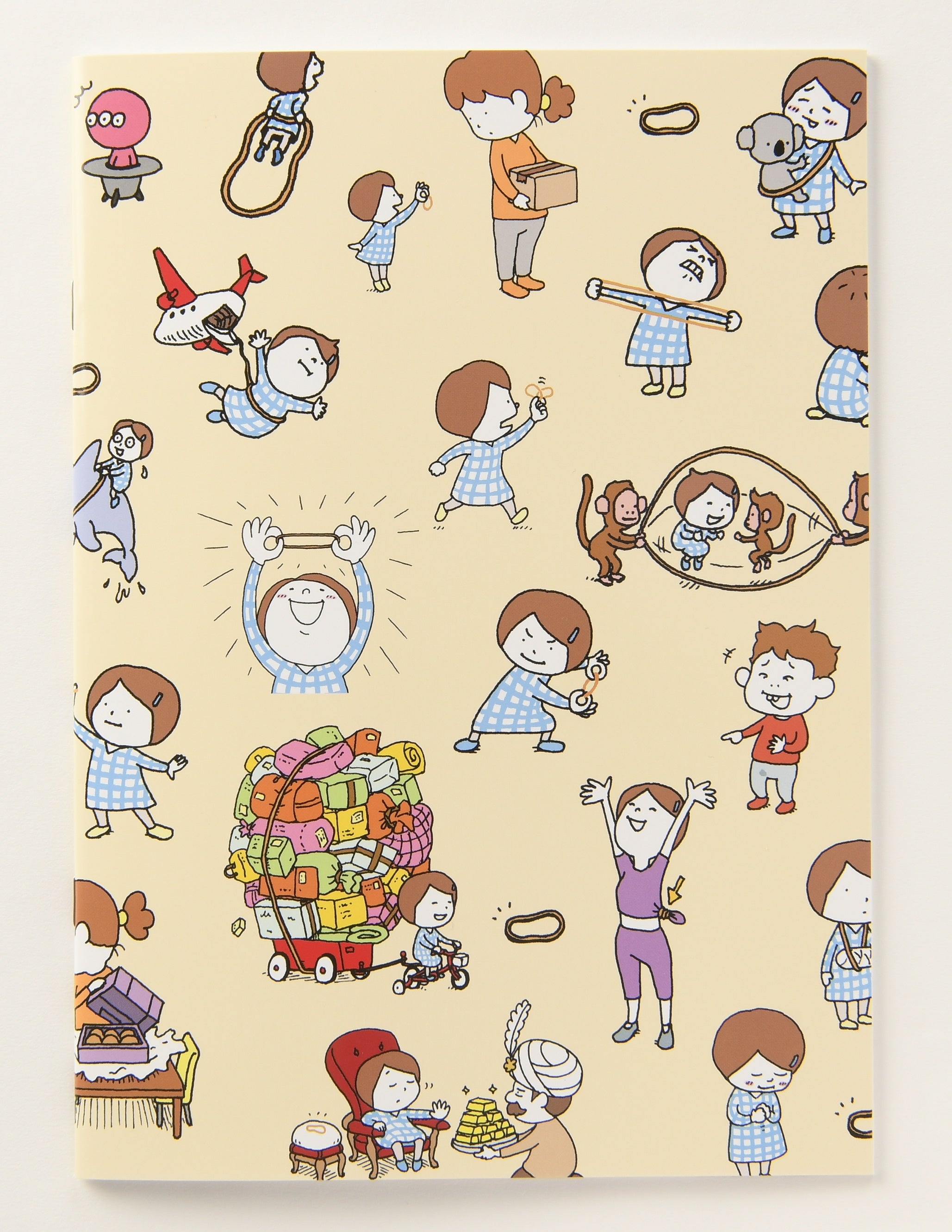発達障害の子に1分でちゃんと伝わるお母さんの言葉がけ
発達障害の子に1分でちゃんと伝わるお母さんの言葉がけ
ある研修会で、発達に障害のある子どもたちの行動の理由と、それに対する配慮や工夫についてお話しすることがありました。話し終えたあとで、幼稚園の年長さんのお嬢さんをお持ちの、ひとりのお母さんが話しに来てくださいました。
「今日、先生が話された行動特徴の多くを、うちの子も持っています。幼稚園の先生から、子どもの激しい行動について、『お母さんの愛情不足』と言われてきました。今日のお話をお聞きして、病院に行って、娘の様子を見てもらおうと決心しました」
お母さんはこれまで幼稚園の先生から言われた「愛情不足」という言葉で、ご自身を責め続けてきたそうです。その話をされたときには声が詰まり、目には涙を浮かべていらっしゃいました。
また、巡回相談に行った先の中学校で出会った自閉症の男の子は、勉強にまったくついていけず、すべての教科の定期考査の点数は0点。授業中は、ノートを写すこともできずに、神経質に周りを常に見回していました。さらに、トゥーレットといういくつかのチックが頻発する症状を示していました。朝、学校に行くことを渋り、登校してもすぐに帰りたくなり、保健室に飛び込む毎日が続いていました。親御さんは、本人のそうした状況を学校から報告されていたものの、「うちの子は大丈夫です」と言い続けていたそうです。
発達障害は、非常にわかりにくい障害です。どこの線からが発達に障害があるのか、そうでないのかが、見えにくいのです。ですから、時に子どもの独特の行動を、親の育て方の問題にされてしまうことがあります。あるいは、「発達に障害がある」ということを見極められずに、子どもに限界を超えた無理をさせ、子どもからのぎりぎりのSOSを見逃してしまうことがあります。
発達障害ということについて、もっと社会の理解が進んでいけば、こうした悲劇が減っていくのだろうと思います。
小学校の低学年から、学校で大きなパニックを頻発して、教室に入れない日々が続いたアスペルガー症候群の男の子がいます。お母さんは、「うちの子は0か100です。中間がありません」とおっしゃっていました。たとえば、身体の不器用さと、反響する大きな音への過敏性から体育の授業には参加したくないのに、「ぜったい参加しなければならない」と思い、その葛藤から身体が動かず、1時間を超えるパニックを起こすといったことが連日続きました。しかし、宇宙や科学に関する彼の知識には、目を瞠るものがあり、相談室でそうした話をする彼は、とても自信に満ちていました。
やがて小学5年生になり、彼の特徴を上手に引き出してくれる先生に出会ったことがきっかけとなり、パニックは激減。中学校では、常に成績はトップクラスとなりました。そして今、彼は科学者を目指して勉強に励んでいます。
発達に障害があるということは、生活に「しにくさ」があるということです。しかし、周囲の人の理解と工夫により、その「しにくさ」は改善されます。さらに改善だけではなく、彼ら・彼女らの持つ素晴らしい才能が開花します。そんな思いで、本書を執筆しました。少しでも皆さまのお役に立つことができれば幸いです。 (「はじめに」より)
著者:小笠原 恵
縦:21×横:14.8 全頁数:192ページ
重量312g厚さ1.2cm
100 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした