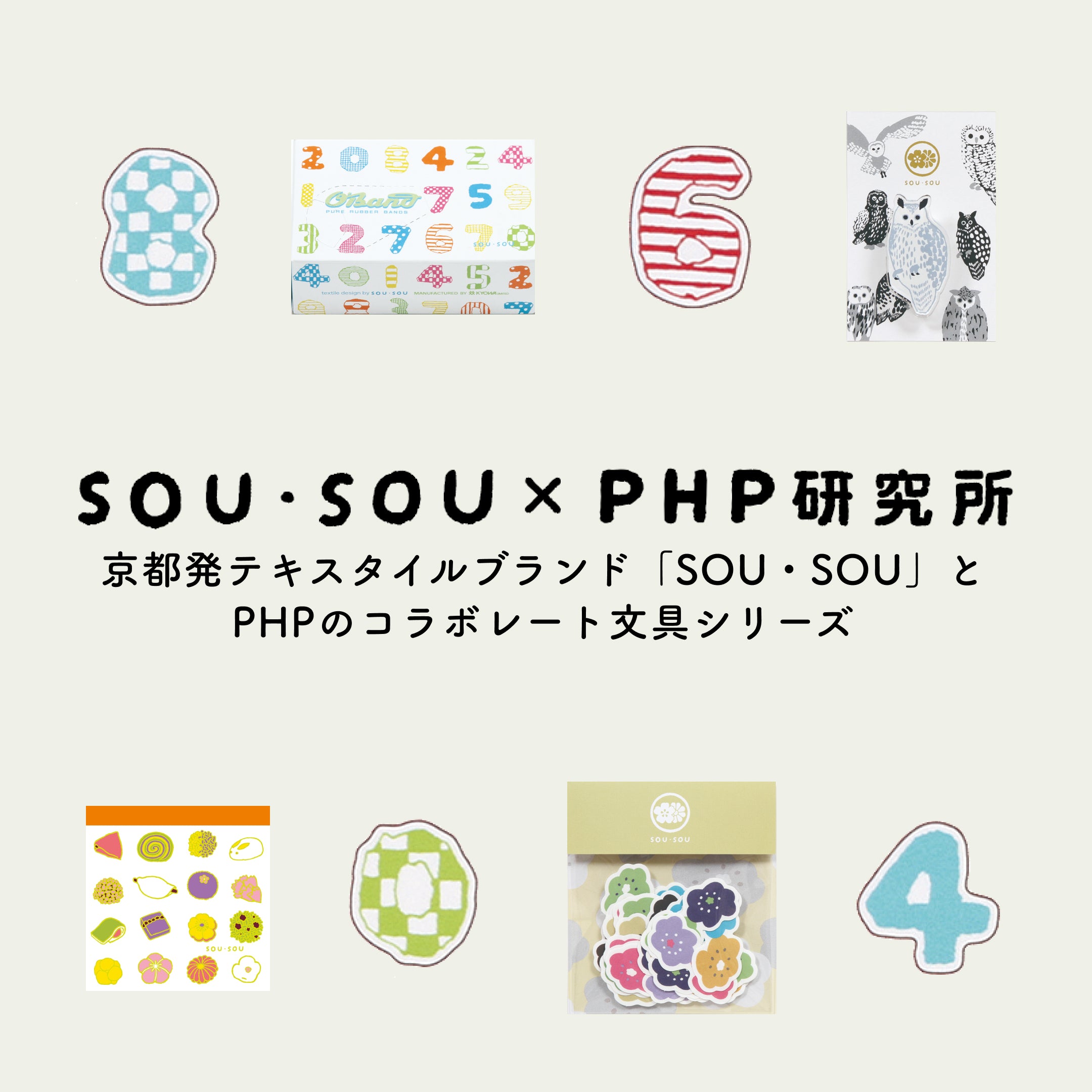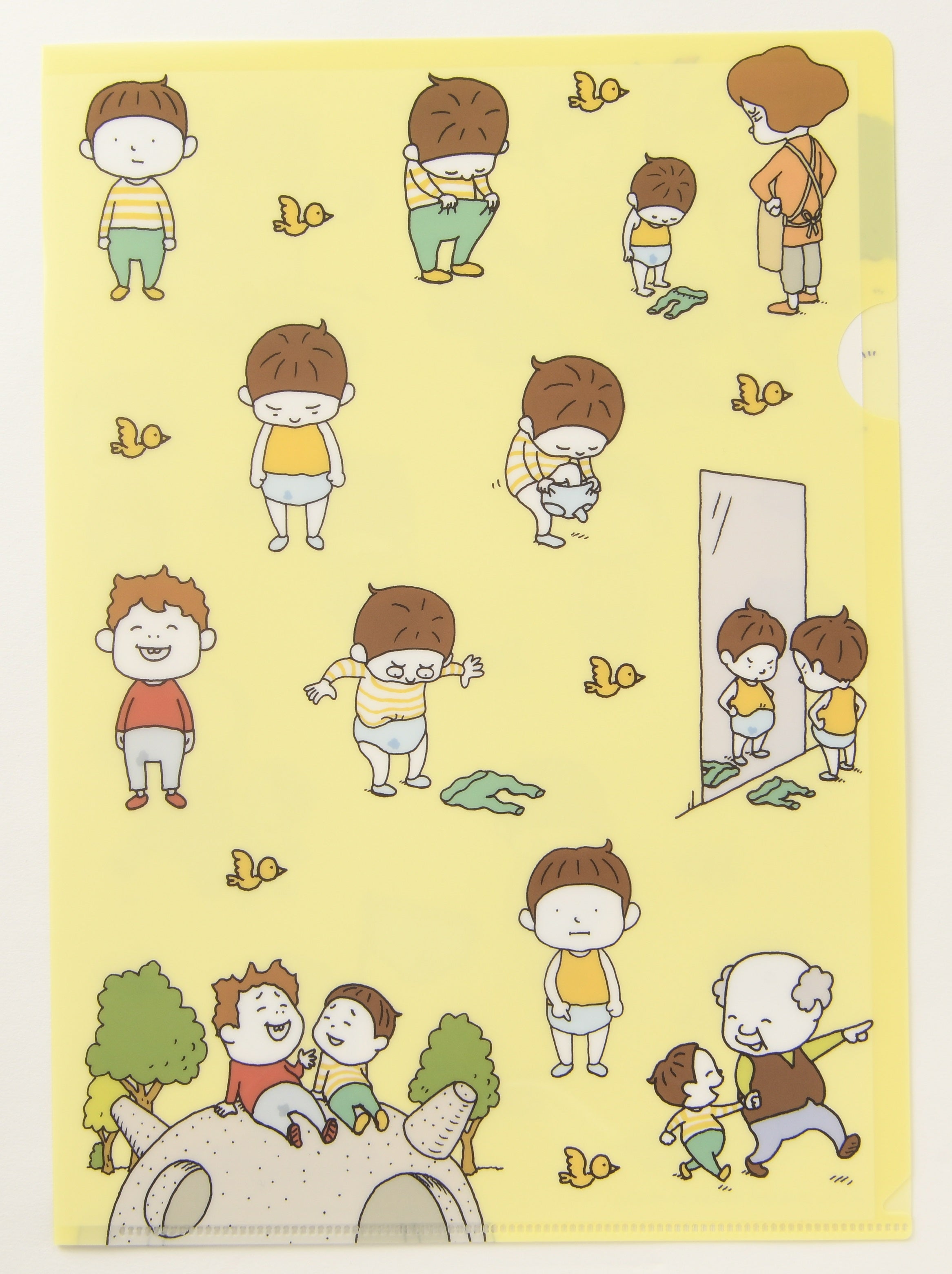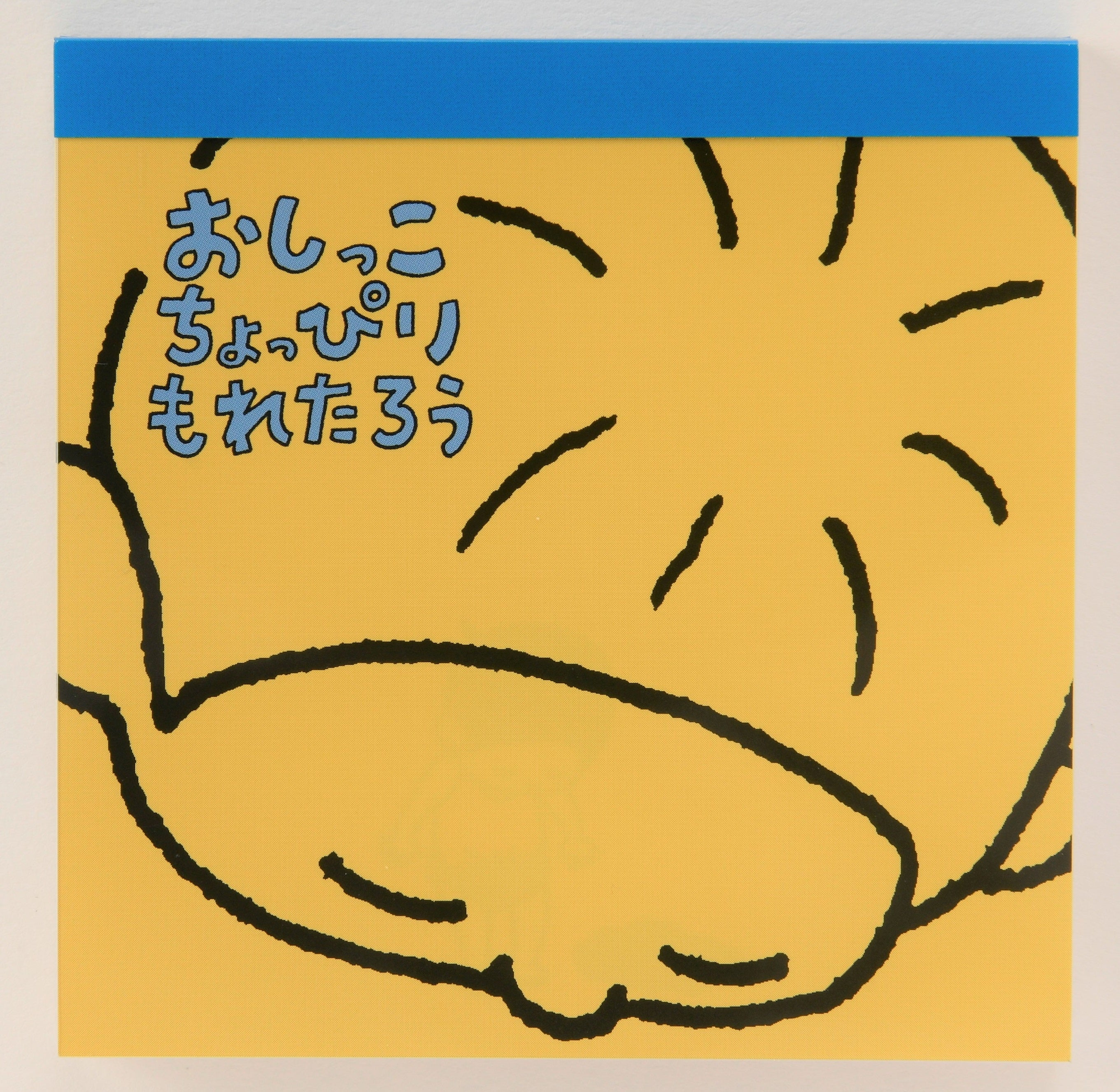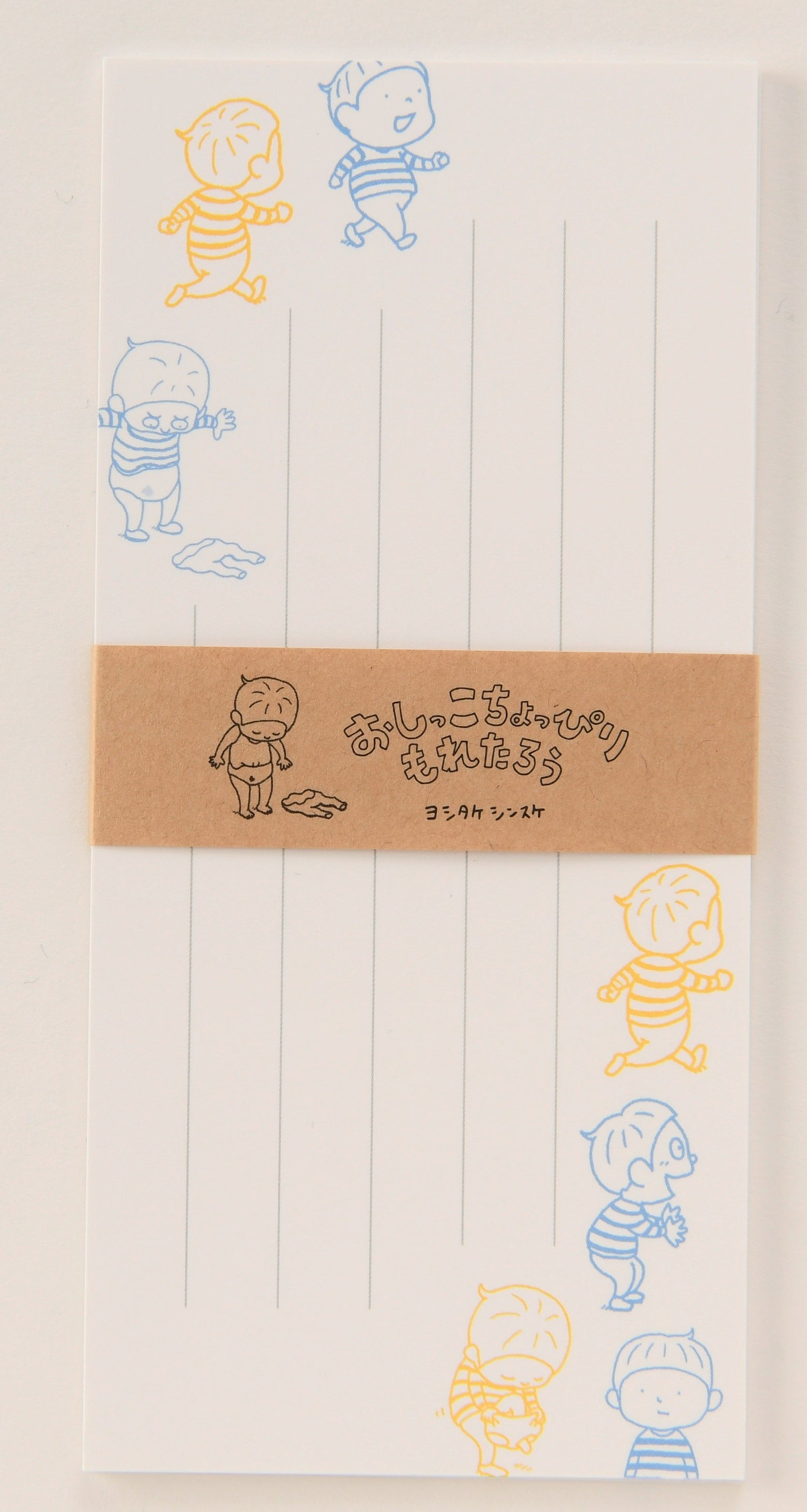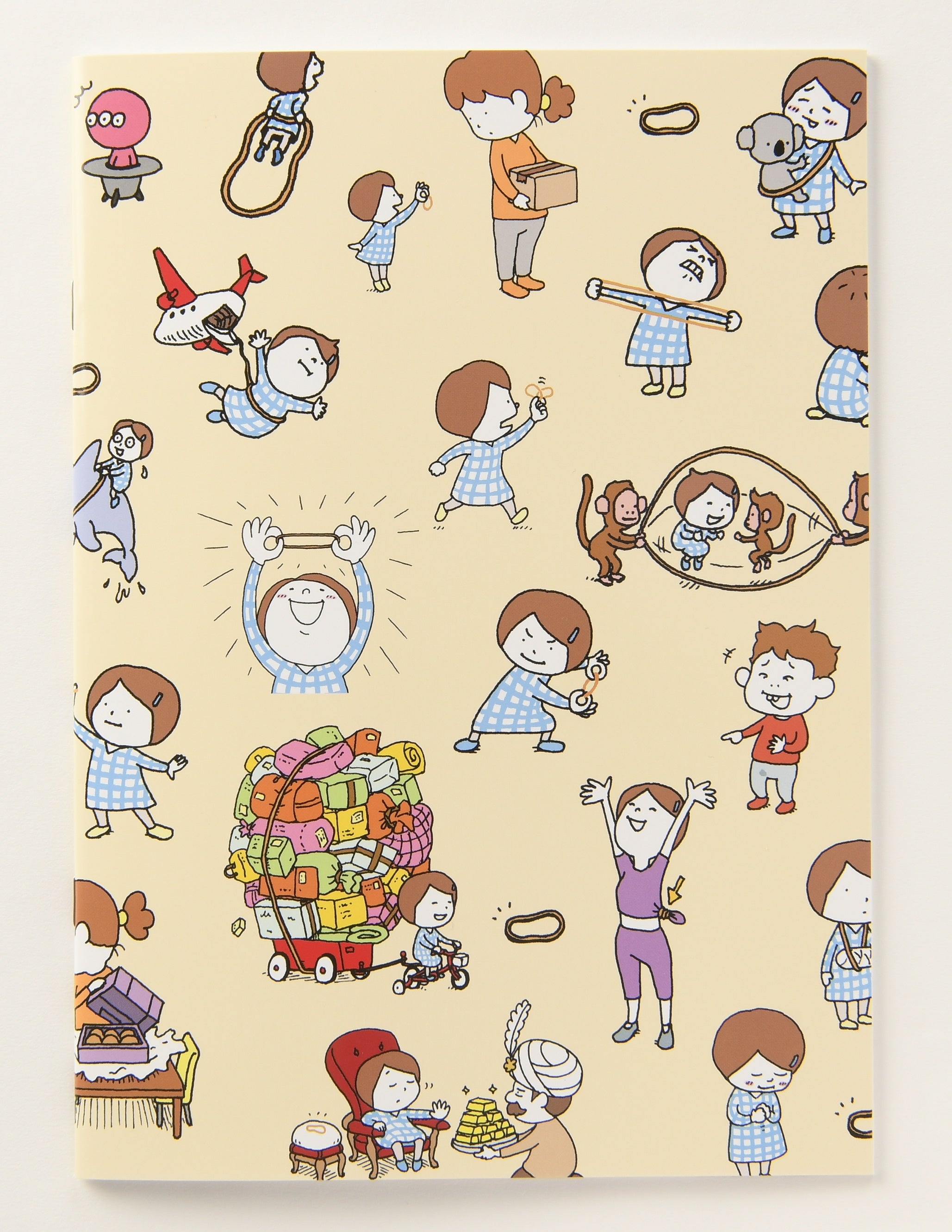下肢静脈瘤は自分で防ぐ! こうして治す!
下肢静脈瘤は自分で防ぐ! こうして治す!
◆下肢静脈瘤は静脈の病気です
それでは、「下肢静脈瘤」についてお話ししていくことにしましょう。
下肢静脈瘤という名前を聞いたことはあっても、詳しくはわからないという人が多いのではないでしょうか。実際、その症状や状態にはいろいろなケースがあり、場合によっては見た目にはわからないこともあります。
そこで、下肢静脈瘤とはいったいどういうものなのか、具体的なケースを挙げながら説明するとともに、どういうことが原因で起こるのかを、細かくお伝えしようと考えました。そのうえで、日頃の生活でできる予防法やケアをご紹介しましょう。
まず、知っておいてほしいのは、下肢静脈瘤とは静脈の病気であること。静脈になんらかのトラブルがあり、起こることなのです。
「静脈」といわれると、なんだかわかりにくいかもしれませんが、血管には静脈のほかに「動脈」があるのをご存じだと思います。
動脈が事故などで切断してしまった場合、すぐに処置をしないと出血多量で死んでしまいます。また、加齢やコレステロールの摂りすぎで血管の壁が石のようになり、血管内腔が細くなる「動脈硬化」や、動脈が閉塞してしまうことで引き起こされる「脳梗塞」や「心筋梗塞」といった病気があります。いずれも死に至るリスクを抱えています。
そのような点からも動脈は医学の世界でこれまでにいろいろと研究され、大まかにそのメカニズムも判明しています。さまざまな治療法や予防法も開発されています。
そんな動脈に比べると、静脈は「あまり悪さをしない血管」と、いわれてきました。静脈は血管が切れたとしても自然に再生する力を持っているし、血管に瘤のような塊ができても、動脈のように破裂することは滅多にありません。
静脈に関しては死に至る大病となることが稀とされ、たいして重要視されることもなく、熱心に研究されることもありませんでした。そのため、静脈のしくみや働きについて、あまりわかっていないのが実情です。
ところが近年、静脈のトラブルが深刻な問題を引き起こすことがわかってきました。
たとえば、「エコノミークラス症候群」です。
飛行機の狭いイスに長時間座っていて起こりやすくなることから、こうした名称で呼ばれていますが、大地震などの災害時に避難先で被災者の身にも起こることがテレビや新聞のニュースでも取り上げられました。
イスに座ったままや、クルマの車内などで寝泊まりをして長時間同じ姿勢でいたり、あまり歩かなかったり、トイレに行く回数を減らすために水分摂取量を控えたりすることで起こる脱水症状などが原因となり、足の静脈に「血栓」という血の塊ができます。その血栓がなにかの拍子に肺まで流れ、肺の血管を詰まらせることを「肺塞栓症」といい、呼吸困難や失神を引き起こします。
大きな肺梗塞はショックを引き起こし、一時的に心停止となり、心臓が止まってしまいます。多くはその際に脳梗塞や心筋梗塞を伴います。
静脈の病気といえどもあなどれず、動脈同様、ことによっては重篤な状態になりかねないのです。
私は、血管外科医として20年以上にわたって静脈瘤の治療にあたり、静脈の研究を進めてきました。2008年に京都でクリニックを開いてからは、診察した症例も1万2000件を超し、多くの患者と接するうちに、ようやく下肢静脈瘤が起こる本当の理由がつかめてきました。そして同時に、長い間ナゾとされてきた静脈の正体も、徐々にわかりはじめてきました。
そのような結果、判明したのが、「静脈はカラダの重大な異変をいち早く感知してシグナルを送ってくれる大切な器官である」ということです。静脈で起こったトラブルは、大病の前兆ととらえることができるのです。
下肢静脈瘤は、いわば下肢=足に瘤ができる静脈の病気なのですが、足に起きた異変がやがてカラダ全体にも影響を及ぼすかもしれないという合図を、私たちに送っているのです。放っておけば、エコノミークラス症候群といった重篤な病気の引き金にもなりかねない、怖い病気であるといえます。
その一方で、静脈自体のメカニズムやからくりがわかるにつれ、静脈瘤の適切な治療法が見え、静脈瘤に対する効果的なケアや予防法もわかってきました。
この本では、そうした私の研究をもとに、「下肢静脈瘤になりにくいカラダになる」知恵や工夫をお話ししようと考えています。
カラダを下肢静脈瘤になりにくくするということは、静脈をつねに健康な状態に保つということ。それはすなわち、健康で元気なカラダづくりをするということでもあるのです。 (「はじめに」より)
著者:佐藤達朗
縦:29.7×横:21 全頁数:136ページ
重量416g厚さ0.9cm
100 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした