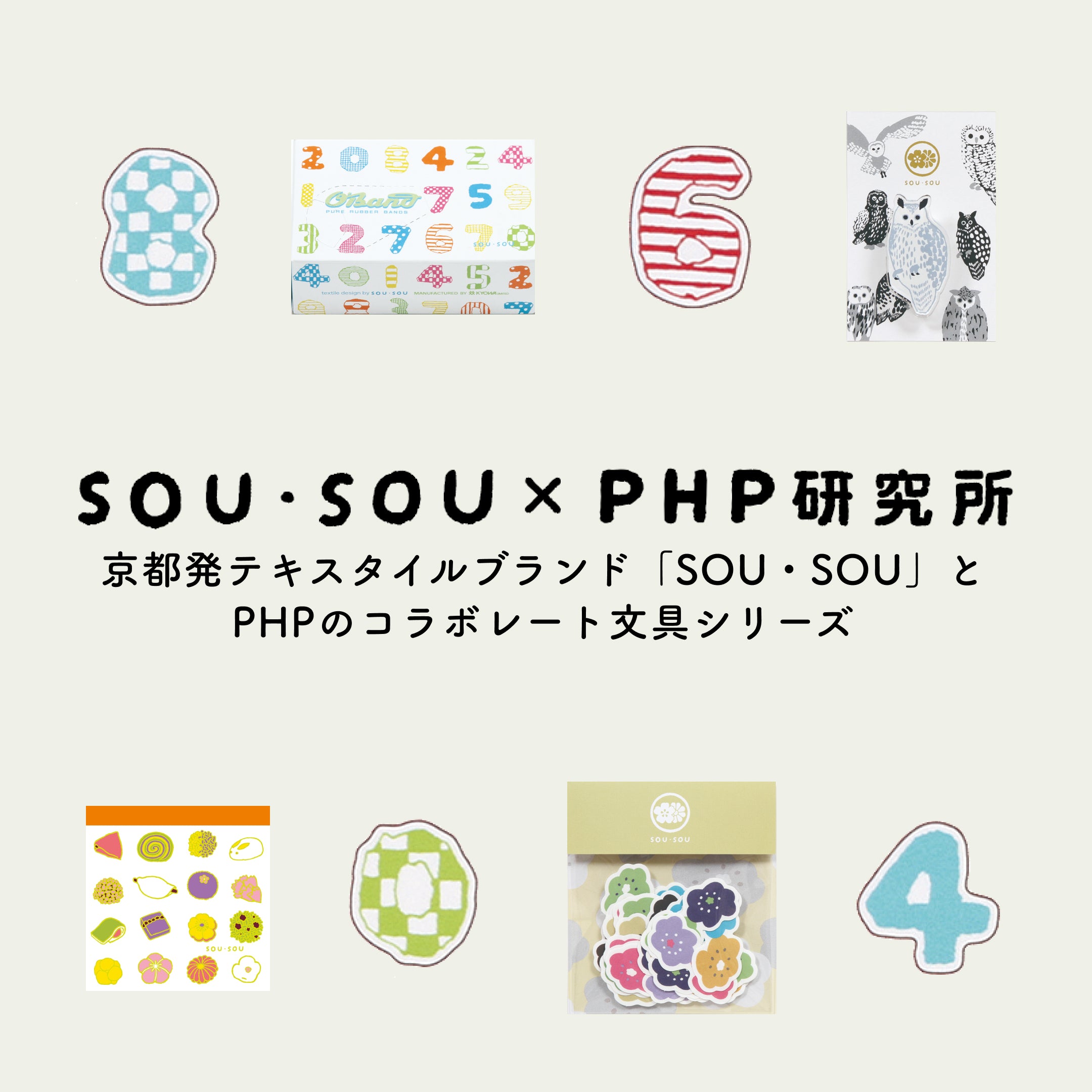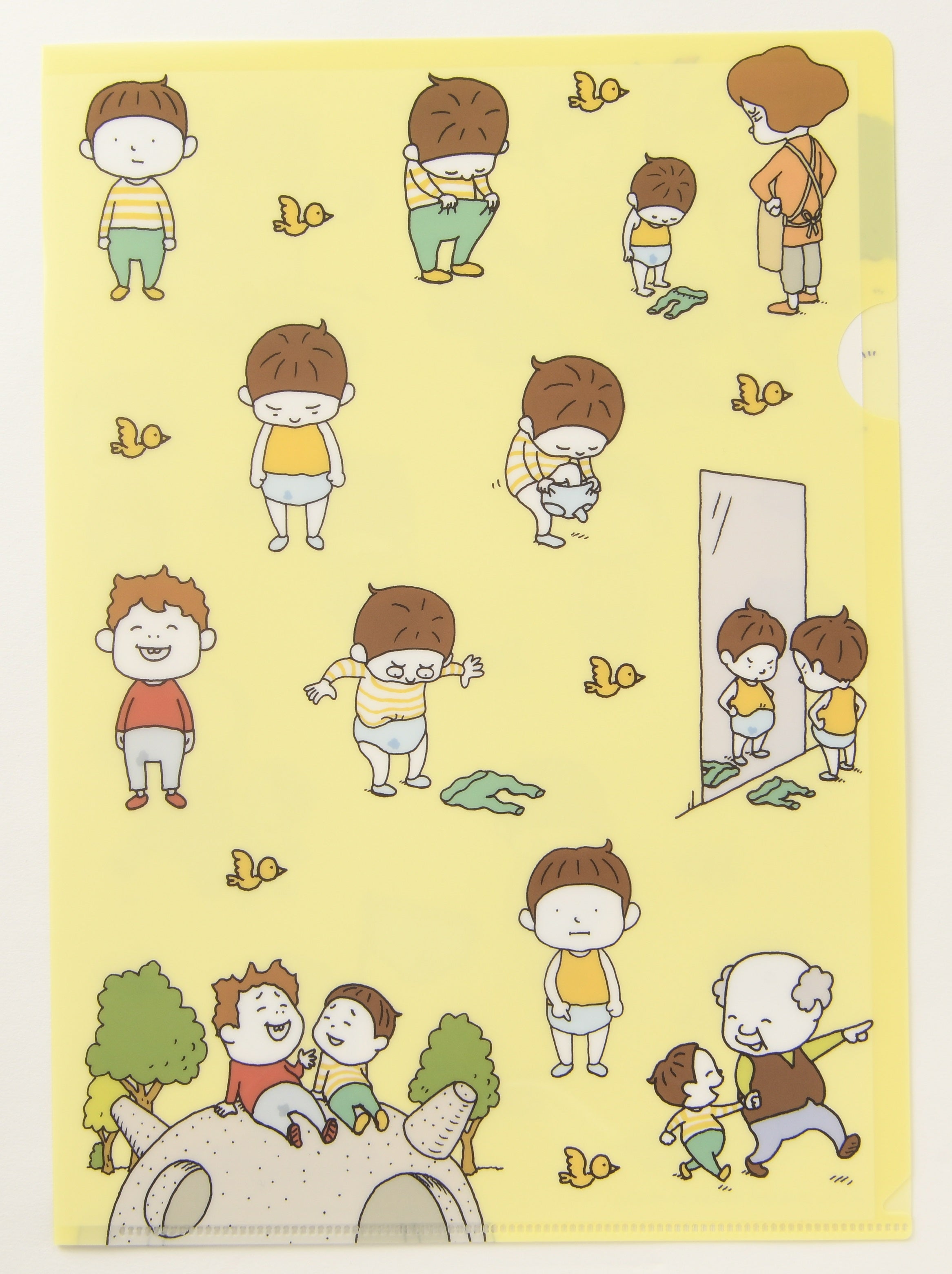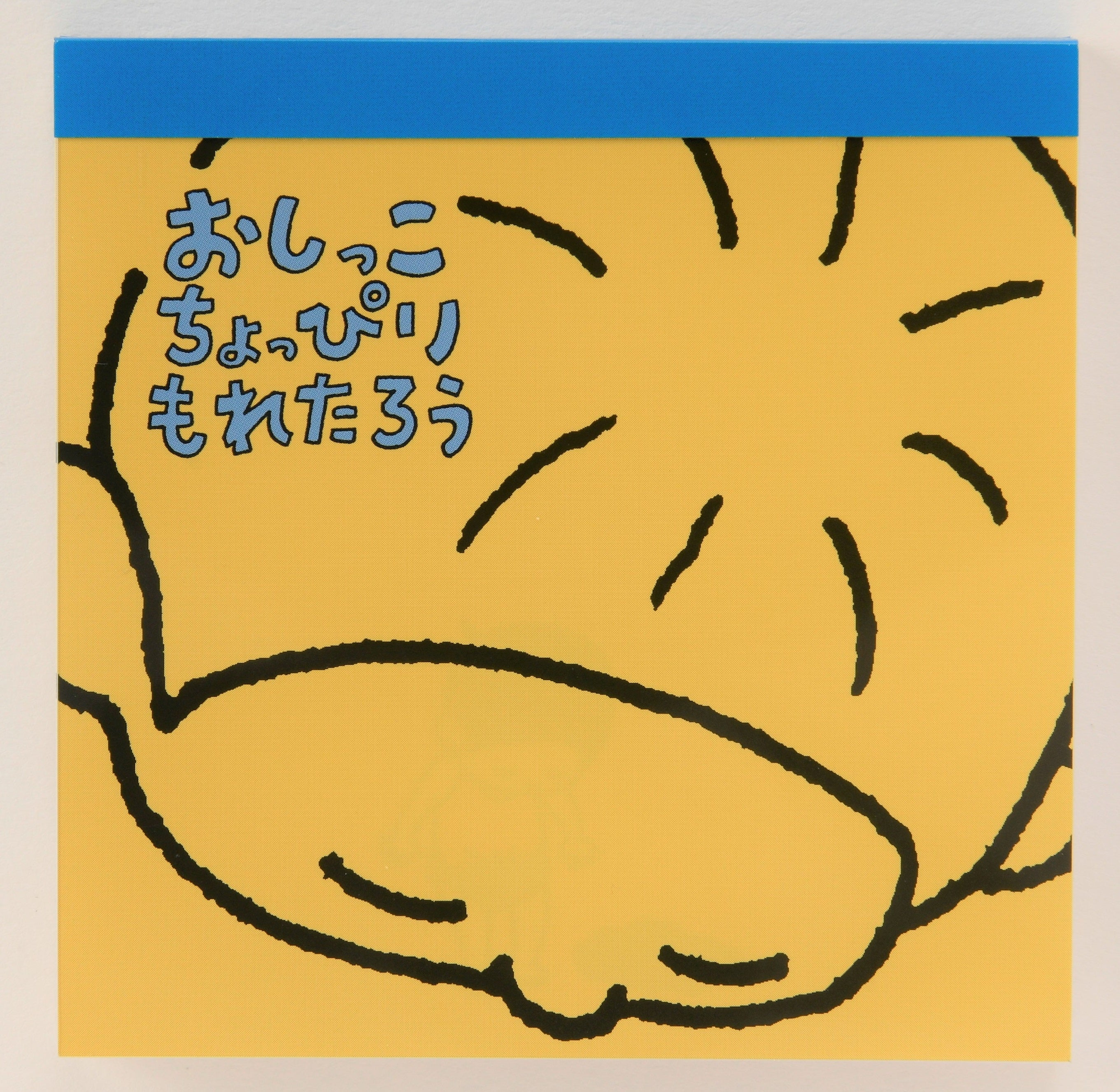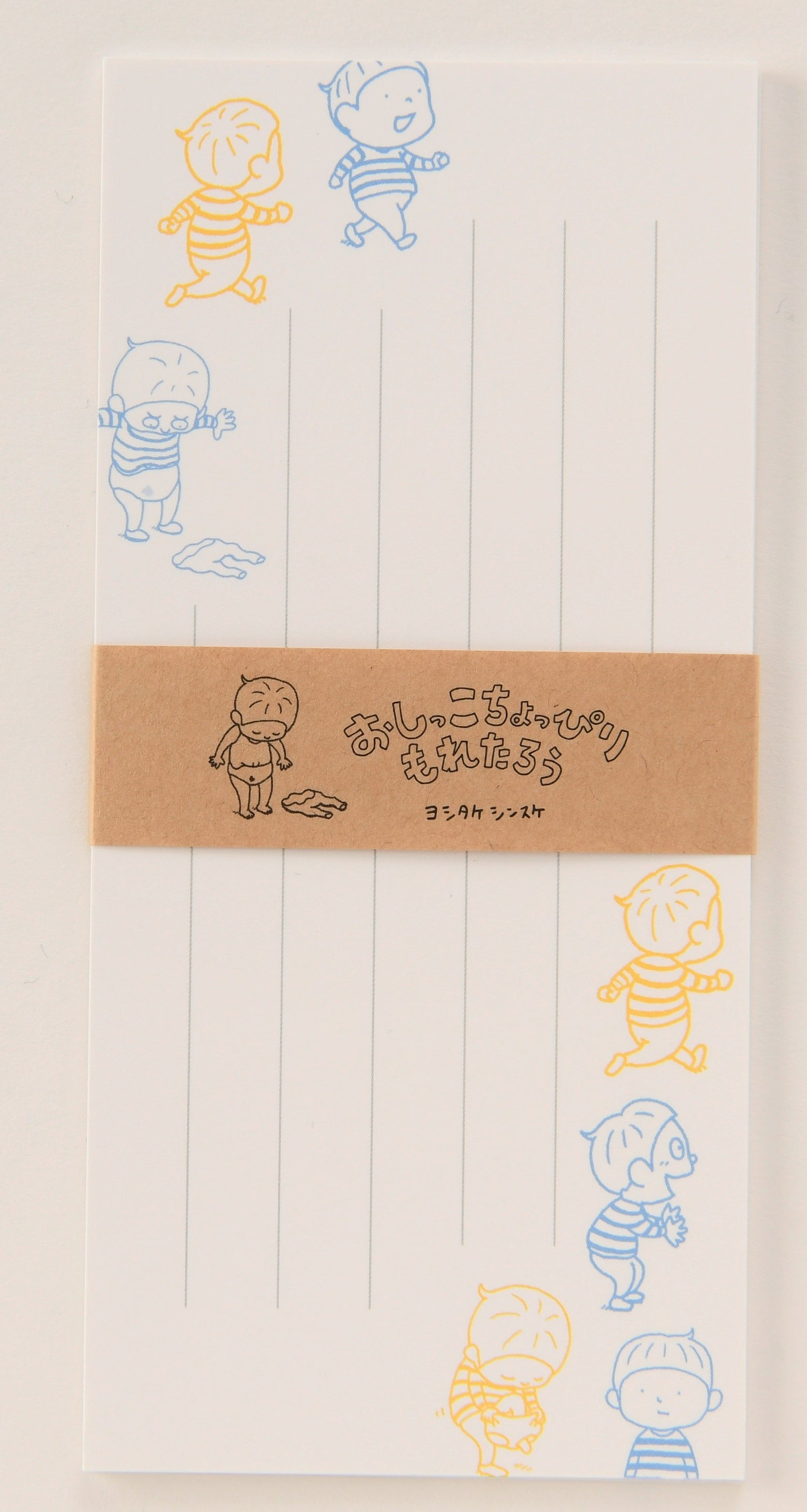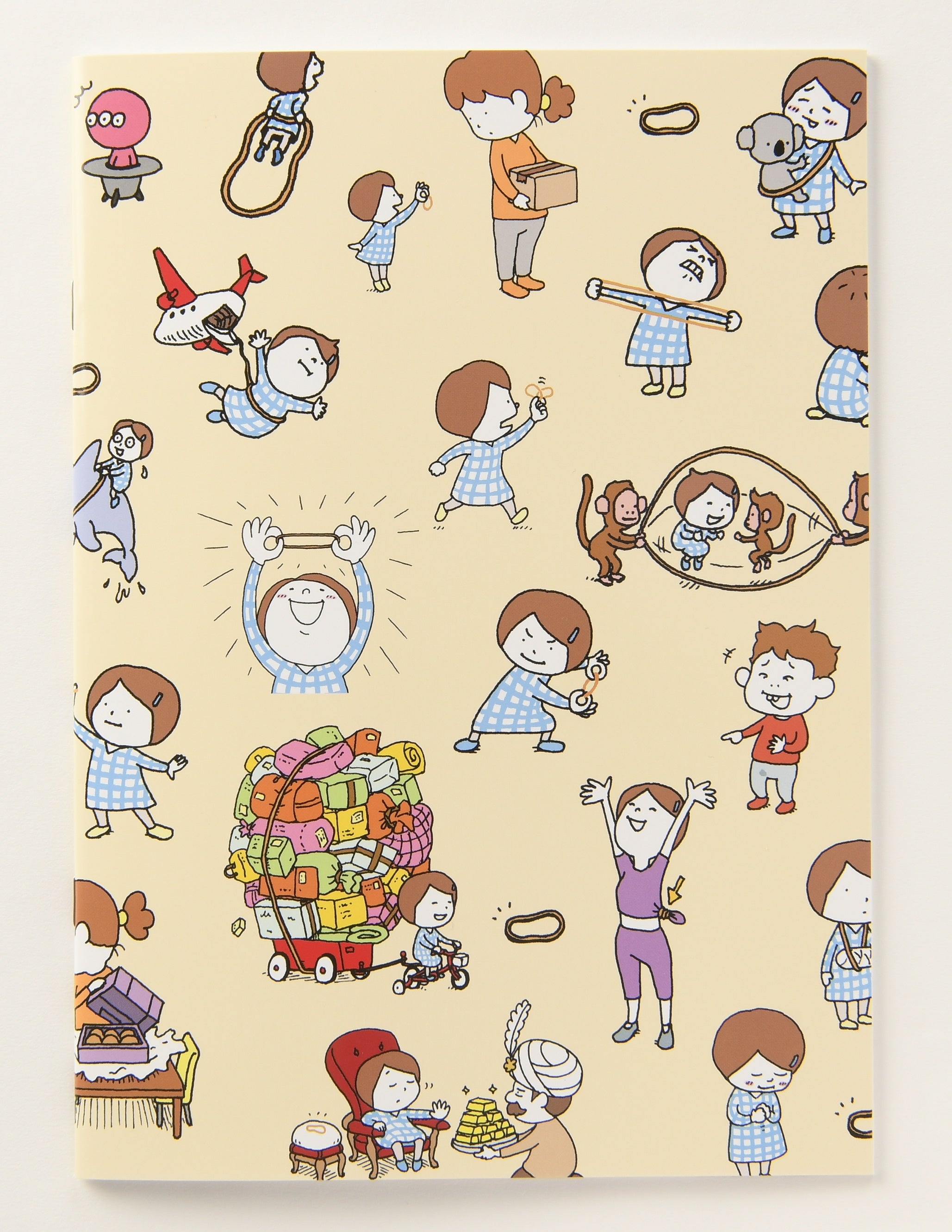9歳からは、まかせて、はなれて、ちょっと聴く
9歳からは、まかせて、はなれて、ちょっと聴く
通常価格
¥1,320
セールスプライス
¥1,320
通常価格
税込み。
教員免許を持たない私が、小学校の現場とかかわりたいと思ったきっかけがあります。
今から十五年ほど前、大学で教鞭をとっていたときのことです。三十年前にも教鞭をとっていましたが、学生が、そのときと大きく変わっていたことに驚いたのです。それがきっかけでした。
なぜ、こんなにも自己表現力が低くなったのだろうか。積極的にコミュニケーションをとろうとしなくなったのは、なぜだろうか。自分の思いをちゃんと伝えようとする力がなぜ低くなったのだろうか。そんな疑問から始まりました。
授業をまともに聞かない、授業に出席はしているけれど積極的に参加しないなど、当時の学生に対して、否定的な感想を抱くことが多くありました。そして、この学生たちが社会人になったときに、どうなるのだろうと思いました。私たち教員は、理想的な子どもを育てているのではなく、「人」を育てているのだと思うと、「社会人として、ちゃんと自立できる人を育てなくてはならないのでは」と思い、悶々とした日々を過ごしていました。
そんなことを考えながら、学生たちと話をしました。一体、今の学生の特徴や性格は、どこに起因するのかを探ってみたいと思ったからです。そして、学生たちといろいろな話をして、ある結論に達しました。小学校時代に要因があるのだと。
そして、小学校時代に、発表したり、自己主張をしたり、相手の言うことを聴いたり、双方向的なコミュニケーションをしたりということがあまりなかったことを知りました。
そこで、小学校の子どもたちが成長する段階で、多くの生きる力を身につけられるよう、何かを与えたいと願いました。
それから、十五年という長い年月が経ちました。その間に、子育てに関する著書を何冊か執筆しましたが、民間人校長として学校現場にかかわるようになってから、子どもの育ちについて、さらに深く考えるようになりました。
小学校という特性上、六年間での子どもの成長の幅は、とても広いものです。
その中でも、九、十歳の、中学年と呼ばれる年齢は、児童期の育ちの中で、とても微妙な立場にいるのだということに気がつきました。
ある方に言われたことがあります。学校外部の方で、民間企業に勤めている方です。
「一年生は大変でしょうね。まだ学校に慣れていないのだから。でも、三、四年生になると、だいぶ楽になるんじゃないですか?」と。
そうか、外から見たら、三、四年生になると楽だと思われるのかと、その一般的なイメージに驚きました。ほかにも何人かに同じことを言われました。
自問しました。「本当に楽なのだろうか?」と。
そのときに、思い出しました。私が以前勤めていた仕事場でのことを。
以前私は、四年間、東京ディズニーリゾートを運営・経営する株式会社オリエンタルランドが、千葉県浦安市舞浜に設立した、子どもの遊びの施設「キャンプ・ネポス」の館長を務めていました。
通常のプログラムでは、三歳から十歳の子どもに楽しんでもらっていました。同じプログラムに三歳から十歳の子どもが参加するのですから、子どもたちの反応は当然違ってきます。キャスト(スタッフ)も子どもの年齢に応じて、話し方や対応の仕方を少しずつ変化させていかなくてはなりません。
幼い子どもには、安心感を与えながら穏やかにプログラムを進めます。九、十歳くらいになると、友人として、仲間として、プログラムを進めていきます。その対応を間違えると、子どもたちから思いもよらぬ反応が返って来て、驚くことになります。軌道修正をしようと思っても後の祭りです。子どもには、そのプログラムがつまらないプログラムになってしまうのです。「二度と来たくない」と思わせてしまいます。ちょっとしたことで子どもの評価が決まるので、細心の注意が必要でした。
キャストの対応の様子を見ながら思いました。九、十歳くらいにもなると、その対応はなかなか大変だということです。この年ごろの子どもは微妙な感情を持っています。手を抜いたら、すぐに見抜かれてしまいます。見抜かれないためにも、さまざまな術を考えながら対応をしなくてはならないのです。この年ごろの子どもの心を豊かに育てるもの。それこそが、大人の対応力にかかっています。それを確信したのも、さまざまな年齢の子どもを見て、心の動きを感じ取ったからです。
ところで、コミュニケーション力や豊かな心の育ちといったものは、大人が子どもとただ一緒にいれば育つというものではありません。大人の働きかけがないかぎり育たないものです。子どもの芽を育て、花を咲かせるために、お母さんやお父さんなどの大人の力が必要です。特に、九、十歳からの子どもには、確たる働きかけが必要です。漫然とした働きかけでは、効果は全く現れません。せっかく子どもが素晴らしい芽を出しても、枯らしてしまうだけです。
そこで本書では、九歳からの子どもに対する働きかけで必要な法則を、三つに分けて紹介しています。
微妙な心理の動きを見せ始める子どもたち。来るべき思春期を前に、その言動を誤解することなく、正面から受け止めるための参考にしていただけたらと思います。
学校現場での体験を基に、さまざまな子どもの言動も紹介しております。きっと、読者のみなさんの周りでも、同じようなことが日々起こっているのではないでしょうか。私のもとへ子育ての相談に来る保護者の方もたくさんいます。お母さんやお父さんの悩みは、一人だけのものではありません。多くの方が同じように感じていることなのです。本書を読み進めながら、少し気が楽になったと思っていただければ幸いです。
さあ、変わり始めた子どもたちを、心から理解する旅に出かけましょう。 (「はじめに」より)
尾塚理恵子
縦:31×横:18.2 全頁数:31日分17枚綴(表紙含む)
重量234g厚さ1.2cm
今から十五年ほど前、大学で教鞭をとっていたときのことです。三十年前にも教鞭をとっていましたが、学生が、そのときと大きく変わっていたことに驚いたのです。それがきっかけでした。
なぜ、こんなにも自己表現力が低くなったのだろうか。積極的にコミュニケーションをとろうとしなくなったのは、なぜだろうか。自分の思いをちゃんと伝えようとする力がなぜ低くなったのだろうか。そんな疑問から始まりました。
授業をまともに聞かない、授業に出席はしているけれど積極的に参加しないなど、当時の学生に対して、否定的な感想を抱くことが多くありました。そして、この学生たちが社会人になったときに、どうなるのだろうと思いました。私たち教員は、理想的な子どもを育てているのではなく、「人」を育てているのだと思うと、「社会人として、ちゃんと自立できる人を育てなくてはならないのでは」と思い、悶々とした日々を過ごしていました。
そんなことを考えながら、学生たちと話をしました。一体、今の学生の特徴や性格は、どこに起因するのかを探ってみたいと思ったからです。そして、学生たちといろいろな話をして、ある結論に達しました。小学校時代に要因があるのだと。
そして、小学校時代に、発表したり、自己主張をしたり、相手の言うことを聴いたり、双方向的なコミュニケーションをしたりということがあまりなかったことを知りました。
そこで、小学校の子どもたちが成長する段階で、多くの生きる力を身につけられるよう、何かを与えたいと願いました。
それから、十五年という長い年月が経ちました。その間に、子育てに関する著書を何冊か執筆しましたが、民間人校長として学校現場にかかわるようになってから、子どもの育ちについて、さらに深く考えるようになりました。
小学校という特性上、六年間での子どもの成長の幅は、とても広いものです。
その中でも、九、十歳の、中学年と呼ばれる年齢は、児童期の育ちの中で、とても微妙な立場にいるのだということに気がつきました。
ある方に言われたことがあります。学校外部の方で、民間企業に勤めている方です。
「一年生は大変でしょうね。まだ学校に慣れていないのだから。でも、三、四年生になると、だいぶ楽になるんじゃないですか?」と。
そうか、外から見たら、三、四年生になると楽だと思われるのかと、その一般的なイメージに驚きました。ほかにも何人かに同じことを言われました。
自問しました。「本当に楽なのだろうか?」と。
そのときに、思い出しました。私が以前勤めていた仕事場でのことを。
以前私は、四年間、東京ディズニーリゾートを運営・経営する株式会社オリエンタルランドが、千葉県浦安市舞浜に設立した、子どもの遊びの施設「キャンプ・ネポス」の館長を務めていました。
通常のプログラムでは、三歳から十歳の子どもに楽しんでもらっていました。同じプログラムに三歳から十歳の子どもが参加するのですから、子どもたちの反応は当然違ってきます。キャスト(スタッフ)も子どもの年齢に応じて、話し方や対応の仕方を少しずつ変化させていかなくてはなりません。
幼い子どもには、安心感を与えながら穏やかにプログラムを進めます。九、十歳くらいになると、友人として、仲間として、プログラムを進めていきます。その対応を間違えると、子どもたちから思いもよらぬ反応が返って来て、驚くことになります。軌道修正をしようと思っても後の祭りです。子どもには、そのプログラムがつまらないプログラムになってしまうのです。「二度と来たくない」と思わせてしまいます。ちょっとしたことで子どもの評価が決まるので、細心の注意が必要でした。
キャストの対応の様子を見ながら思いました。九、十歳くらいにもなると、その対応はなかなか大変だということです。この年ごろの子どもは微妙な感情を持っています。手を抜いたら、すぐに見抜かれてしまいます。見抜かれないためにも、さまざまな術を考えながら対応をしなくてはならないのです。この年ごろの子どもの心を豊かに育てるもの。それこそが、大人の対応力にかかっています。それを確信したのも、さまざまな年齢の子どもを見て、心の動きを感じ取ったからです。
ところで、コミュニケーション力や豊かな心の育ちといったものは、大人が子どもとただ一緒にいれば育つというものではありません。大人の働きかけがないかぎり育たないものです。子どもの芽を育て、花を咲かせるために、お母さんやお父さんなどの大人の力が必要です。特に、九、十歳からの子どもには、確たる働きかけが必要です。漫然とした働きかけでは、効果は全く現れません。せっかく子どもが素晴らしい芽を出しても、枯らしてしまうだけです。
そこで本書では、九歳からの子どもに対する働きかけで必要な法則を、三つに分けて紹介しています。
微妙な心理の動きを見せ始める子どもたち。来るべき思春期を前に、その言動を誤解することなく、正面から受け止めるための参考にしていただけたらと思います。
学校現場での体験を基に、さまざまな子どもの言動も紹介しております。きっと、読者のみなさんの周りでも、同じようなことが日々起こっているのではないでしょうか。私のもとへ子育ての相談に来る保護者の方もたくさんいます。お母さんやお父さんの悩みは、一人だけのものではありません。多くの方が同じように感じていることなのです。本書を読み進めながら、少し気が楽になったと思っていただければ幸いです。
さあ、変わり始めた子どもたちを、心から理解する旅に出かけましょう。 (「はじめに」より)
尾塚理恵子
縦:31×横:18.2 全頁数:31日分17枚綴(表紙含む)
重量234g厚さ1.2cm
100 個の在庫があります
受け取り可能状況を読み込めませんでした